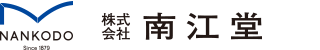ここが知りたかった緩和ケア
こちらの商品は改訂版・新版がございます。
| 著 | : 余宮きのみ |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-26458-2 |
| 発行年月 | : 2011年10月 |
| 判型 | : A5 |
| ページ数 | : 266 |
在庫
定価3,190円(本体2,900円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

緩和ケアの患者さんに漫然とNSAIDsを投与したり、長期間経鼻胃管を留置していませんか? 下痢の訴えは便秘が原因? などなど緩和医療の現場で意外に知られていない薬剤の使い方やケアのコツを、各項目冒頭の「概念図」でつかみ、読んで納得できる構成。役立つ情報が満載。
I 疼痛治療
A 非オピオイドと鎮痛薬
1 疼痛治療では腎障害をチェック!
2 NSAIDsを使用する前に消化性潰瘍のリスクを考える
3 アセトアミノフェンを活用する
B オピオイド
4 オピオイドをうまく使い分けるには
5 オピオイド注射の導入と増量間隔
6 フェンタニル貼付剤投与中の患者で急に強い苦痛がでたら
7 フェンタニル貼付剤の1日製剤と3日製剤、どのように使うか
8 オピオイドローテーション:換算比は万能ではない
9 オピオイドの非経口投与への変更
10 オピオイド投与中に腎障害が悪化した時
11 肝代謝が低下している状態でオピオイドを使用するには
12 レスキュードーズ:説明が大事!
13 レスキュードーズ:剤形の選択と投与量の決定
C 鎮痛補助薬
14 鎮痛補助薬を使用するタイミング
15 鎮痛補助薬の選択方法
16 鎮痛補助薬を使用するポイント
17 どの鎮痛補助薬も無効という時のポイント
D アセスメント
18 痛みのスケールの使いこなし法
19 痛みのスケールだけじゃない、便利なツール
E 鎮痛薬への抵抗解消
20 疼痛治療の意義を考える
21 オピオイドに抵抗がある時
II 疼痛治療がうまくいかない時
22 痛みと眠気の組み合わせで解決の糸口をつかもう
23 いま一度、痛みの原因を評価する
24 「痛みがとれない」という中身をアセスメントする
25 持続痛なのか突出痛なのか
26 レスキュードーズの効果判定による対処方法
27 夜間だけ痛みが増強する場合
28 鎮痛薬の対象かどうかを見極めよう
29 しびれを訴えたら脊椎転移を見逃さない
30 病的骨折のリスクをどう評価するか
31 骨転移による体動時痛への対応:薬に頼りすぎない対応
32 悪性腸腰筋症候群を見逃さない
33 ステロイドパルス療法の出番
34 どうしても痛みが和らがず苦痛が強い時どうするか
III 痛み以外の症状の緩和
A 全身症状
35 オピオイドの副作用と思ったらすべき3つのこと
36 これで見逃さない、薬剤性錐体外路症状
37 困った時のステロイド
38 ステロイドを開始する時の注意点
39 見逃してはならないオンコロジーエマージェンシー:脊髄圧迫
40 見逃してはならないオンコロジーエマージェンシー:高カルシウム血症
41 ステロイドの具体的な投与方法
42 終末期の輸液・栄養管理の考え方
43 激しい苦痛のある時の助け舟
B 消化器症状
44 悪心が緩和されない時:原因を考え、原因治療を行う
45 悪心が緩和されない時:症状緩和を行う
46 オピオイド投与中の患者で悪心や下痢:実は、便秘や宿便
47 排便コントロールの重要性をもう一度
48 排便コントロールのポイント:予防とセルフケア
49 消化管閉塞時の治療方針:「食べたい」を叶えるために
50 「食べたい」を叶える薬物療法
51 必ず「舌をだしてください」とお願いしよう
52 がん性腹水による腹部膨満感
C 睡眠障害、精神症状
53 眠気が強い時、せん妄の時にすべきこと
54 せん妄の薬物療法
55 飲酒歴を問診しよう:アルコール離脱でせん妄が
56 抗精神病薬の換算、比較
57 不眠時の問診
58 注射剤で睡眠コントロールしているが、どうしても眠れない時
IV 鎮静
59 鎮静の基本
60 鎮静の方法
61 鎮静前に確認しておく事項
62 鎮静について家族へどのように説明したらよいか
V コミュニケーション
63 最短の時間で最大の効果をあげるチューニング
64 化学療法やる・やらない:患者の選択への援助
65 コミュニケーションは質問力
66 難しい質問には逆質問
67 家族ケア
68 チーム医療の“うまくいってるつもり”が危ない!
VI 麻薬の取り扱いについてのQ&A
索引
私は医学生の時に、がんで苦しんでいる患者さんの「緩和ケア」に携わろうというきっかけを与えられました。時は1987年、たまたまWHOから『がんの痛みからの解放』の日本語版が出版された年でした。
当時の日本は「緩和ケア」という言葉を耳にすることもなく、「ターミナルケア」などと呼ばれてオピオイドの使用もままならない時代でした。そのような時代からこれまで、周囲の先輩たちから教えを受け、緩和ケアに関する本を読みながら、いかに目の前の患者さんの苦痛を和らげるかということに力を尽くしてきました。
それでもなお、苦痛を和らげることができない、緩和の難しい激しい苦痛に遭遇し、本を調べて得られることでは太刀打ちできないというケースにたびたび遭遇しました。いつも「どうしたらこの患者さんの苦痛を一刻もはやく和らげられるのか」と考えてきました。そんな逡巡を繰り返すうちに、こうした解決の糸口は基本をさらに掘り下げたところにあることに気づき、すこしずつ自分なりの工夫が生まれました。このような難渋症例は、臨床研究では対象から除外されること、そしてさまざまな事例に対処できる臨床は個々の臨床家が経験の中で培った小さなノウハウの集積であるのだな…ということにも気づきました。ひとつひとつのノウハウは小さなものでも、それが大きく患者さんに影響する、しかし、それは本にはあまり取り上げられないこともわかりました。
このような内容を医療者向けの勉強会で話していたところ、南江堂の方から本にしてみないかとの提案があり、本書の企画がスタートしました。コンセプトは「教科書には載っていない、でもそこが本当は知りたかったんだ」という、まさに私が20余年来抱いてきた思いに答えようとするものです。
がんで苦しんでいる患者さんたちの声が「がん対策基本法」に結びつき、ここ数年で緩和ケアの教育環境は大きく好転しました。「ターミナルケア」だけでなく、「診断時からの緩和ケア」の重要性も叫ばれるようになりました。いまでは基本的な緩和ケア教育も盛んになり、緩和ケアについての書物もたくさん出版されています。しかし教育を受けて得た知識をもってしても、対応できない症例に出会うことがあるはずです。
このような時にどうするか?
ひとつは、基本にもどること。基本的知識の理解を深めることが、技術の向上に直結します。もうひとつは、小さなノウハウを知ることです。本書では、よく遭遇する症状や病態について、他書では触れられることのなかった内容を多く盛り込みました。もちろん、死が差し迫った患者さんの問題の中には、自分の持てる資源の限界に達し、鎮静を行う必要がでてくることもあります。そのような場面であっても最善を尽くすこと、鎮静を行う場合でも適切な手順をふむことについても触れました。
目の前の患者さんの苦痛を思うように和らげられない、そんな時に本書が一助となれば著者としてこれに勝る喜びはありません。
2011年初秋
余宮きのみ
がん診療の早期から緩和ケアを提供することの重要性が再認識されている。進行非小細胞肺癌患者を対象とした無作為比較試験で、早期から緩和ケアを併用した群では標準的治療群に比較し有意にQOLが良好であり抑うつ症状の割合が少なく、さらに生存期間の中央値が有意に長かったことが報告され(JSTemel、NEJM、2010)、緩和ケアの重要性と有効性が示されたことは喜ばしい。
こうして緩和ケアのニーズと活躍の場が広がり、オンコロジストとして、緩和ケアチームのメンバーとして、または緩和ケアの専門家を目指そうとして、それぞれの立場で緩和ケアを学ぶ人が増え、緩和ケアに関する書物は急激に増えている。その中で、まさに「そう、そこが知りたかった!」という、臨床疑問のポイントを適切に押さえてくれ、丁寧にわかりやすく解説してくれるテキストが出版された。
本書の特徴は、具体的であり実践的であることだ。「鎮痛補助薬を使用するタイミング」、「鎮痛補助薬の選択方法」、「眠気が強い時、せん妄の時にすべきこと」などの章は、まさに毎日出会う「さあ、困ったぞ」という臨床疑問であろう。小難しいエビデンスを振りかざすことはせず、しかし「えらい誰かがいった」とか「私はこうしている」だけのレベルにとどまるのではなく、説得力のある丁寧な解説で、臨床での指針を与えてくれるのである。さらに学習したい人のために信頼できる文献が付記されているのも心強い。随所で「言葉かけ」の例が示され、問診や面談時の具体的なボキャブラリーの参考になるだろう。
もう一つの特徴として、非常に読みやすい工夫がされていることがあげられる。考え方のアルゴリズムが示され、思考のプロセスが図示され、臨床で役立つ図表が示されているので、本文の理解が大いに助けられる。また、臨床疑問の小項目に分かれているので、必要なときに必要な所だけをチェックするのもよし、興味のあるところから少しずつ読み続けていくのもよし、手軽に利用できるところがうれしい。文章がやわらかくエレガントで読みやすいのは、著者の人柄そのものなのかもしれない。
著者は序文で、むずかしい症例に出会ったときの対応法として「基本に戻り、基本的知識の理解を深めること」と「小さなノウハウを知ること」をあげている。ここにはそうした臨床の「知識」と「知恵」がぎっしり詰まっていると思う。
評者● 田中桂子
臨床雑誌内科109巻3号(2012年3月号)より転載