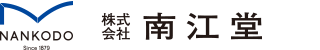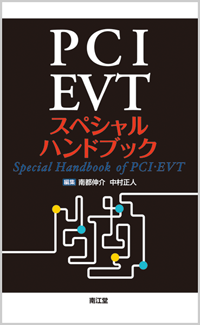PCI・EVTスペシャルハンドブック
こちらの商品は改訂版・新版がございます。
| 編集 | : 南都伸介/中村正人 |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-26096-6 |
| 発行年月 | : 2010年7月 |
| 判型 | : B6変 |
| ページ数 | : 290 |
在庫
定価4,730円(本体4,300円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

冠動脈インターベンション(PCI)と末梢血管インターベンション(EVT)に関する総合的な知識を提供するために、病態、診断、薬剤、手技について、必須な情報をコンパクトにまとめた。解説は各領域のエキスパートによって執筆され、エビデンスを重視するものの、実臨床における各エキスパートならではの工夫などもわかる。白衣のポケットに入れて、知りたい情報がすぐにわかり、若手医師の知識整理にも役立つ一冊。
I PCIコース
A 知っておくべき病態
1.安定狭心症
2.急性冠症候群
3.無症候性心筋虚血
4.PCIの適応を考える
B 画像診断技術
1.冠動脈造影・読影のコツ
2.心臓CTの活用:スクリーニングからPCIへの応用まで
3.PCI術者に必要なRI心筋シンチグラムの知識
4.IVUSの手技と読影法の基本
5.その他のモダリティによる冠動脈評価法
C これから始めるための基礎知識
1.よく聞くPCI用語
2.PCIデバイスの構造と種類
3.アプローチ
4.PCIに特異的な合併症
D PCI手技のプロの技
1.橈骨動脈アプローチのコツ
2.複雑病変でのTips&Tricks
II EVTコース
A 頚動脈狭窄症・腎動脈狭窄症
1.頚動脈狭窄症
2.腎動脈狭窄症
B 下肢閉塞性動脈硬化症
C これから始めるための基礎知識
1.よく聞くEVT用語
2.EVTデバイスの用い方
3.EVTに特異的な合併症
III インターベンションの基礎知識:PCI・EVT共通事項
A 薬剤に関する知識
1.造影剤
2.Heparin・HITS
3.抗血小板薬
B 合併症に関する知識
1.コレステロール塞栓症
2.止血合併症と止血デバイス
3.放射線防護
C その他
1.補助循環
2.二次予防のための薬剤とガイドライン
3.同意書
食文化の欧米化、人口の高年齢化、交通の発達による運動不足などの要因による心血管系の動脈硬化を起因とする疾病の増加は大きな社会問題である。一次予防がもっとも大切な課題であることには違いないが、狭窄病変が出現してしまった症例に対しては血行再建術が必要となる。動脈硬化性狭窄病変に対するカテーテル治療(心血管インターベンション)は、バイパス術とともに血流改善には大変有効な血行再建術のひとつである。
心血管インターベンションは、1964年にCharles T. Dotter先生により下肢の狭窄病変がカテーテルで拡張されたことにより始まったと言える。その後、1974年にAndreas Gruentzig 先生がバルーン付きのカテーテルを考案し、効率よく狭窄病変を拡大できるようになった。彼はこのバルーン血管形成術を1977年に冠動脈に応用し、下肢動脈の治療により始まったカテーテル治療は、冠動脈インターベンションにおいて大いに発展した。現在では、冠動脈・下肢のみならず、全身の血管系の治療がカテーテルで可能になり、また使用されるデバイスも豊富になった。そのぶん、インターベンション治療に際しては、多くの新しい知識が要求される。また、その手技だけでなく、病態の理解、画像診断や薬剤の知識も必要である。
そこで、本書では、この冠動脈インターベンションと末梢インターベンション(PCI・EVT)に関する病態・診断・薬剤・手技のコツについて、若手医師やコメディカルが知りたい事項をコンパクトにまとめて提供し、今後この領域を担う次世代に供するものとすることを目的に企画した。解説は各領域のエキスパートによる執筆をお願いし、エビデンスを重視するものの、実臨床における各エキスパートの工夫や思いを述べていただいた。読者の日々の臨床医療に役立てば幸いである。
2010年7月
編集者
小さいが役に立つこと請け合いの“スペシャル”な本
循環器内科の臨床は、診断においても治療においても日進月歩である。冠動脈インターベンション・末梢インターベンション(PCI・EVT)は、その中でもとくに進歩の著しい分野であり、まさに循環器診療の花形といえよう。1964年にDotterがEVTを、1974年にはGruentzigがPCIをはじめ、1987年には冠動脈ステントの有効性が報告された。筆者が循環器の臨床をはじめてまもないときであったが、『NEJM』誌に発表されたステントに関する論文を読んだときの衝撃を今も覚えている。「こんな金網みたいなのを冠動脈に入れて大丈夫なのか」というのが正直な感想であったが、今やステントは常識であり、時代は薬剤溶出性ステントである。わが国では、諸外国以上に多くの循環器医が実際にPCI・EVTに関わっているが、すべての循環器医が、急速に進歩するPCI・EVTに関する知識を素早く吸収し、理解する必要があろう。
そこで当然PCI・EVTに関する成書も沢山出ているわけであるが、今回新たにPCI・EVTに関するハンドブックが出版された。PCI・EVTの世界では大変ご高名な、南都伸介先生と中村正人先生のお二人の編集された本とは一体どのようなものであろうかと手にとってみたところ、今までのものとは大変異なった本であることに驚かされた。小さいながらも必要にして十分なばかりか、かゆいところに手が届くような心遣いがされている、まさに“スペシャル”な本なのである。いつも携帯するようなハンドブックは、とかく紙面が限られるために、文字ばかりが並び、無味乾燥な本になるところが、本書では多数の写真や表が掲載されていて、読んで楽しいばかりでなく、大変理解しやすくなっている。また所々に配されている「MEMO」欄は重要なポイントを短くまとめており、理解と記憶を大いに助けている。臨床上よく遭遇する問題に対するトラブルシューティングも沢山盛り込まれており、まさにプロの技を伝授しているような感がある。
本書は、わが国を代表する多数のPCI・EVTのエキスパートによって書かれており、きわめて実践的である。ハンドブックなので、通常は医師が普段から携帯したりカテ室に置いておくのだろうが、本書に関しては通読しても面白く、PCI・EVTの世界が臨場感をもって体験できる。そこが“スペシャルハンドブック”の所以であろうか。PCI・EVTを実際に行っている医師はもとより、これからPCI・EVTをやってみたいと考えている若い医師やPCI・EVTに興味のある医師、コメディカル、すべての方に勧めたい特別な本である。
評者● 小室一成
臨床雑誌内科106巻6号(2010年12月増大号)より転載