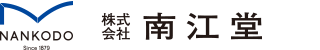抗悪性腫瘍薬コンサルトブック
薬理学的特性に基づく治療
こちらの商品は改訂版・新版がございます。
| 編集 | : 南博信 |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-25373-9 |
| 発行年月 | : 2010年3月 |
| 判型 | : B6変 |
| ページ数 | : 362 |
在庫
定価5,170円(本体4,700円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

がん薬物療法に使用される主な抗悪性腫瘍薬の、適応・副作用、作用機序・耐性機序、臨床薬理学的特徴、投与スケジュールなどの臨床に必要な知識をコンパクト・明解に解説。臨床導入が進む分子標的治療薬から細胞傷害性抗がん薬まで使用のポイントがわかる。各がん種の代表的なレジメンも掲載。がん治療認定医、がん薬物療法専門医の取得を目指す医師には必須の知識を凝縮した一冊。
I 抗悪性腫瘍薬の臨床薬理学―総論
A がん薬物療法の基本的考え方
B 抗悪性腫瘍薬の分類
C 薬物動態・薬力学の個体差
D 薬理ゲノム学
E 高齢者の薬物動態・薬力学
F 臓器障害時の薬物動態・薬力学
G 分子標的治療薬の臨床使用の位置づけ
H 蛋白結合
I drug delivery system(DDS)
II 各薬剤の臨床薬理学的特長と使い方
1 分子標的治療薬
A 小分子化合物
1 イマチニブ
2 ソラフェニブ
3 スニチニブ
4 ゲフィチニブ
5 エルロチニブ
6 ボルテゾミブ
B 抗体薬
1 トラスツズマブ
2 リツキシマブ
3 ベバシズマブ
4 セツキシマブ
5 ゲムツズマブオゾガマイシン
6 イブリツモマブチウキセタン
2 抗がん薬
A 代謝拮抗薬
(1)アルキル化薬
1 シクロホスファミド
2 イホスファミド
3 ブスルファン
4 メルファラン
5 ダカルバジン
6 プロカルバジン
7 テモゾロミド
(2)葉酸拮抗薬
1 メトトレキサート
2 ペメトレキセド
(3)ピリミジン拮抗薬
1 フルオロウラシル
2 カペシタビン
3 ドキシフルリジン
4 S-1(テガフール・ギメラシル・オテラシル)
5 UFT(テガフール・ウラシル)
6 テガフール
7 シタラビン
8 ゲムシタビン
(4)プリン拮抗薬
1 メルカプトプリン
2 フルダラビン
3 クラドリビン
B 抗生物質
(1)アントラサイクリン系
1 ドキソルビシン
2 liposomal doxorubicin
3 ダウノルビシン
4 エピルビシン
5 イダルビシン
6 アムルビシン
7 ミトキサントロン
(2)その他の抗生物質
1 マイトマイシンC
2 アクチノマイシンD
3 ブレオマイシン
C 微小管阻害薬
(1)ビンカアルカロイド
1 ビンクリスチン
2 ビンブラスチン
3 ビノレルビン
(2)タキサン
1 パクリタキセル
2 ドセタキセル
D 白金製剤
1 シスプラチン
2 カルボプラチン
3 ネダプラチン
4 オキサリプラチン
E トポイソメラーゼ阻害薬
(1)トポイソメラーゼI阻害薬
1 イリノテカン
2 ノギテカン
(2)トポイソメラーゼII阻害薬
1 エトポシド
III 各領域におけるがん薬物療法のとらえ方
A 頭頚部扁平上皮がん
B 肺がん
C 消化器がん
D 乳がん
E 造血器がん
F 婦人科がん
G 腎がん
H 泌尿器がん
I 悪性黒色腫
J 原発不明がん
K 骨・軟部肉腫
L 脳腫瘍
索引
抗悪性腫瘍薬は治療域が狭いため、薬物動態あるいは薬力学の個人差が重篤な毒性や効果の減弱を招く。したがって、各薬物の薬物動態など臨床薬理学的特長を十分理解したうえでがん薬物療法にあたる必要がある。高齢者や臓器障害時には臨床薬理学的情報なくして治療はできない。抗悪性腫瘍薬の最適な使用方法についてしばしば臨床家より相談を受けるが、抗悪性腫瘍薬の臨床薬理学的知見をまとめた良い書籍が日本には存在しなかったことに不便を感じていた。本書は実地のがん診療において、各薬剤を使用する際に薬剤に関する知識を整理したり、高齢者や臓器障害時の治療計画を科学的に個別化する際に役立てていただく目的で企画した。執筆はそれぞれの薬剤に詳しい専門家にお願いした。
近年開発されている抗悪性腫瘍薬の多くは分子標的治療薬であり、実地医療で単剤として、あるいは従来の化学療法との併用で使用されている。また、最近の薬理ゲノム学の進歩はめざましく、その成果ががん薬物療法に取り入れられている。本書では抗体薬も含む分子標的治療薬も扱い、実地のがん医療で必要と思われる薬理ゲノム学の情報も提供することを心がけた。
がん薬物療法に携わっている医師およびコメディカルのための教科書として、あるいは医療現場で携帯するリファレンスとして利用できるように、本書では、まず臨床薬理学やがん薬物療法の基本的な考え方など必要最低限のエッセンスをまとめ、次に各薬剤の解説、最後に標準的に使用されるレジメンをまとめている。
実地医療のみならず、抗悪性腫瘍薬の臨床開発にも臨床薬理学的な知識は不可欠である。特に早期開発は臨床薬理学の十分な知識を持った臨床腫瘍医が実施する必要がある。また、がん薬物療法の進歩には新薬の開発ばかりでなく、既存の薬剤をより安全で有効に使用する方法を確立する臨床薬理学的研究も欠かせない。新薬の開発や市販薬を用いた臨床試験の計画や実施に際しても本書が役立つものと確信している。本書を実地医療におけるがん薬物療法の科学的個別化やよりよい薬物療法の開発に役立てていただければ幸いである。
2010年2月
南博信
抗悪性腫瘍薬は殺細胞性の抗がん薬と、分子標的治療薬に大別される。抗がん薬は細胞のDNA、細胞骨格に直接作用したり、がん細胞のDNA、RNA、蛋白の代謝を修飾することにより抗腫瘍効果を示す。一方、分子標的治療薬は、がん細胞あるいはがん環境の生物学的特性を選択的に修飾することが作用機序となっている。21世紀に入り、分子生物学的研究の成果をベースとして数多くの分子標的治療が開発され臨床試験が行われるとともに、実地医療にも導入され目覚ましい臨床効果を示し、新たな標準的治療の確立に貢献している。最近、一つのカテゴリーの治験中の分子標的治療薬の数が10種類以上あることも不思議ではなくなってきている。
南博信教授が編集された本書には、他の教科書にはみられない特徴がある。まず、分子標的治療薬の項が抗がん薬の項の前に存在する。これは時代の流れを反映したものと思われる。執筆者はほとんど例外なく現在活躍中の中堅の先生方であり、多くは日本臨床腫瘍学会のがん薬物療法専門医の方々である。構成は総論、各薬剤の臨床薬理学的特長、各領域におけるがん薬物療法の捉え方となっており、よくバランスがとれている。
他書に比べ編集者の意図である「各薬剤の薬理学的特性」に関する記述が薬剤ごとに充実しており、おのおのの薬剤をどのように使うべきかについて正しい知識が得られるように記載されている。しかし、抗悪性腫瘍薬の場合、必ずしも理論と現実が一致しないこともある。たとえば細胞周期を念頭に置けば、当然少量分割あるいは持続投与がよいと推定されるにもかかわらず、臨床では3〜4週間隔で投与したほうが副作用も少なく、高い効果を得られることもある。
また同じ系統の薬剤開発の過程で、構造式のわずかな変化によって半減期が著しく延長し優れた抗腫瘍効果をもたらすこともある。最近注目を集めているのは薬理学、薬力学を左右する薬理遺伝学(pharmacogenomics:PGX)的変化に関する研究である。これは抗がん薬、分子標的治療薬のいずれに対しても重要な研究テーマと思われる。PGXの研究によって分子標的治療薬の効く対象(予測因子)の同定が可能になるとともに、抗がん薬の代謝酵素に関わるSNP(一塩基多型)が明らかにされてきた。とくに、がん増殖のdriving forceとなる遺伝子異常の同定とそれに対する創薬はもっとも重要な課題であり、患者に僥倖を与えると思われる。UGT1A1*28、*6、CDA*3などの同定により抗がん薬の毒性を強く受ける患者に対する投与量決定の研究も実際行われ、PGX研究の進歩に基づく真の個別化治療が可能となりつつある。
現在、分子標的治療薬の臨床試験と承認は急速に進んでおり、本書発刊後もさまざまな薬剤が使用可能となっている。up to dateに改訂することが必要と思われる。
評者● 西條長宏
臨床雑誌内科106巻4号(2010年10月号)より転載