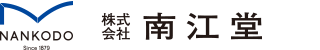運動器スポーツ外傷・障害の保存療法 下肢
| 監修 | : 福林徹 |
|---|---|
| 編集 | : 熊井司/石橋恭之 |
| ISBN | : 978-4-524-24639-7 |
| 発行年月 | : 2020年11月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 316 |
在庫
定価7,260円(本体6,600円 + 税)
サポート情報
-
2021年03月31日
競技スポーツ選手に対する「糖質コルチコイド」注射経路の禁止について
正誤表
-
2022年08月04日
第1刷
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

整形外科医をはじめとしたスポーツ関連医療スタッフを対象に、スポーツ外傷・障害の保存療法についての最新の知識を提供し、その具体的方法と進歩をビジュアルな紙面で解説するシリーズ(全3巻)。下肢編では、多岐にわたる疾患ごとに運動療法の適切な選択や指導方法について細かく解説。また、物理・装具療法の気づきにくいポイント、最近のトピックスであるPRPや体外衝撃波治療のポイントから最新の実績まで網羅した。
1 疫学
2 保存療法に必要な機能解剖とバイオメカニクス
3 各種保存療法の基礎知識
1.運動療法
2.物理療法
3.装具療法
4.多血小板血漿(PRP)
5.体外衝撃波治療(ESWT)
6.高気圧酸素治療(HBO)
7.局所注射療法
4 疾患別保存療法
1.骨盤・股関節
A.大腿骨寛骨臼インピンジメント
B.グロインペイン症候群
C.骨盤の疲労骨折(坐骨,恥骨)
D.股関節脱臼
E.大腿肉離れ(大腿四頭筋,ハムストリングス)
F.筋挫傷・骨化性筋炎
G.大腿骨疲労骨折
2.膝関節
A.Osgood-Schlatter病(Sinding-Larsen-Johansson病含む)
B.ジャンパー膝(膝蓋腱炎,大腿四頭筋腱付着部炎)
C.有痛性分裂膝蓋骨(膝蓋骨疲労骨折含む)
D.腸脛靱帯炎
E.鵞足炎
F.前十字靱帯損傷
G.後十字靱帯損傷
H.側副靱帯損傷
I.半月板損傷
J.関節軟骨損傷
K.膝蓋大腿関節障害(反復性膝蓋骨脱臼,膝蓋大腿関節症)
3.下腿
A.アキレス腱断裂
B.アキレス腱症
C.脛骨・腓骨疲労骨折
D.腓腹筋肉離れ
4.足関節・足部
A.足関節外側靱帯損傷
B.アキレス腱付着部障害(踵骨後部滑液包炎含む)
C.足関節前方インピンジメント症候群
D.腓骨筋腱脱臼
E.足の疲労骨折(舟状骨,中足骨,内果,母趾基節骨)
F.有痛性外脛骨
G.足底腱膜炎
H.距骨骨軟骨損傷
I.足関節後方インピンジメント症候群
J.Jones骨折(第5中足骨近位骨幹部疲労骨折)
K.扁平足障害(後脛骨筋腱機能不全)
L.母趾MTP関節傷害(turf toe,母趾種子骨障害)
M.足根骨癒合症
索引
序文
この度、福林徹先生ご監修の下、『運動器スポーツ外傷・障害の保存療法』体幹・上肢・下肢の3巻が企画され、その中の「下肢」を編集させていただいた。走る、跳ぶといったスポーツの基本動作の中で、下肢には最も過酷な負荷が加わる。そのため、下肢には様々なスポーツ外傷や障害(損傷)が発生する。体幹や上肢のスポーツ損傷に比較し、下肢では手術を要するものが多いが、たとえ手術に至らない損傷であっても、アスリートの競技復帰を妨げたり、パフォーマンスを低下させたりする要因となる。
手術に至ることが最も多いスポーツ損傷は、膝の前十字靱帯(ACL)損傷であろう。鏡視下手術の進歩に伴いACL再建術を行えば、ほぼ元通りの関節安定性が獲得できるようになった。しかし、スポーツ復帰にあたっては、単に可動域や筋力訓練を行うだけでは不十分である。動作指導を含めた細心の再受傷予防トレーニングを行うことが不可欠であり、それには1年近いリハビリテーションを要する。とかくACL損傷=再建術と考えられがちではあるが、治療の中で最も重要な部分が、スポーツ復帰前のトレーニングである。ACL損傷治療=保存療法(再受傷予防トレーニング)ともいえるだろう。
本書も他巻と同様、保存療法の理解のために、まず必要な機能解剖とバイオメカニクスを解説した。さらに、運動療法に加え、臨床やスポーツの現場で用いられている各種保存療法の基礎知識をまとめていただいた。後半は、実際にスポーツの現場で活躍されている第一線のスポーツドクターと理学療法士(トレーナー)の先生方に、下肢の各部位の損傷とその保存療法について詳しく解説していただいた。非常に読み応えのある内容となっており、保存療法のバイブルになるものと信じている。
2020年の東京オリンピックのさなかに本書を発刊することは叶わなかったが、運動器スポーツ損傷を治療するドクターやトレーナーの方々にご一読いただき、今後のアスリートの診療にお役立ていただけたら幸いである。本書がアスリートの競技復帰、そしてパフォーマンス向上に寄与することを期待してやまない。
2020年10月
早稲田大学スポーツ科学学術院 熊井司
弘前大学整形外科 石橋恭之
COVID—19 によるパンデミックは,その変異株の猛威も加わりおさまりそうもない状態で,プロスポーツも緊急事態宣言によって無観客となることを強いられています.そのなかで,ゴルフの松山英樹選手が2021 年マスターズ・トーナメントで優勝したことは,日本中を明るくし,あらためてスポーツの偉大さを感じました.
そのスポーツには外傷がつきもので,スポーツをやめれば外傷が減少することを今回のパンデミックで改めて感じた先生も多いと思います.しかし,それでは前へすすめませんので,スポーツを行って生じた外傷・障害に対して適切に治療し,早期の競技復帰をめざすことは,選手はもちろん,医療従事者も望むところです.今回上梓された本書は,そのような方々に紹介したい1冊です.
本書は,「運動器スポーツ外傷・障害の保存療法」シリーズ全3 巻のうち,下肢についてまとめられたものです.スポーツで下肢を使わない競技はなく,スポーツをきわめようとすれば,当然下肢を障害する機会も多くなります.本書は,長年日本のスポーツ医学を牽引している福林徹先生の監修のもと,熊井司先生と石橋恭之先生が編集され,現在スポーツ医学の最前線で実際に治療にたずさわっている先生方によって執筆されています.特に本書は保存療法にフォーカスをあてており,スポーツドクターのみならず,理学療法士,トレーナーの先生方も加わって編集されたもので,下肢スポーツ障害,保存療法の教科書に相当すると感じました.
本書では,はじめに治療の方針や概念を理解するための下肢の機能解剖やバイオメカニクス,次いで,保存療法の基礎知識について解説されています.そのために,スポーツ障害で行われる保存療法に必要な基本的な知識の整理確認ができます.基礎知識には,従来からの運動療法や物理療法に加え,多血小板血漿(PRP),体外衝撃波,エコーガイド下注射療法についても掲載され,近年解明のすすんだバイオメカニクスの内容も充実しています.疾患別の分野においても,下肢のスポーツ障害を骨盤・股関節,膝関節,下腿,足関節・足部の章に分けて掲載されて,その領域は下肢全体を網羅しています.
股関節では,femoroacetabular impingement(FAI)に代表される大腿骨寛骨臼インピンジメントに加え,グロインペイン症候群,肉離れ,疲労骨折など日常診療で遭遇して,「まず保存療法でいくが,さてどうしようか,いつからスポーツ復帰を考えようか」と悩む疾患が掲載されており,非常に役立ちます.膝関節では,まずは保存療法が行われる靱帯炎,腱炎などの保存療法の方法やスポーツ復帰への指導なども詳細に記載されています.また,手術的治療となることの多い半月板や靱帯損傷に関しても,選手の希望などにより保存療法を選択せざるをえないときの治療方法など手元に置いておきたい内容です.
下腿や足関節領域では,疲労骨折,筋肉損傷,アキレス腱断裂やアキレス腱症および付着部障害をはじめ,ここでも日常診療で接する機会が多くかつ保存療法が積極的に行われる疾患や,観血的手術も行われるがまずは保存療法が第一選択となる靱帯損傷やインピンジメント症候群の運動療法や対外衝撃波療法から競技復帰へのプログラムについても記載されています.
全般に障害部位の写真やそれをわかりやすくしたシェーマ,治療計画の表や実際の治療時の様子などが多く掲載されており,診療や治療の現場でわかりやすく使いやすいと思います.また,本書は,保存療法に十分に精通した読者でも,体系的にその理解を深めることができると思います.また,本書を机のそばにおいておけば,現場からの問い合わせに応じたり,チームの医療関係者および選手本人と話し合いながら損傷部位の治療や競技復帰に向けての計画を立てる際に有効です.スポーツ障害に従事している医師,理学・作業療法士,トレーナーにぜひ読んでいただきたい書と思います.ぜひご一読ください.
臨床雑誌外科72巻8号(2021年7月号)より転載
評者●出家正隆(愛知医科大学整形外科教授)