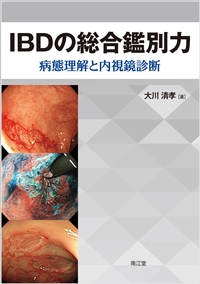IBD�̑����ӕʗ�
�a�ԗ����Ɠ������f�f
| �� | : ��쐴�F |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-22538-5 |
| ���s�N�� | : 2020�N12�� |
| ���^ | : B5 |
| �y�[�W�� | : 240 |
��
�艿9,020�~(�{��8,200�~ �{ ��)
- ���i����
- ��v�ڎ�
- ����
- ���]

��ᇐ��咰���A�N���[���a�݂̂Ȃ炸�A���������ܐ��Ȃǂ́g�L�`��IBD�h���܂߁A����ɂ킽��IBD�̕a�Ԑ�������摜�����A�f�Â̗v�_�܂ł�ԗ��B�a�Ԃ𗝉����������œ�����������ǂ݉����u�����ӕʗ́v�̃m�E�n�E�������B���N�ɂ킽��IBD�f�ÂɌg����Ă������҂��L���L�x�ȏǗ�A�~�ς��ꂽ�m���ƌo���ɗ��ł����ꂽ�����͂̂������B�t���J���[�Ŕ���ȓ������������ځB2020�N�ŃK�C�h���C���ɂ��Ή��B
�@�D���_
�@�͂��߂�
�@�@�|1�D�c����ᇂ̊ӕ�
�@�@�|2�D�֏��ᇂ̊ӕ�
�@�@�|3�D�~�E���~�`��ᇂ̊ӕ�
�@�@�|4�D�ʐΏ��̊ӕ�
�@�@�|5�D�я��ᇂ̊ӕ�
�@�@�|6�D�U���̊ӕ�
�A�D�e�_
�@A�D���`�̉��ǐ�������
�@�@�A�|1�D��ᇐ��咰��
�@�@�A�|2�D�N���[���a
�@B�D����������
�@�@�A�|3�D�J���s���o�N�^�[�����E�T�����l������
�@�@�A�|4�D���Ǐo�����咰�ے���
�@�@�A�|5�D�G���V�j�A����
�@�@�A�|6�D�����j
�@�@�A�|7�D�T�C�g���K���E�C���X����
�@�@�A�|8�D��ᇐ��咰���ɍ�������T�C�g���K���E�C���X����
�@�@�A�|9�D�A���[�o���咰��
�@C�D��ܐ�����
�@�@�A�|10�D�R�ۖ�N�����o�����咰��
�@�@�A�|11�DClostridioides difficile������
�@�@�A�|12�DNSAIDs�N��������
�@�@�A�|13�Dcollagenous colitis
�@�@�A�|14�D���������Ԗ��Ö��d����
�@D�D���������a��
�@�@�A�|15�D�������咰��
�@�@�A�|16�D�������咰���ȊO�̋������咰�a��
�@�@�A�|17�D������������
�@E�D�Ɖu���֗^���鎾��
�@�@�A�|18�D���ǃx�[�`�F�b�g�a�E�P�������
�@�@�A�|19�DIgA���lj�
�@�@�A�|20�DIgA���lj��ȊO�̌��lj�
�@�@�A�|21�D�D�_�����ݒ���
�@F�D���̑��̎���
�@�@�A�|22�D���Ԗ����b�D��
�@�@�A�|23�D�}���o�����������
�@�@�A�|24�D�h�����
�@�@�A�|25�D�����S���E�nj�Q
�@�@�A�|26�Dcap polyposis
�@�@�A�|27�D�A�~���C�h�[�V�X
�@�@�A�|28�D�e�����咰��
����
��
�@���ǐ��������iIBD�j�̓������f�f�Ɋւ���{��G���̓��W���́A����܂ł��������s����A�Տ��Ǐ�A�m��f�f�@�A�����������A���ÂȂǂ��R���p�N�g�ɂ܂Ƃ߂��Ă��邪�A���̂قƂ�ǂ����S���M�ł���A����䂦��ѐ��������Ă�����̂����������Ǝv����B���ɓ����������Ɋւ��Ă͏\���Ƃ͂������A���ɂ͑��̕������Q�l�ɂ�������������Ă���悤�Ȃ��̂܂ł݂���B�M�҂͂���܂Œ��N�ɂ킽��IBD�̓������f�f�Ɍg���A�����̏��Ђɕ��S���M�Ƃ��Ċւ��@������������Ă������A�������������܂߂āA�ǂ̂悤�Ɍ����悭�f�f���Ă������Ƃ������_�ŏ����ꂽ�����̂������Ђɂ߂��荇�����Ƃ́A�����Ȃ������B�����ŁA����܂Ŏ��g��ł���IBD�̓������f�f�̏W�听�ɂȂ�悤�Ȗ{�����g�ŕҎ[���邱�ƂɎv��������A�{������悵���B
�@IBD�̊ӕʐf�f�͓���Ƃ�����B�������̎���������A������m���Ă��Ȃ���A���������f�f�͕s�\�ł���B���ׂĂ̎����𗝉����邱�ƂŁA�悤�₭�I�m�Ȋӕʐf�f���ł���悤�ɂȂ�B���̂��߁AIBD�f�f�̃G�L�X�p�[�g�ɂȂ�ɂ́A�����̎������o���ł��A�����Ă����l��������ɂ��āA������x�̔N���̌��r��ςޕK�v������B���̂��Ƃ��Ⴂ��������ȈオIBD�̓������f�f���h������傫�Ȍ�����1�ɂȂ��Ă���B�{�������̉ۑ����������ꏕ�ƂȂ�ƍl���A�M���������B
�@���������������Ƃ����t�́A���Ȃǂ̎�ᇂ���Ƃ���҂Ɖ��ǂ���Ƃ���҂ɑ傫��������Ă���B��ᇂ̊m��f�f�͂��ׂĕa���g�D�f�f�ł���A�f�f�ɖ������Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B����A���ǂł���IBD�ɂ��ẮA�a���g�D�݂̂Őf�f���������͔������݂��Ȃ��B�������f�f�ɂ����Ă��A��ᇂł͊g���������NBI�̐i���ɂ��A���̐f�f�݂̂łȂ��a���f�f�ɂ������悤�ɂȂ��Ă���B����A���ǂɂ��Ă̓������̖����͂ǂ��ł��낤���B�������A�����������݂̂Őf�f�����������������A�f�f������Ǘ�Ɋւ��ẮA�^���̂��鎾���̏E���グ�������ł���B���̂��߂ɂ́A�{���̑��_�łƂ�グ�����قȌ`�Ԃɂ��ӕʂ��L���ȕ��@�ƍl������B���̒i�K�ŏE���グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ���A�f�f�͂��Ȃ����A��₪���܂�ɑ������Ă��f�f�͓���B���ۂɂ́A�����������Ɯ늳���ʂɂ��A������x�̎����ɂ����悻�̖ڈ������A�����Ŋ��Ҕw�i�i��b�����A�N��A���ʁA���^��܂Ȃǁj�ƗՏ��Ǐ�3�`5���x�Ɏ������i�荞�ލ�Ƃ��s���B����ɁA�����̊ӕʂ��s�����߁A�a�������iHE���F�A�Ɖu���F�j�A�|�{�����A�R�̌����A�R�������A��`�q�����A�㕔�⏬�������������AX�����e�����A�����⋹��CT�����Ȃǂ��s�����ƂŊӕʂ��Ă����B�Ƃ��낪�A���̒i�K�łǂ̌������s�����́A���ꂼ��̎����ɂ��傫���قȂ��Ă���B�܂��A�����ɂ��m��f�f�̕��@���قȂ��Ă���A�m��f�f�̕��@���m������Ă��Ȃ����������݂���B���̂��߁A���ꂼ��̎����ɂ��Ă̐[���m�����K�v�ł���A�{���̊e�_�ł́A�m��f�f�̕��@��f�f�̃|�C���g�ɂ��ďڂ����q�ׂ��B�������A����ł��ŏI�I�ɐf�f���m��ł��Ȃ����Ƃ����蓾��B���̏ꍇ�ɂ͐f�f�I���Ái�R���j��A�RCMV��Ȃǁj��A�o�ߊώ@���s�����ƂŐf�f����B���̂悤��IBD�̐f�f�͓���A�������f�f�\�͂ɉ����āA�����I�Ȑf�f�\�͂��K�v�ł���B���̂��߁A�{���̖��O���uIBD�̑����ӕʗ́v�Ƃ����B
�@�{���͑��_�Ɗe�_�̓\���ɂȂ��Ă���B���_�́A�n�Ӊp�L�搶�̊�{����^����݂����ނ��Q�l�ɂ��āA�i1�j�c����ᇁA�i2�j�֏��ᇁA�i3�j�~�E���~�`��ᇁA�i4�j�ʐΏ��A�i5�j�я��ᇁA�i6�j�U����悷�鎾���ɂ��ĕp�x�ʂɏq�ׂĂ���B������6�̏�����悷�鎾���͔�r�I���Ȃ��A�f�f�̏d�v�ȃq���g�ɂȂ邩��ł���B���_�Ƃ͂����A�����̎ʐ^���ڂ����A�g���X�ɂ��Ȃ��Ă���A���ꂼ��̌`�ԕʂɁA�f�f����������Ǘ�����Ă���B�����̓������������݂��ꍇ�ɂ́A���Ж{����p���Ċӕʐf�f���s���Ă��炢�����B
�@�e�_�͍��ڂ��ƂɁA�u�����̃|�C���g�ƍŋ߂̓����v�A�u�a�Ԑ����v�A�u�Տ����v�A�u�摜�f�f�v�A�u�f�f�̃R�c�v�A�u�m��f�f�v�A�u���Áv�̏����o�������ċL�ڂ��Ă���B�摜�f�f�Ɋւ��ẮA�܂��늳���ʂɂ��ďq�ׁA�����������������Ă���B�����ɂ���Ă�CT�������d�v�Ȃ��̂�����A�����Čf�ڂ��Ă���B�M�҂�̃O���[�v�́A����܂Ŏ�X��IBD�̕a�ԂɊ�Â����V���Ȏ��_����̓������f�f�ɂ��ĕ��Ă����B�V�����������������������Ă���A�����̏����̊ӕʐf�f�ɂ�����L�p���ɂ��ďq�ׂĂ����B����ɁA�{���ɂ����Ă͂��߂āu�h����ᇂ̉����������������v�A�u�D�_�����ݒ����̓����I�咰���������Ƃ��Ă̔��F�������߁v�ɂ��ďq�ׂĂ���B�e�_�ł͂���܂łɕM�҂��Ǝ��̎��_����̓������f�f���m������������ԗ����Ă���A���_���܂߂��IBD�Ɋւ���قڂ��ׂĂ̎��������ڂ��Ă���B�ǎ҂̊F�l�������ɃA�N�Z�X���₷���悤�ɃC���f�b�N�X���[��������悤�S�������B
�@�{���́A�������f�f�Ɋւ��Ă͓��ɏڂ����L�ڂ��Ă���A���������e�̒��S�ł��邪�A����݂̂Ȃ炸�A�����I�Ȑf�f�ɕK�v�Ȃ��ƂɊւ��Ă��]���Ƃ���Ȃ��L�ڂ��Ă���B�{����1������A����IBD�f�f�̖{�͂���Ȃ��Ƃ������e��ڎw���ď������BIBD�̐��ゾ���łȂ��A��������Ȉ�A�������Ȉ�A�J�ƈ�̐搶���ɂ����p���Ă���������K���ł���B
2020�N10��
��쐴�F
�@���ǐ��������i�L�`��IBD�C�ȉ�IBD�j�̂قƂ�ǂ͖��Ɋւ��Ȃ��ǐ������ł���C�܂����������i�i�ɑ����m��f�f�������Ȃ����Ƃ��������߁C�f�f�͂Ȃ�������ɂ��ꂪ���ł���D��ᇂ́g�f�f���Đ؏��������ŏI���h�Ƃ������ʂ����邽�߁C�a�ԁE�摜�͓����Ȃ����CIBD�͏����C�Ɋ��C�������Cፍ����ł��̕a�ԁE�摜�͌����������C����ɂ͏������⎡�Ẩ���C�������ω��̍����Ȃǂɂ���T�^����悵�C�����̑������݂��ďo�����邱�Ƃ����邽�߁C���̉摜�͂���߂ĕ��G�ł���D���̂��߁C�[����摜�f�f����߂Ă��܂��y�������Ǝv����D
�@IBD�̉摜�f�f�𐳊m�ɍs�����߂ɂ́C�܂����̒��Ŏ������ƂɓT�^���́u�m���̔��v�����C�����̔����쐬����K�v������D�����𐳊m�ɏE���グ�āi�d�v�j�C���͂��C���̒��ɍ쐬�����������Ƃ̒m���̔��̂ǂ�Ɉ�v���邩�C�߂�������͂��Ă䂭�X�e�b�v���d�v�ł���D����CIBD�̐f�f�͑��̎����Ɠ��l�C�摜�݂̂ł͌��܂�Ȃ��D��f�C�g�̏����C�����w�I�E�ۊw�I�ؖ��C�����C���ꌟ���ȂǁC�������摜�����Ƒg�ݍ��킹�邱�Ƃł͂��߂Đ������f�f�E���Â��\�ƂȂ�D���Ȃ킿�CIBD�ɂ͓������f�f�\�͂ɉ����đ����I�Ȑf�f�\�͂��K�v�Ȃ̂ł���D
�@����CIBD�f�f�ɂ�����{�M�̑��l�҂ł���C��쐴�F�搶�̂����M�ɂ��Җ]�̖{�����������ꂽ�D�{���͂�������̔���ȉ摜��p���āC��q�����摜�����̏E���グ���C���͂̎d���ɂ��Ă̂ق��CIBD�f�f�̗����C�������ǂ̂悤�ɑg�ݍ��킹�邩�Ȃǂ������ɖԗ����ꂽ�C���搶��IBD�������f�f�E���Â̏W�听�Ƃ�����D�^�C�g���́uIBD�̑����ӕʗ́v�̖��ɂӂ��킵������ł���D
�@�{����2������\������Ă���D���_�ł́CIBD��������I�i����I�j�`�Ԃ���C�n糉p�L�搶�̕��ނɏ]����6�`�Ԃɕ��ނ��C���ꂼ��̓���^��悷�鎾���ɂ��Ă̓T�^�I�ȓ���������������Ă���i�摜�������玾����f�f�j�D���ꂪ�C�܂��ɓ������������瓪�̒��ɍ쐬����鎾�����Ƃ́u�m���̔��v�ł���D���̕������J��Ԃ����ǁi�ǂ݂Ȃ��疰���Ă͂����܂���I�j���邱�ƂŐf�f�\�͈͂�C�Ɍ��シ��D�e�_�ł͊e�����̕a�Ԃ̏ڍׂȉ���Ɠ������������f�ڂ���Ă���C�����ɂ͏������C�Ɋ��̑��C�������̑��Cፍ����̑��C�����Ď��Âɂ��C�����ꂽ���̂��ׂĂ�����Ă���D�e�_�ł͑��_�̋t�̎v�l��H�E�ߒ��ł̃g���[�j���O�i��������摜�����𐄑��j���Ȃ����悤�ɍ\������Ă���D
�@IBD�͑���ɂ킽�邽�߁C���߂��玾���̉摜���ׂĂɒ@�����ނ��Ƃ͕s�\�ł���D�{�����茳�ɒu���C���ۂ̓�����������{���̏����Ɣ�r���C�^���������ɂ��ĕ�����D���̃t�B�[�h�o�b�N���d�v�ł���D���߂́C������ۊw�I�����C���ꌟ���ɗ����Đf�f�����ʂ��������C�{�����J��Ԃ����ǂ��C���̒��ɒ@�����ނ��ƂŁC���R��IBD�̓������f�f���x�����サ�C�摜�݂̂���ł������̎����̐f�f�C�������\���\�ƂȂ�D�����Ȃ��IBD�̐f�f�͖ʔ����D����ɗՏ�������摜����C�����W�{�œ�����\��������a����ɓ`����C�ۂ̎�ނ�\�����āC�|�{�����̐ݒ蓙���s����悤�ɂȂ�D�����āC���̊Ԃɂ�IBD�f�f�̃v���t�F�b�V���i���ƂȂ��Ă��鎩���ɋC�����D���₻�̑O�ɁC���͂��C�Â��ċ����ł��낤�D
�@���_�Ɗe�_���s�����藈���肵�Ȃ���{���̓��e�������ɓ��ɓ���邱�Ƃɂ��C�ǎ҂��킪���Łi�����E�Łj�g�b�v�N���X��IBD����ɂȂ�邱�Ɛ��������ł���D�������C���������Ƃ��Ȃ��C���Ȃ̈�t�C�������Ȃ̈�t���CIBD�f�f�̃A�g���X�C�o�C�u���Ƃ��Ė{�����茳�ɒu���Ă�����邱�Ƃ����������߂������D
�Տ��G������128��4���i2021�N10�����j���]��
�]�ҁ��s������a�@ �@���@�ē��T��

![������� ��]�� / NANKODO](/img/usr/common/logo.gif)