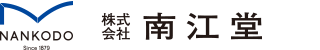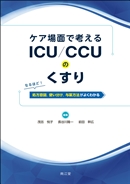健康・栄養科学シリーズ
食べ物と健康 食品の科学
こちらの商品は改訂版・新版がございます。
| 監修 | : 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 |
|---|---|
| 編集 | : 太田英明/北畠直文/白土英樹 |
| ISBN | : 978-4-524-26846-7 |
| 発行年月 | : 2015年3月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 302 |
在庫
定価3,080円(本体2,800円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文

食品の一次機能(栄養機能)、二次機能(嗜好・感覚機能)、三次機能(生体調整機能)と、分類、食品ごとの栄養成分・特性など、管理栄養士業務の基本となる知識をわかりやすく学べるよう解説。化学の知識を復習しながら効果的に理解できるよう構成。最新トピックのコラム、章末の練習問題も充実。管理栄養士国家試験出題基準「食べ物と健康(1、2、3)」に準拠。「食べ物と健康I 食品の科学と技術」の改訂新版。
第1章 人間と食品(食べ物)
A.食文化と食生活
1 食物の歴史的変遷
2 食物連鎖
3 わが国の農林水畜産業と食品科学
B.食生活と健康
1 健康寿命とQOL
2 食品の安全性
3 生活習慣としての食生活の質の向上
4 食育の必要性
C.食料と環境問題
1 食料自給率の低下
2 フード・マイレージ
3 地産地消
4 食品ロス、食品ロス率
第2章 食品の一次機能
A.食品の一次機能とは
1 食品の3つの機能
2 栄養機能(一次機能)
B.水
1 水の特性
2 食品と水
C.たんぱく質
1 たんぱく質を構成しているアミノ酸
2 ペプチド結合
3 たんぱく質の構造
4 たんぱく質の種類と分類
5 たんぱく質の性質
6 たんぱく質の定量分析
7 たんぱく質の変性と凝集
8 たんぱく質の栄養性
9 酵素
D.炭水化物(糖質、食物繊維)
1 糖質
2 食物繊維
E.脂質
1 脂質の定義と種類
2 油脂の物理化学的性質
3 油脂の理化学的試験法
4 油脂の性質と加工
5 油脂の劣化
6 脂質の栄養
F.ビタミン
1 ビタミンの定義と分類
2 脂溶性ビタミン
3 水溶性ビタミン
G.ミネラル
1 ナトリウム
2 カリウム
3 カルシウム
4 マグネシウム
5 リン
6 鉄
7 亜鉛
8 銅
9 セレン
0 マンガン
11 クロム
12 ヨウ素
13 モリブデン
14 その他の元素
第3章 食品の二次機能
A.食品の二次機能とは
B.色素成分
1 ポルフィリン系色素
2 カロテノイド系色素
3 フラボノイド系色素
4 その他の色素
C.呈味成分
1 甘味成分
2 酸味成分
3 塩(鹹)味成分
4 苦味成分
5 うま味成分
6 辛味成分
7 渋味成分
8 えぐ味成分
D.香気・におい成分
1 植物性香気成分
2 動物性香気成分
3 その他
E.テクスチャー
第4章 食品の三次機能
A.食品の三次機能とは
B.消化管内で機能する成分
1 難消化性成分の機能
2 脂質の消化・吸収
C.抗酸化作用
1 活性酸素とは
2 抗酸化作用
3 抗酸化酵素
4 抗酸化ビタミン類
5 カロテノイド類
6 ポリフェノール類
7 その他抗酸化物
D.免疫系で作用する成分
1 脂質とアレルギー反応
2 多糖類の免疫調整機能
E.神経系で作用する成分
1 食品成分による神経障害の緩和
2 食品成分のストレス緩和効果
F.循環器系に作用する成分
1 高血圧予防
2 動脈硬化予防
3 血栓予防
G.代謝に作用する成分
1 代謝とは
2 代謝に着目した食品機能研究
3 ニュートリゲノミクス
H.骨・歯系に作用する成分
1 カルシウムの吸収機構
2 カルシウム吸収に関与する成分
3 骨の形成促進作用
4 むし歯予防効果作用
第5章 食品の分類と食品成分表
A.食品の分類
1 生産様式による分類
2 原料による分類
3 主要栄養素による分類
4 食習慣による分類
5 その他の分類
B.食品成分表の理解
1 はじめに
2 日本食品標準成分表2010の詳細
3 日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010の概要
4 五訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編の概要
第6章 植物性食品の分類と成分
A.穀類
1 穀類の特徴
2 米
3 小麦
4 大麦
5 とうもろこし
6 そば
7 その他の穀類
B.いも類
1 生産と消費
2 栄養的・生理機能的特徴
3 種類
C.豆類
1 豆類の特徴
2 大豆
3 小豆
4 いんげん豆
5 えんどう
6 ささげ
7 そら豆
8 緑豆
9 その他の豆類
D.種実類
1 分類・成分特徴
2 生産・消費動向
3 主な種実類の特徴
E.野菜類
1 分類・成分特徴
2 生産・消費動向
3 主な野菜類の特徴
F.果実類
1 分類・成分特徴
2 生産・消費動向
3 主な果実類の特徴
G.きのこ類
1 生産と消費
2 栄養的・生理機能的特徴
3 種類
H.藻類
1 生産と消費
2 栄養的・生理機能的特徴
3 種類
第7章 動物性食品の分類と成分
A.肉類
1 食肉の構造
2 食肉の化学成分
3 肉類の種類と特徴
4 食肉の熟成と成分の変化
5 食肉中の機能性成分
6 食肉の利用
B.魚介類
1 分類
2 魚肉の構造
3 成分
4 魚の死後の変化と鮮度保持
5 魚介類の種類
C.乳類
1 乳牛の品種
2 牛乳の成分
3 牛乳・乳製品の種類と利用
4 牛乳・乳製品の三次機能
D.卵類
1 卵の種類と構造
2 卵の一般成分
3 卵の鮮度評価
4 卵の加工特性
5 卵の加工
6 卵の三次機能
第8章 油脂、調味料、香辛料、嗜好飲料の分類と成分
A.油脂類
1 食用油脂の分類
2 主な植物性油脂
3 主な動物性油脂
4 主な加工油脂
B.甘味料
1 オリゴ糖(少糖類)
2 糖アルコール
3 アミノ酸、たんぱく質
4 その他の天然甘味料(配糖体)
5 人工甘味料
C.調味料
1 食塩
2 酸味料
3 うま味調味料
4 みそ
5 しょうゆ
D.香辛料
1 味をつける辛味性の香辛料
2 香りをつける芳香性の香辛料
3 臭みを消す矯臭性の香辛料
4 色をつける着色性の香辛料
E.嗜好飲料
1 茶
2 コーヒー、ココア
3 嗜好飲料に含まれる機能性成分
第9章 微生物利用食品の分類と成分
A.アルコール飲料
1 醸造酒
2 蒸留酒
3 混成酒
B.発酵調味料
1 みそ
2 しょうゆ
3 食酢
4 みりん
C.その他の微生物利用食品
1 漬物
2 納豆
3 かつお節
参考図書
練習問題解答
索引
はじめに
人にとって「食」は、生きるために必須の“もの”であり、“こと”である。“もの”としての食、すなわち食品・食べ物・食物は、言うまでもなく生命体そのものを維持するための“もの”であり、一昔前までは人類は生きている時間の大半を、食べ物を探し、得ることに費やしていた。現在では、食料の生産に携わる人と、専らそれを購入して食べる人に分かれ、自分が食べている“もの”が、どこでどのようにして作られ、運ばれてきたかもなかなか分からない時代になっている。わが国においては、食の生産に関わる、いわゆる農業人口は必ずしも多くはないが、生産だけではなく、食料・食品の輸送や貯蔵、販売や宣伝まで広げると、極めて多くの人々が今でも「食」を生活の糧にして生きていると言える。
専ら食料生産を行う産業は一次産業に位置し、畑でできた農産物が食卓に到達するまでには、加工や輸送、貯蔵などが必要であり、それに関わる産業領域は二次産業と言えるであろう。そして、食に関わる多くの業種を金融や情報の面で支える産業は三次産業の領域である。現在はこれらの多くの産業が関わって、われわれの食が維持されている。
食品の機能についても、一次、二次、三次という分け方が一般的になってきた。食品のもつ最初の機能は、生命体の構造維持やエネルギーの供給にあり、もっとも根源的で、本質的である。いわゆる栄養機能であり、これは現在、食品の一次機能と呼ばれる。しかし、食品は単に栄養素を満たしていればそれで十分というわけではなく、食欲をそそり、食べる楽しみや満足感を与える機能が備わっていなければ本当の食品とは言い難い。それが食品の二次機能である。さらに、食べたものが人の生命活動を整え、調節する形で寄与するのが三次機能である。食品素材のほとんどが生命体由来のものであり、これを食べる「ヒト」も同じ生命体であるがゆえに、食品学と栄養学は表裏一体の関係にある。つまり、食品の機能を、生命体としての「ヒト」の側から捉えて解析するのが栄養学であり、一方、同じ生命体ではあるが、「食品」の側から解析するのが食品学であるといえる。特に、生化学や物理化学などの手法を用いて食品そのものの実体を解き明かすのが食品科学であり、食品学は、食品科学に加えて、上記の一次産業から三次産業にわたる食品の加工・流通・貯蔵・調理の領域も視野に入れ、様々な方法論を駆使して、食品本体の全体像を明らかにしようとする学問分野である。
本書は食品科学に軸足を置いて、食品の成分やその化学的変化、食品の嗜好性を支配する要素である色、におい、味、口腔内触感(食感)などについて述べており、食品の一般的特性を取り上げている。個々の食品の特性や特徴については、姉妹書の『食べ物と健康食品の加工』をご覧いただきたい。本書は、特に管理栄養士をめざして勉学に励まれる方を対象にした教科書として編纂されたものであり、管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン)の出題科目「食べ物と健康」の内容に沿って記述されている。栄養学や生化学などの他の分野とも関連付けながら本書を紐解き、学んでいただければ、理解がいっそう深まると思われる。また、管理栄養士に求められる食品についての知識は、食に携わる多くの人々にとっても基礎的な知識である。したがって、管理栄養士を目指す方々はもとより、食品関連領域に携わる様々な方々にも、本書を手に取っていただくことを期待する。
2015年2月
執筆者を代表して
北畠直文