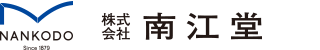健康・栄養科学シリーズ
応用栄養学改訂第5版
こちらの商品は改訂版・新版がございます。
| 監修 | : 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 |
|---|---|
| 編集 | : 渡邊令子/伊藤節子/瀧本秀美 |
| ISBN | : 978-4-524-26162-8 |
| 発行年月 | : 2015年3月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 386 |
在庫
定価3,520円(本体3,200円 + 税)
正誤表
-
2015年04月20日
第1刷
- 商品説明
- 主要目次
- 序文

「日本人の食事摂取基準(2015年版)」に対応した改訂版。各ライフステージにおける生理的機能や栄養状態の特徴、スポーツ、特殊環境それぞれに応じた栄養ケア・マネジメント、ならびにその基礎となる食事摂取基準の考え方・科学的根拠を、総合的にわかりやすく解説した。「管理栄養士国家試験出題基準」に準拠し、豊富な図表やコラム、脇組の基本用語解説などの工夫により、学習しやすい構成になっている。
第1章 栄養管理(栄養マネジメント)
A.栄養管理の概要
B.栄養スクリーニング
C.栄養アセスメント
D.栄養アセスメントの方法
1 身体計測
2 生理・生化学的検査(臨床検査)
3 問診・観察
4 食事調査
E.栄養ケア・栄養プログラムの計画
F.栄養ケア・栄養プログラムの目標設定
G.栄養ケア・栄養プログラムの実施
1 栄養補給
2 栄養指導
3 他領域との連携
H.行動科学理論の応用
1 KAPモデル
2 ヘルスビリーフモデル(保健信念モデル)
3 社会的学習理論
4 プリシ−ド/プロシードモデル
5 トランスセオレティカルモデル(行動変容段階モデル)
6 エンパワメントアプローチ
I.対象者とのカウンセリング
1 言語的コミュニケ−ション
2 非言語的コミュニケーション
J.評価の種類およびデザイン
1 評価の種類
2 評価のデザイン
3 評価結果のフィードバック
第2章 食事摂取基準の基礎的理解
A.食事摂取基準の意義
1 意義
2 概要
3 歴史
B.食事摂取基準の基礎的理解
1 エネルギー
2 栄養素の摂取不足からの回避を目的とした指標の特徴
3 栄養素の過剰摂取からの回避を目的とした指標の特徴
4 生活習慣病の一次予防を目的とした指標の特徴
5 策定における基本的留意事項
C.食事摂取基準活用の基礎理論
1 食事調査などによるアセスメントの留意事項
2 活用における基本的留意事項
3 個人の食事改善を目的とした評価・計画と実施
D.エネルギー・栄養素別必要量
1 エネルギー
2 たんぱく質
3 脂質
4 炭水化物
5 食物繊維
6 エネルギー産生栄養素バランス
7 ビタミン
8 ミネラル
第3章 成長・発達,加齢/ライフサイクル
A.成長・発達,加齢(老化)
1 概念
2 成長・発達に伴う身体的・精神的変化と栄養
3 加齢(老化)に伴う身体的・精神的変化と栄養
B.ライフサイクル,ライフコースの概念
1 近代諸学派
2 健康日本21とライフサイクル・ライフコース
第4章 妊娠期,授乳期
妊娠期
A.妊娠
1 性成熟期女性の月経周期
2 妊娠の成立と維持
3 母体の生理的変化
4 胎児の成長
5 妊娠中の喫煙・飲酒
B.産褥
C.栄養アセスメントと栄養ケア
1 問診・観察
2 臨床検査
3 身体計測
4 生活習慣の把握
5 食事摂取基準
6 妊産婦のための食生活指針
7 妊婦のやせと肥満
8 鉄摂取と貧血
D.栄養と病態・疾患
1 食欲不振と妊娠悪阻
2 妊娠期にみられる糖尿病
3 妊娠高血圧症候群
4 葉酸摂取と神経管閉鎖障害
E.栄養ケアのあり方
1 妊娠期の栄養ケアについて
授乳期
A.授乳女性の生理的特徴
1 体重と体組成の変化
2 エネルギー代謝の変化
3 授乳の生理的機序
4 初乳と成乳
5 母乳成分と母乳量の変化
B.栄養アセスメント
1 健康診査と授乳支援体制
2 臨床検査(ヘモグロビン,ヘマトクリット)
3 身体計測
4 新生児・乳児の哺乳状況
5 臨床診査
C.授乳期の病態
1 授乳婦の体重
2 低栄養状態とリスク要因
3 乳腺異常と乳腺炎
4 摂食障害
D.栄養ケアのあり方
1 授乳婦の栄養ケアのあり方
2 出産後の健康・栄養管理
3 出産後のQOLに向けた維持管理
4 新生児・乳児の正常発育発達
5 人工栄養法と離乳食
第5章 新生児期,乳児期
A.新生児期,乳児期の生理的特徴
1 一般的な新生児,乳児の発達生理
2 新生児期,乳児期における消化・吸収能の発達
3 消化管機能の発達
B.栄養アセスメント
1 出生時の身体計測値と子宮内発育状況
2 出生時の合併症
3 栄養素摂取状況
4 新生児期,乳児期の発育
5 精神運動および摂食機能の発達
6 母子関係,被虐待児症候群
C.栄養と病態・疾患
1 母乳性黄疸
2 乳児ビタミンK欠乏性出血症
3 鉄欠乏性貧血
4 乳児下痢症
5 食物アレルギー
6 胃食道逆流症
7 極低出生体重児の栄養学的諸問題
8 便秘
9 乳糖不耐症
10 発達遅滞
D.栄養補給法
1 母乳
2 人工乳
3 授乳方法
4 離乳食
E.乳児期の食事摂取基準
F.栄養ケアのあり方
1 栄養ケアの重要性の認識
2 育児の視点・個別化した指導・
3 個人差の配慮
第6章 幼児期
A.幼児の成長
1 臓器別発育曲線と身体のプロポーション
2 身長と体重
3 頭囲と胸囲,胸郭
4 大泉門
5 骨年齢
B.幼児の発達
1 運動機能の発達
2 精神機能の発達
3 生活習慣行動の発達
4 社会性の発達
5 生理機能の発達
C.栄養状態の変化
1 幼児における食事摂取基準
2 幼児期の栄養の特徴と食生活
D.栄養アセスメント
1 身体計測
2 頭囲と胸囲
3 問診・観察
4 臨床検査
E.栄養と病態・疾患・生活習慣
1 小児における代謝・栄養の特性
F.栄養ケアのあり方
1 幼児の成長と発育からみた栄養ケアのあり方
2 食事摂取基準からみた栄養ケアのあり方
3 食物や食事を味わい,受容し,楽しむ能力の形成
4 適切な食習慣の形成
5 保育所給食
第7章 学童期,思春期
A.成長・発達
1 生理的機能の発達
2 運動機能の発達
3 精神機能・社会性の発達
4 歯の発育と骨年齢
B.学童・思春期の成長・発達
1 身体発達の特徴
2 身体の成長,発育
3 第二次性徴
C.栄養状態の変化
1 身長,体重,体脂肪率
2 食習慣の変化
D.栄養アセスメント
1 身体計測・体格指数
2 臨床検査
E.栄養と病態・疾患
1 肥満
2 低身長
3 生活習慣病
4 やせと摂食障害
5 貧血
6 起立性調節障害
7 無月経
8 喫煙,飲酒,性の問題
F.栄養ケアのあり方
1 食事摂取基準と栄養の適正化
2 不適切な生活習慣の是正
第8章 成人期
A.成人期の特性
1 若年成人期(思春期以降29歳まで)
2 壮年期(30〜49歳)
3 実年期(50〜64歳)
B.成人期の生活習慣
1 運動
2 休養
3 飲酒,喫煙
C.成人期の食生活
1 欠食
2 外食
D.成人期の食事摂取基準
1 エネルギー
2 たんぱく質
3 脂質
4 炭水化物
5 ミネラル
6 ビタミン
E.栄養と疾患・病態
1 肥満とメタボリックシンドローム
2 高血圧
3 脂質異常症(高脂血症)
4 糖尿病
5 慢性腎臓病(CKD)
6 高尿酸血症・痛風
7 虚血性心疾患
8 脳血管障害(脳卒中)
9 悪性新生物(がん)
10 甲状腺機能障害
11 う蝕および歯周病
12 うつ病
F.栄養アセスメント
1 問診,身体所見
2 身体計測
3 臨床検査
4 食事調査
5 食行動・食態度・食知識・食スキル・食環境の調査
G.栄養ケアのあり方
1 生活習慣の改善には
2 食生活指針の理解に向けての推進
3 運動習慣を身につける
4 自己管理能力の習得
5 健康日本21(第2次)の目標値の最終評価
第9章 高齢期
A.高齢期の特徴
1 加齢と老化
2 高齢者の年齢区分
3 高齢者の現状
B.高齢者の生理的特徴
1 感覚機能(視覚,聴覚,嗅覚,味覚)
2 脳・神経系
3 咀嚼・嚥下機能
4 消化器系
5 食欲不振,食事摂取量の低下
6 日常生活動作(ADL)の低下
7 エネルギー・たんぱく質代謝の変化
8 免疫系
9 筋・骨格系
10 循環器系
11 呼吸器系
12 腎臓
C.高齢者の精神的変化
1 不安と喪失
D.高齢期の栄養アセスメントと栄養ケア
1 身体計測
2 生化学的検査
3 問診・観察
4 食事調査
5 食事摂取基準
E.高齢者の疾患と栄養ケア
1 肥満とるいそう
2 運動器疾患
3 誤嚥性肺炎
4 褥瘡と失禁
5 脱水と水分補給
6 消化器系疾患
7 眼科疾患
8 認知症
F.身体的特徴に配慮した栄養ケア
1 味覚機能の低下に対応した栄養ケア
2 消化器機能の低下に対応した栄養ケア
3 身体活動に対応した栄養ケア・
G.介護予防・合併症予防のための栄養ケア
1 QOL向上の条件
2 食事の役割
第10章 運動・スポーツと栄養
A.運動時の生理的特徴とエネルギー代謝
1 骨格筋とエネルギー代謝
2 身体活動時の呼吸・循環応答
3 運動・スポーツ活動とエネルギー供給
4 運動・スポーツと体力
B.運動と栄養ケア
1 運動の健康に対する影響
2 健康づくりのための身体活動基準2013
3 運動時の食事摂取基準
4 炭水化物とたんぱく質の摂取
5 水分・電解質補給
6 スポーツ貧血
7 食事内容と摂取のタイミング(筋グリコーゲンの再補充)
8 ウエイトコントロール(減量)と運動・栄養
9 栄養補助食品の利用
第11章 環境と栄養
A.環境変化に対する生体の応答とホメオスタシス
1 生体のホメオスタシス調節のしくみ
2 体温のホメオスタシス
3 体液のホメオスタシス
4 血糖のホメオスタシス
5 生体リズムとホメオスタシス
B.ストレスと応答と栄養
1 生体のストレス応答
2 ストレスと疾患
3 ストレスと栄養
C.特殊環境と栄養
1 高温・低温環境と栄養
2 高圧・低圧環境と栄養
3 無重力環境(宇宙空間)と栄養
4 災害時の栄養
参考資料
参考図書
練習問題解答
索引
改訂第5版の序
「応用栄養学」という科目では、栄養管理の基本的考え方に始まり、誕生から死に至るまでの生涯の各ライフステージにおける生理的特徴を理解するとともに、個々の対象者の生活環境、身体状況や栄養状態に応じた栄養管理のあり方を習得しなければならない。そのためには、食事摂取基準の意義、策定の考え方やその科学的根拠について理解を深め、これを各ライフステージの栄養管理に活用できる力を養うことが求められる。2015(平成27)年4月から5年間活用される「日本人の食事摂取基準(2015年版)」では、新たに生活習慣病の重症化予防という視点が加えられ、「応用栄養学」の学習範囲はますます広範囲になった。この背景には、わが国の高齢化率が2014(平成26)年に25.9%に達し、4人に1人が65歳以上、8人に1人が75歳以上となり、健康寿命の延伸が国民1人ひとりにとってだけでなく、わが国にとっても最重要課題となっていることがあげられる。とくに高齢者栄養においては、フレイルティおよびサルコペニアと栄養の関連が大きくとりあげられた。それゆえ、栄養管理業務に携わるにあたって、これまで以上に対象者特性を把握した栄養アセスメントが重要になり、食事摂取基準を理解したうえで、科学的知識・基盤をもって適切に対処することが期待されている。
そこで、今版では以下の点を中心に改訂を行った。
第一に、「日本人の食事摂取基準(2015年版)」の策定における基本理念をふまえて、新たな内容を加えるなど、全面的な見直しを図った。
第二に、第4版から約3年が経過したので、できる限り最新の知見や統計資料を盛り込んだ。
第三に、第4版を活用していただいた管理栄養士・栄養士養成課程の諸先生方から寄せられたご意見・要望を熟慮したうえで全体を見直し、「応用栄養学」の標準的教科書、国家試験受験対策書などとして、より充実した書となることを目指した。
本改訂にあたり、初版から多大なご尽力をいただいた戸谷誠之先生(現編集顧問)をはじめ、一部編集者ならびに執筆者に交代をいただくことになった。編集方針をご理解のうえ、ご対応いただいた執筆者の先生方と、さまざまな調整に対応くださった南江堂出版部に深謝申し上げる。
基礎栄養学から実践栄養学への過程における「応用栄養学」の重要性を認識し、その基礎的理解を助け、最新の知識・技術を習得するために、本書を活用していただきたい。今後も、本書をより一層充実させていくために、忌憚のないご意見やご指摘をいただけたら幸いである。
2015年2月
編集者を代表して
渡邊令子