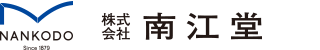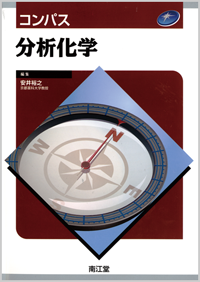コンパスシリーズ
コンパス分析化学
こちらの商品は改訂版・新版がございます。
| 編集 | : 安井裕之 |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-40303-5 |
| 発行年月 | : 2013年8月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 336 |
在庫
定価4,840円(本体4,400円 + 税)
サポート情報
-
2015年03月12日
改訂薬学教育モデル・コアカリキュラム(平成25年度改訂版)対応表
- 商品説明
- 主要目次
- 序文

わかりやすくミニマムエッセンスがコンセプトの、分析化学・機器分析学の教科書。豊富な図とポイントを押さえた記述で、薬剤師国家試験の中級レベルの問題を確実に解けるようになることを目指す。章末問題(Exercise)には自主学習を助ける丁寧な解説付き。薬学教育モデル・コアカリキュラムの分析化学・機器分析学分野に対応。第十六改正日本薬局方対応。
1章 序論
A 薬学における分析化学
B 物理量と単位
C 定量分析と定性分析
D 分析結果(実験データ)の取り扱い方と統計手法の適用
E 医薬品分析法のバリデーション
F 日本薬局方における標準分析法
2章 酸と塩基
A 酸と塩基の定義
B 酸と塩基の強さ
C 強酸と弱酸
D 弱酸の化学種とpH分布
E 強塩基と弱塩基
F 緩衝液と緩衝作用
G 多塩基酸の多段階解離
H 中和滴定
I 非水溶媒中における酸・塩基反応(非水滴定)
3章 錯体化学、キレート滴定
A 錯体生成反応
B 錯体の安定度定数
C キレート滴定
4章 酸化と還元、酸化還元滴定
A 酸化還元反応
B 酸化還元電位
C 酸化還元平衡
D 酸化還元滴定
5章 沈殿の生成と溶解、沈殿滴定
A 沈殿平衡と溶解度積
B 沈殿滴定
6章 分配平衡
A 溶媒抽出
B イオン交換
7章 有機物の確認試験
A 官能基の定性反応
B 構造特異的反応
8章 無機イオンの定性分析
A 無機イオンの分析法
B 無機イオンの定性分析
C 純度試験
9章 その他の分析法
A 電気的終点検出法
B 導電率測定法
10章 分離分析
A クロマトグラフィーと関連用語
B クロマトグラフィーの種類
C クロマトグラフィーの実際
D 電気泳動
11章 電磁波分析法
A 紫外可視吸光度測定法
B 蛍光光度法
C 原子スペクトル/ICP分析法
D 赤外吸収・ラマンスペクトル測定法
E X線分析法
F 旋光度測定法、円偏光二色性測定法
G 磁気共鳴法(NMR/ESR)
12章 質量分析法
A 装置
B マススペクトルの解析
C ほかの分析法との結合(ハイフネーテッド)
13章 分子間相互作用解析法
A 分子間の相互作用を解析することにより得られる情報
B 検出方法の違いによる相互作用解析法の分類
C 相互作用解析実験の手順
D 実験系環境の違いによる相互作用解析法の分類
14章 臨床分析
A 概論
B 試料の前処理
C 精度管理と標準物質
D 酵素を用いる分析法
E 免疫反応を用いる分析法
F ドライケミストリー
G センサー
H 薬毒物分析
I 画像診断法
索引
分析化学は大きく分けると化学分析、機器分析、臨床分析の主要な3つの分野から成り、医薬品やそれに関連する化学物質、および生体物質の定性分析と定量分析に関する化学の基礎理論や方法論を扱う学問である。薬学は創薬化学、生命科学、臨床科学を主体とした総合科学であるため、その基礎としての薬学教育および薬学研究を行う上で、分析化学は重要な位置を占めている。
6年制薬学教育の標準カリキュラムは体系化され、日本薬学会の「薬学教育モデル・コアカリキュラム」(以下、コアカリキュラムと略す)としてまとめられ、2006(平成18)年4月から全国の薬学部、薬科大学でコアカリキュラムを踏まえた教育が実施されている。コアカリキュラムでは講義単位ごとに、一般目標(GIO:学習者が学習により得る成果)とその到達目標(SBO:GIOに到達するための具体的な学習内容)により構成されている。コアカリキュラムに基づいた多くの新しい教科書や参考書がこれまでに出版されているが、本書は各専門分野の気鋭の執筆陣により、SBOのうち「C2化学物質の分析」、「C3生体分子の姿・かたちをとらえる」の「(1)生体分子を解析する手法」、「C4化学物質の性質と反応」の「(4)化学物質の構造決定」に関するすべての内容を網羅している。また、コアカリキュラムに伴い4年次最終のOSCEとCBTから成る共用試験も、2009(平成21)年から実施されている。本書は分析化学の分野に関して、このCBT 合格を第一の目標として、さらには薬剤師国家試験にも対応可能な意欲的な図書として企画されている。
薬学という非常に幅広い学問分野における基礎学問としての分析化学の重要性から、本書では分析化学で用いられる学術用語を可能な限り丁寧に説明することに努めている。また、図表を多用して、記述部分は平易でコンパクトにすることを前提として構成された。さらに、各章での主要項目は、学習のまとめに役立つように「ポイント」に要約し、内容の理解度は「Exercise」で確かめるよう工夫がなされている。また、「コラム」では、身近なところから分析化学の一口知識を紹介し、関連事項は「ここにつながる」によって学習の幅を広げ、知識を関連付けたい学生諸君のための指針を示している。このように、各章の内容を理解しやすいよう新しい試みが豊富になされている。本書が読者にとって、短時間で効率的な学習によりCBTや国家試験に活用されるだけでなく、化学の原理、理論、方法論をわかりやすく指し示す「コンパス」となることを期待してやまない。
2013年6月
安井裕之