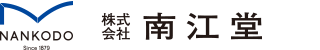新しい食品加工学
食品の保存・加工・流通と栄養
こちらの商品は改訂版・新版がございます。
| 編集 | : 小川正/的場輝佳 |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-26257-1 |
| 発行年月 | : 2011年1月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 222 |
在庫
定価2,640円(本体2,400円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文

好評の『栄養・健康科学シリーズ 食品加工学』をより一層充実した内容に再編集した改訂新版。食品加工に関する全般的な知識をコンパクトにまとめたテキスト。豊富な図表とともに、食品加工に対する基本的な考え方、さまざまな食品加工法の実際例や特徴、保存食品などについて解説。
第1章 序論−食品加工の意義
Column 内食(うちしょく)、中食(なかしょく)、外食
第2章 食品保存(貯蔵)の原理
A 食品の劣化の原因
1 物理的劣化
2 化学的劣化
3 生化学的劣化
4 生物的劣化
B 温度の操作による保存
1 目的
2 冷蔵(冷却貯蔵)
3 冷凍(冷凍貯蔵)
4 新温度帯保存
C 水分の制御による保存
1 目的
2 食品の水分含量と水分活性
3 水分活性と微生物
4 乾燥・乾燥食品
D 浸透圧を利用した保存
1 目的
2 塩蔵(塩漬け)・塩蔵品
3 糖蔵(砂糖漬け)・糖蔵品
E 水素イオン濃度(pH)の調節による保存
1 目的
2 酢漬け食品
F 殺菌による保存
1 目的
2 加熱殺菌法
3 加熱殺菌以外の滅菌・殺菌法
4 缶詰、びん詰食品
5 レトルトパウチ食品
6 無菌包装食品
G くん煙の利用による保存
1 目的
2 くん材
3 くん煙法の種類
4 くん製品
H 放射線の利用による保存
1 目的
2 放射線処理の特徴
3 照射食品の法的許可の現状
I 環境ガスの調節による保存
1 目的
2 CA貯蔵
3 簡易CA貯蔵
4 ガス貯蔵
5 脱酸素剤や鮮度保持剤の使用
J 食品添加物による保存
1 目的
2 保存料
3 防カビ剤(防ばい剤)
4 酸化防止剤(抗酸化剤)
練習問題
第3章 食品加工の原理
A 物理的操作
1 乾燥
2 抽出
3 ろ過・濃縮
4 エクストルーダー加工(エクストルージョンクッキング)
5 電磁波加熱
6 誘導加熱
7 凍結加工
8 高圧加工
9 加熱
B 化学的操作
1 化学反応
2 酵素反応
C 生物的操作
1 微生物による加工
2 バイオテクノロジー
Column 遺伝子組換え(GM)食品
練習問題
第4章 食品の加工
1.農産物加工
A 穀類
1 こめ
Column 新形質米
2 こむぎ
3 とうもろこし
4 雑穀
B 豆類
1 だいずの加工
Column 豆腐よう
C いも類
D 野菜類、きのこ類
1 漬物
2 乾燥野菜、乾燥きのこ
3 その他の加工品
E 果実類
1 ジャム類
2 果実飲料
3 果実缶詰、びん詰
4 乾燥果実、糖果
練習問題
2.畜産物加工
A 畜肉類
1 食肉の生産とその調製
2 筋肉から食肉への変換
3 食肉の加工技術
4 食肉製品の種類
Column 食肉加工品に含まれる機能性成分
B 卵類
1 加工用原料としての鶏卵
2 鶏卵の加工品の種類と製造法
Column 鶏卵成分の高付加価値利用
C 乳類
練習問題
3.水産物加工
A 水産物加工の特徴
1 原料の多様性
2 加工が必要な理由
3 魚介類筋肉の成分の特徴
4 加工の原理
B 魚体の死後変化と鮮度判定法
1 死後硬直
2 筋肉の軟化現象
3 熟成
4 腐敗
5 鮮度判定の指標
6 酵素センサー
C 魚介類の加工
1 冷凍品
2 乾燥品
3 塩蔵品
4 くん製品
5 練り製品
6 缶詰
7 調味加工品
Column 熟れずし
D 海藻類
練習問題
4.油脂
A 食用油脂の分類
B 植物・動物油脂
1 採油
2 原油の精製
Column グリシドール脂肪酸エステル
3 植物油中の脂溶性成分
4 油かすおよび除去物質の利用
C 油脂の改変
1 硬化油
Column トランス脂肪酸
2 エステル交換
3 分別
4 低カロリー油脂と構造脂質
5 ジアシルグリセロール油脂
Column いわゆる保健効果があるといわれている機能性脂質について
D 油脂製品
1 精製油とサラダ油
2 マーガリン、ファットスプレッド
3 ショートニング
4 ドレッシング
5 フライ用油脂
6 粉末油脂
7 バター
8 乳化油脂(合成クリーム)
練習問題
5.多糖類
1 デンプン
2 増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料
3 シクロデキストリン
Column 魔法のデンプン−シクロデキストリン
4 食物繊維素材
Column ポリデキストロース
練習問題
6.調味料およびし好食品
A 調味料
1 みそ
2 しょうゆ
3 みりん
4 食酢
5 ソース
B 甘味料
1 糖質系天然甘味料
2 非糖質系天然甘味料
3 合成甘味料
C うま味調味料と食塩
1 うま味調味料
2 天然調味料
3 風味調味料
4 食塩
D 香辛料
1 天然香辛料
2 香辛料抽出物
3 香辛料抽出物製剤
E し好飲料類
1 茶
2 コーヒー
3 ココア
4 清涼飲料
5 ミネラルウォーター
6 機能性飲料
7 アルコール飲料(酒類)
Column さまざまなビール様酒類
Column アルコール濃度と酔い
F 菓子類
1 和菓子
2 洋菓子
Column ビスケット、クッキー、サブレー
G 新規加工食品(特別用途食品、保健機能食品など)
1 特別用途食品
2 保健機能食品
練習問題
第5章 包装
A 食品包装の役割
B 食品包装材料
1 紙
2 金属
3 ガラス
4 プラスチック
5 複合材料
6 その他の包装材料
C 包装容器と包装方法
1 紙容器
2 金属缶
3 ガラスびん
4 プラスチック容器
練習問題
第6章 加工食品の規格・表示と安全性
A 品質の規格化と表示の制度化の意義
B 主要な規格・表示制度
1 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
2 食品衛生法および乳等省令
3 健康増進法
4 その他の法律による表示
C 加工食品の安全性とその評価
1 食品添加物
2 残留農薬
3 食品加工をとりまく環境問題
4 家畜・養殖魚の残留医薬品
5 輸入食品
6 食中毒
7 HACCPと安全性の確保
8 アレルギー食品に関する規定
9 食品安全委員会
10 国際食品規格委員会
練習問題
練習問題解答
索引
今日、わが国は、世界に類を見ないほど豊富な食材や食品が流通していて、欲しいと思えば何でも手に入る恵まれた食環境にある。しかし、一見、人々は飽食を謳歌して心身ともに健全な生活を営んでいるように見えるが、見逃すことのできない深刻な社会問題がある。その第一は、食生活の乱れに由来することで、若年層(特に、女性)が低栄養状態にあること、壮年層に肥満やメタボリックシンドロームなどをはじめ生活習慣病の発症増加が危惧されること、第二は、幼児や児童・生徒にみられる個食や孤食、偏食や欠食など、家庭で食卓を介した家族間のコミュニケーションが欠如し、子どもたちの健全な成長や人格形成に支障があること、さらに、食品の偽装表示やメディアの不確定な情報により助長される異常な食行動(フードファディズム)なども見受けられることである。
ライフスタイルの変化とともに、食生活を食品産業に依存する割合は高まっているのが明らかである。しかし、その問題点のために利便性に優れた今日の食生活を否定して昔に戻ることは意味がない。快適で豊かな食生活を実現するために、加工食品のサポートを生活文化や文明の自然な流れとして受け止めたい。それゆえに、多種多様な食品が登場し食情報が氾濫している中で、生産者のみならず生活者は、食に関する正しい知識をもつことが強く求められている。
このような背景を踏まえて、政府は、「食生活指針」や「健康日本21」の中で、栄養面だけでなく、自己管理、環境問題、生活文化の面まで言及し、わが国の風土や地域性を考慮した日本型食生活の見直しを求めるとともに、食事を通してコミュニケーションを図ることの大切さも指摘している。また、平成17(2005)年に「食育基本法」が施行されたことに伴い、子どもから高齢者までの食教育が国民的プログラムとして推進されている。
本書は、このような社会の要請に応えるため、〈栄養・健康科学シリーズ〉として平成3(1991)年に出版された好評書『食品加工学』の新版として、さらなる社会の変化や科学技術の進歩を加味して再編集された。管理栄養士・栄養士養成課程のテキストとして、国家試験ガイドラインを網羅しつつ、食品加工の原理等まで懇切な解説を加えた。また、製造工程など、統一感をもった豊富な図表で理解を助けるよう工夫した。さらに、国家試験の出題様式に準じた練習問題を加え学習効果の向上を図った。なお、食品の名称や成分の用語は原則として『五訂増補日本食品標準成分表』に準じた。本書は、管理栄養士・栄養士を目指す学生はもちろんのこと、農学・工学の分野で食品科学を学ぶ学生全般にも広く使えるよう編集されている。
2010年11月
編者