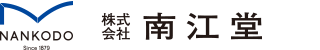コンパクトシリーズ
コンパクト生化学改訂第3版
こちらの商品は改訂版・新版がございます。
| 編集 | : 大久保岩男/賀佐伸省 |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-26226-7 |
| 発行年月 | : 2011年4月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 230 |
在庫
定価2,200円(本体2,000円 + 税)
正誤表
-
2013年01月31日
第1刷
- 商品説明
- 主要目次
- 序文

看護学生をはじめとするコメディカル学生が、生化学の基礎を限られた時間内で身に付けることを目指して編集された、コンパクトで分かりやすい教科書。「第3版」では生化学と疾患との関係を豊富に盛り込み、臨床における生化学の重要性を一層理解できる構成とした。用語解説と相互参照を充実させ、学習目標と併せて自学自習を促す構成となっている。
第1章 序論
1 コメディカルと生化学
2 生体分子
1 化学結合
a 共有結合
b イオン結合
c 水素結合
2 分子量や濃度の表し方
a 分子量
b 濃度
c 単位
3 生体の構成物質
a タンパク質
b 糖質
c 脂質
d 核酸
第2章 細胞の基本構造と機能
1 細胞の基礎
2 膜
3 細胞骨格
1 微小管
2 ミクロフィラメント
3 中間径フィラメント
4 細胞小器官
1 核
2 ミトコンドリア
3 小胞体
a リボソーム
b 粗面小胞体
c 滑面小胞体
4 ゴルジ体
5 リソソーム
6 ペルオキシソーム
第3章 生体成分の構造と機能
1 糖質
1 単糖類
a 単糖の異性体構造
b 単糖の種類と働き
c 糖誘導体
2 少糖類
3 多糖類
a ホモ多糖
b ヘテロ多糖
4 複合糖質
5 糖質の性質と機能
a 性質
b 機能
2 脂質
1 単純脂質
a ろう
b アシルグリセロール
2 複合脂質
a リン脂質
b 糖脂質
c ミセルと脂質二重層
3 誘導脂質とその他の脂質
a 脂肪酸
b ステロイド
c 脂溶性ビタミン
d リポタンパク質
3 アミノ酸とタンパク質
1 アミノ酸
a 構造と性質
b 種類と必須アミノ酸
c ペプチド結合
2 タンパク質
a 構造
b 性質
c 分類
4 核酸
1 ヌクレオチド
a 種類と構造
b 働き
2 ポリヌクレオチド
a DNA
b RNA
5 ビタミン
1 種類と働き
a 脂溶性ビタミン
b 水溶性ビタミン
2 ビタミンの利用
第4章 代謝
1 酵素と代謝
1 酵素の働き
a 酵素反応の条件
b 酵素反応とエネルギー
2 酵素反応の速度論
a 酵素反応の速度
b 酵素の活性
c KmとVmax
3 酵素の反応機構
4 酵素活性の影響因子
5 酵素活性の調節
6 酵素による診断
2 エネルギー代謝とその調節
1 生体エネルギー
a エネルギー通貨
b ATP産生
3 糖質の代謝
1 消化と吸収
a 口腔・胃・小腸
b 肝臓の働き
2 グリコーゲン代謝
a グリコーゲン合成
b グリコーゲン分解
3 解糖と糖新生
a 解糖反応
b クエン酸回路
c 電子伝達系
d 2つのシャトル
e 糖新生
4 ペントースリン酸回路とグルクロン酸回路
5 血糖調節と糖尿病
a 血糖値
b 血糖調節
c 糖尿病
4 脂質の代謝
1 消化と吸収
a 分解と吸収
b 脂質の運搬
2 脂肪酸の分解
a 脂肪酸のエネルギー産生
b β酸化
c ATP産生量
3 ケトン体
4 脂肪酸の生合成
5 コレステロール代謝
a コレステロールの働き
b コレステロールの合成
6 胆汁酸とステロイドホルモンの生合成
7 プロスタグランジン
5 アミノ酸とタンパク質の代謝
1 タンパク質の消化と吸収
a 胃の消化作用
b 小腸の消化作用
c アミノ酸の吸収
2 アミノ酸の代謝
a アミノ酸の分解
b アミノ酸の生合成
c ケト酸の代謝
d アミノ酸由来の生体物質
3 アミノ酸の代謝異常
4 窒素平衡
6 三大栄養素と代謝
1 糖質と脂質とアミノ酸の関係
2 代謝調節
a 臓器の代謝
b 飢餓とストレス
7 ヌクレオチドの代謝
1 ヌクレオチドの合成
2 ヌクレオチドの分解
8 ポルフィリンと胆汁色素の代謝
1 ポルフィリンの合成
2 ポルフィリンの分解と胆汁色素
a ビリルビン
b 黄疸
9 水と無機質の代謝
1 水の分布
2 水の代謝
3 無機質と代謝
10 酸塩基平衡
1 酸と塩基とpH
2 血液の緩衝作用
3 腎臓と肺の調節機構
4 アシドーシスとアルカローシス
a 呼吸性アシドーシス
b 呼吸性アルカローシス
c 代謝性アシドーシス
d 代謝性アルカローシス
第5章 核酸とタンパク質の生合成
1 核酸の構造と機能
2 DNAの複製
1 細胞周期
2 半保存的複製
3 複製の制御
4 DNAポリメラーゼ
5 不連続複製
6 複製に関与するその他の酵素
3 DNAの修復
4 RNAの合成
1 転写とその調節
2 RNAのプロセシング
3 遺伝子発現の制御
5 タンパク質の生合成
1 コドンとアンチコドン
2 翻訳
3 分泌タンパク質・膜タンパク質の翻訳
6 遺伝の生化学
1 遺伝と染色体
2 メンデルの法則
3 遺伝形式
4 母性遺伝(細胞質遺伝)
5 遺伝子工学
a ハイブリダイゼーション
b 塩基配列決定法
c ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)
6 遺伝病の原因
第6章 ホメオスタシスとホルモン
1 ホルモンの分類
2 ホルモンの作用機序
1 ステロイドホルモンと甲状腺ホルモン
2 ペプチドホルモン
a cAMPを介する作用機序
b cGMPを介するホルモン作用
c リン脂質とカルシウムイオンを介するホルモン作用
3 ホルモン各論
1 視床下部
2 下垂体
a 下垂体前葉
b 下垂体後葉
3 甲状腺
a 甲状腺ホルモン(T3およびT4)
b カルシトニン(CT)
4 副甲状腺(上皮小体)
a 副甲状腺ホルモン(PTH)
5 膵臓
a インスリン
b グルカゴン
c ソマトスタチン
6 副腎
a 副腎髄質
b 副腎皮質
7 性腺
a 精巣
b 卵巣
8 消化管
a ガストリン
b コレシストキニン
c セクレチン
9 プロスタノイド
10 神経伝達物質
第7章 臓器の生化学
1 循環器系
1 心臓
2 呼吸器系
1 肺
a ガス交換
b 酸素の運搬
c 二酸化炭素の運搬と酸塩基平衡
3 消化器系
1 胃・十二指腸・小腸・大腸
a 胃
b 十二指腸・空腸・回腸
c 大腸
2 膵臓
3 肝臓・胆嚢
a 肝臓の機能
4 泌尿器系
1 腎臓
a 酸塩基平衡
b 腎臓と血圧
c 腎臓と生理活性物質
d 尿の成分
5 神経系
1 神経の化学的成分
2 神経刺激の伝達
6 血液
1 血漿成分
a 血漿タンパク質
2 血液凝固
a 血液凝固・線溶機序
b 血液凝固異常症
3 血球成分
a 赤血球
b 白血球
c 血小板
第8章 がんの生化学
1 細胞周期
2 細胞増殖
3 アポトーシス
1 細胞死
2 アポトーシス
4 発がんの分子機構とがん遺伝子
1 発がん
a がんの原因
b がんと遺伝子
2 がん遺伝子とがん抑制遺伝子
3 腫瘍マーカー
第9章 免疫の生化学
1 免疫担当細胞と免疫応答
1 細胞性免疫
a マクロファージ
b 顆粒球
c リンパ球
2 液性免疫
a 抗原
b 抗体
2 補体系
1 古典経路
2 副経路
3 免疫疾患
1 アレルギー
2 免疫不全
参考図書
索引
本書は初版の発行から5年目に第2版となる改訂を行い、現在12年目を迎えて改訂第3版を発行するに至った。本書は医療人を目指す学生あるいは医学を学ぶ多くの人々に利用されてきたが、その間、医学教育に携わる人々や現場で働く多くの医療従事者の方々から貴重なご助言やご教唆を戴き、版を重ねるごとにそれらのご意見を取り入れて、次第にその充実度や成熟度を増してきた。十年一昔と言うが、医学の分野ではこの間に多くの新たな発展があり、医学の基礎的な学問である生化学の分野でも多くの新たな知見が見いだされた。したがって、本改訂版ではこれらの知見を、本書の特徴である「できるだけコンパクトかつ平易に」という視点で分かりやすく解説し、より一層理解しやすい教科書になるよう改訂した。また、第3版の特徴として、より臨床医学に即した今日的な事項およびその解説を新たに欄外に取り上げ、理解を深めるための一助とした。さらに、医学領域にとどまらず、関連する他領域にも踏み込んで解説した箇所もあり、幾分欲張りすぎたきらいもあるが、その点は本書の特質として看過して頂きたい。
医療面における生化学の役割は、一部の例を除いて、ともすると表立って活躍する他領域の学問とは無縁のように見える。しかし、生化学は解剖学や生理学と同様に医学の基礎を築く学問であり、生命現象を化学という言葉で説明しようとするところに特徴を持っている。したがって、化学を駆使する点が生化学を学ぶ上で二の足を踏む原因となっているが、医療人育成関連の生化学教育では他領域、例えば農学や理学の生化学とは自ずとその目的が異なり、学ぶ細目や深度も当然、選ばれてしかるべきと思われる。本書はそれらの点も考慮して編纂されている。本書は看護師や臨床検査技師、放射線技師などの学生を対象にした生化学書であるが、医学部にあって正規に使用する教科書とは別に本書を読み込む学生や、生化学を気楽に復習しようとする現役の医師にも広く利用され、好評を得ている事を付記しておく。
2011年1月
編者