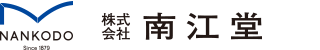シンプル理学療法学シリーズ
運動器障害理学療法学テキスト
こちらの商品は改訂版・新版がございます。
| 監修 | : 細田多穂 |
|---|---|
| 編集 | : 高柳清美/中川法一/木藤伸宏/細田昌孝 |
| ISBN | : 978-4-524-24254-2 |
| 発行年月 | : 2011年10月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 352 |
在庫
定価4,950円(本体4,500円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文

臨床をベースとした内容で構成。障害と疾患の基本的理解と、根拠に基づく介入法とその実践に必要な整形外科学・運動学など基礎学問を盛り込んでいる。障害部位別、機能障害別に理学療法アプローチ、理学療法評価、ADLについて解説。理学療法後の効果について“エビデンス”の項目を設け、二次情報を示した。
1 運動器系障害学総論
A 運動器障害とは
1 運動器とは
2 運動器障害に対する理学療法の歴史
a.Therapeutic Exercise
b.『リハビリテーション技術全書』
c.運動器障害に対する理学療法の変化の背景
B 運動器障害における基礎:炎症、再生、修復、癒合など
1 炎症症状
2 運動器の炎症
a.浮腫
b.癒着
c.筋スパズム(防御的筋収縮)
d.関節内圧の亢進
3 運動器の修復過程
a.筋の修復
b.骨癒合
c.靱帯の修復
d.腱の修復
C 理学療法介入の目的と原則
1 理学療法介入の目的
2 理学療法アプローチの原則
3 評価の目的と原則
a.外傷性障害
b.退行変性障害
D 理学療法の一般的介入アプローチ
1 運動療法
a.筋の収縮様式を考慮した運動療法の導入
b.荷重感覚の重要性
c.開放性運動連鎖(OKC)の運動療法
d.閉鎖性運動連鎖(CKC)の運動療法
e.筋力強化のポイント
2 主な物理療法の適応と禁忌
3 装具
関節機能障害
2 骨・軟骨障害(1)変形性関節症(総論)
A 変形性関節症の概論
1 疫学
2 病態
3 臨床症状
B 整形外科的治療
1 薬物療法
2 手術療法
C 理学療法の目的と原則
D 理学療法の一般的アプローチ
1 筋力増強運動
2 関節可動域運動
3 日常生活動作(ADL)練習
4 装具療法
5 物理療法
6 患者教育
3 骨・軟骨障害(2)変形性脊椎症
A 疾患の概略
B 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.脊柱
b.椎間板
C 理学療法評価
a.現病歴
b.既往歴
c.職業
d.X線所見
e.疼痛
f.関節可動域(ROM)
g.知覚
h.姿勢
i.体幹の機能評価
D 理学療法プログラム
a.安静
b.牽引療法
c.装具療法
d.温熱療法
e.治療体操
f.日常生活
4 骨・軟骨障害(3)変形性膝関節症(保存療法)
A 疾患の概略
B 整形外科的保存治療の概略
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.立位荷重線(ミクリッツ線)と大腿脛角(FTA)
b.姿勢
c.内側・外側スラスト
D 理学療法評価
a.問診による情報収集
b.画像からの情報収集
c.膝関節の触診
d.関節可動域(ROM)
e.筋力
f.姿勢・動作分析
g.ADL
h.その他
E 理学療法プログラム
1 理学療法の目的
a.軽度-中等度膝OA(K/L分類の1、2)
b.重度膝OA(K/L分類の3、4)
2 関節可動域(ROM)運動
a.目的
b.留意点
3 筋力増強運動
a.目的
b.留意点
c.筋力増強の一例
4 装具療法とADL練習
5 物理療法
F 理学療法関連のエビデンス
5 骨・軟骨障害(4)変形性膝関節症(手術療法)
A 整形外科的治療の概略
1 関節鏡視下手術
2 高位脛骨骨切り術
3 人工膝単顆置換術unicompartmental knee arthroplasty(UKA)
4 人工膝関節全置換術(TKA)
B 理学療法評価
1 術前理学療法評価
2 術後理学療法評価
a.手術に関する情報収集
b.静脈血栓塞栓症
c.感染徴候
d.疼痛
e.筋力
f.関節可動域(ROM)
g.平衡機能
h.歩行
i.ADL、QOL
C 術前、術後の理学療法プログラム
1 術前理学療法プログラム
2 術後理学療法プログラム
a.静脈血栓塞栓症の予防
b.感染予防
c.浮腫軽減
d.筋力増強運動
e.ROM運動
f.平衡機能
g.歩行練習
h.ADL
i.物理療法
D 理学療法関連のエビデンス
6 骨・軟骨障害(5)変形性股関節症(保存療法)
A 疾患の概略
B 整形外科的保存治療の概略
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.立位荷重線(ミクリッツ線)
b.頸体角
c.股関節合力とパウエルの理論
d.デュシェンヌ-トレンデレンブルグ徴候
D 理学療法評価
1 問診による情報収集
2 疼痛
a.他動運動時痛
b.触圧痛
3 アライメント
4 関節可動域(ROM)
a.可動域制限の発現様式
b.筋の短縮
5 筋力
6 ADL
7 歩行観察
E 理学療法プログラム
1 ADL(装具療法を含む)
2 関節可動域(ROM)運動
a.前股関節症、初期股関節症
b.進行期股関節症、末期股関節症
3 全期を通して注意すべきこと
4 筋力増強運動
a.目的
b.留意点
F 理学療法関連のエビデンス
G 筋力トレーニング(ホームプログラム)
1 ゴムバンドを使った筋力強化運動ほか
2 CKC運動
7 骨・軟骨障害(6)変形性股関節症(手術療法)
A 整形外科的治療の概略
B 術前、術後の理学療法
1 術前の理学療法
2 術後の理学療法
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.CE角
b.シャープ角
c.下肢長:棘果長と転子果長
d.二関節筋の制約作用
e.知覚と運動の相互作用
D 理学療法評価
a.術前の評価
b.術中および手術結果
c.問診による情報収集
d.疼痛
e.アライメント
f.ROMと筋力:術後のポイント
g.ADLと歩行
E 理学療法プログラム
a.術前、術後の指導(ADL練習を含む)
b.疼痛に対する理学療法(術後の疼痛に対して)
c.ROM運動
d.筋力増強運動
e.歩行練習と水中運動療法
f.ホームプログラムの指導(ADL上の工夫を含む)
F 理学療法関連のエビデンス
8 演習1
課題
解説
9 関節軟部組織性障害(1)靱帯損傷・半月板損傷概論
A 疾患の概略
1 靱帯損傷、半月板の受傷機転
2 分類
a.靱帯損傷
b.半月板損傷
3 症状
a.靱帯損傷
b.半月板損傷
B 整形外科的治療の概略
a.前十字靱帯
b.後十字靱帯
c.半月板損傷
C 運動学的理解のためのキーワード
1 関節運動の制動機構
2 半月板と靱帯の機能
a.半月板
b.十字靱帯
c.膝関節側副靱帯
d.足関節側副靱帯
3 関節位置覚と関節運動覚
a.メカノレセプターとは
b.関節位置覚、運動覚の機能低下の原因
c.関節位置覚、運動覚の機能低下の影響
d.関節位置覚、運動覚の機能低下に対する理学療法の効果
D 理学療法介入の目的と原則
1 血行の重要性と関節軟骨と滑液について
2 関節の不動・固定での運動器への弊害
3 早期からの関節運動の重要性
E 理学療法の一般的アプローチ
1 救急処置(RICE処置)
2 神経-運動器協調トレーニング法
3 神経-運動器協調トレーニングの基本事項
4 メカノレセプターの姿勢制御における重要性
5 強化のためのポイント
6 実際のトレーニング
10 関節軟部組織性障害(2)前十字靱帯・後十字靱帯損傷
A 疾患の概略
1 前十字靱帯損傷(ACL損傷)
2 後十字靱帯損傷(PCL損傷)
B 整形外科的治療の概略
1 ACL損傷
a.保存療法
b.手術療法
2 PCL損傷
a.保存療法
b.手術療法
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.4節リンク機構
b.終末強制回旋運動
c.膝屈曲角度の違いによる、大腿四頭筋の収縮と脛骨前方への剪断力
d.開放性運動連鎖(OKC)、閉鎖性運動連鎖(CKC)運動時のACLに加わる張力
D 理学療法評価
a.病歴
b.視診
c.触診
d.疼痛
e.関節可動域(ROM)
f.筋力
g.機能のテスト
h.特殊なテスト
i.定量的脛骨前後移動量検査
E 理学療法プログラム
1 ACL再建術後の理学療法プログラム
a.ROM運動
b.筋力強化運動
c.物理療法
d.バランストレーニング
e.心肺機能トレーニング
f.敏捷性トレーニング
2 PCL再建術後の理学療法プログラム
a.ROM運動
b.筋力強化運動
F 理学療法関連のエビデンス
11 関節軟部組織性障害(3)膝内側側副靱帯、半月板および足関節外側側副靱帯損傷
A 疾患の概略
1 膝内側側副靱帯損傷(MCL損傷)
2 半月板損傷
3 足関節外側側副靱帯損傷(足関節靱帯損傷)
B 整形外科的治療の概略
1 MCL損傷
2 半月板損傷
3 足関節靱帯損傷
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.大腿脛骨角(FTA)とQ-angle
b.screw-home movement(終末強制回旋運動)
c.extension lag(伸展不全)
d.leg-heel alignment
D 理学療法評価
a.情報収集
b.一般的炎症所見
c.関節可動域(ROM)
d.筋力
e.アライメント
f.荷重位での評価
E 理学療法プログラム
a.ROM運動
b.筋力増強運動
c.動作指導
F 理学療法関連のエビデンス
12 関節構造に由来する障害(1)脱臼
A 疾患の概略
1 肩関節脱臼
2 股関節脱臼
3 膝蓋骨脱臼
B 整形外科的保存治療の概略
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
1 肩関節脱臼
2 股関節脱臼
3 膝蓋骨脱臼
a.Q-angle
b.膝蓋骨の安定化機構
D 理学療法評価
1 問診による情報収集
2 疼痛
3 アライメント
a.肩関節脱臼
b.股関節脱臼
c.膝蓋骨脱臼
4 関節可動域(ROM)
5 筋力
6 ADL
7 スポーツ動作
8 関節不安定性テスト
E 理学療法プログラム
1 ADL練習
2 関節可動域(ROM)運動
a.肩関節脱臼
b.股関節脱臼
c.膝蓋骨脱臼
3 筋力増強運動
4 動作獲得
F 理学療法関連のエビデンス
G トレーニング
a.肩関節エクササイズ
b.股関節エクササイズ
c.膝蓋骨エクササイズ
13 関節構造に由来する障害(2)動揺関節、関節不安定性
A 疾患の概略
1 肩関節
2 股関節
3 膝関節
4 足関節
B 整形外科的治療の概略
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.関節安定化機構
b.関節深層筋
c.関節のメカノレセプター
d.神経-筋協調性
D 理学療法評価
a.問診による情報収集
b.疼痛
c.関節可動域(ROM)
d.筋力
e.関節不安定性検査
f.全身関節弛緩性検査
g.機能的不安定性の評価
E 理学療法プログラム
1 動的安定化エクササイズ
a.個別の筋機能改善エクササイズ
b.神経-筋協調性改善エクササイズ
2 装具
F 理学療法関連のエビデンス
14 演習2
課題
解説
関節外機能障害
15 骨性障害(1)骨折
A 骨折の要因
1 外力、応力による骨折
2 骨折の分類
a.単純骨折simple fracture
b.開放骨折、複雑骨折compound fracture
3 特殊な骨折
a.疲労骨折
b.病的骨折
B 骨折の治癒過程
1 骨癒合の過程
2 骨癒合の条件
C 整形外科的治療の概略(固定法、合併症など)
1 骨折治療の三原則
2 症状
a.全身症状
b.局所症状
3 合併症
a.骨折の合併症
b.骨折治癒後の合併症
c.固定法
D 高齢者骨折の概略
E 理学療法介入の目的と原則
a.安静・固定期
b.回復期(仮骨形成期)
c.骨癒合完成期(治癒)
F 理学療法評価
a.情報収集内容
b.形態測定
c.感覚および知覚
d.疼痛
e.ROM
f.筋力検査
g.動作分析
h.ADLテスト
G 理学療法の一般的アプローチ
a.高齢者の骨折の場合
b.小児骨折の場合
H 理学療法プログラム
a.オリエンテーション
b.全身調整運動
c.ポジショニング
d.筋力増強・維持運動
e.ROM維持・改善運動
f.患肢の浮腫防止
g.物理療法
h.装具の目的と機能的骨折治療器具の適応
i.呼吸理学療法
j.ADL練習(外泊・歩行練習を含む)
16 骨性障害(2)大腿骨頸部骨折、転子部骨折(術前、術後)
A 疾患の概略
B 整形外科的治療の概略
1 大腿骨頸部骨折
2 大腿骨転子部骨折
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
1 人工骨頭の脱臼
a.脱臼の発生
b.脱臼を起こす運動方向
2 早期荷重を実現させるための外科的工夫
a.骨接合術
b.人工骨頭置換術
3 人工関節への応力
a.SLRによる股関節への応力
b.杖による免荷歩行
D 理学療法評価と注意点
a.患者、家族の問診による生活・運動能力の情報収集
b.カルテ、術者、医師による情報収集
c.看護師より病棟での生活・運動能力情報を得る
d.疼痛
e.関節可動域(ROM)
f.筋力
g.形態測定
h.神経-筋協調性・立位平衡機能テスト
i.基本動作、ADL
j.知覚
E 理学療法プログラム
1 術前の理学療法
a.インフォームド・コンセント
b.理学療法のオリエンテーション
c.理学療法の実際
2 ベッドサイドの理学療法
a.骨接合術
b.人工骨頭置換術
3 体重負荷の時期について
a.早期荷重の場合
b.荷重時期が遅れる場合
4 術後免荷期の理学療法
5 部分荷重期の理学療法
6 全荷重期の理学療法
F 理学療法関連のエビデンス
17 骨性障害(3)大腿骨頸部骨折、転子部骨折(術後回復期)
A 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.T字杖の使用と荷重量
b.諸動作における大腿骨骨頭部分にかかる応力(対体重比)
B 理学療法評価
a.情報収集
b.全身状態
c.認知機能
d.疼痛
e.形態計測
f.ROM検査
g.筋力
h.姿勢、バランス
i.感覚
j.ADL
k.社会的因子
l.家屋調査(家庭環境)
C 理学療法プログラム(術後回復期)
a.ROM運動
b.筋力増強運動
c.バランス運動
d.ADL練習
D 理学療法関連のエビデンス
18 骨性障害(4)下肢の骨折
A 疾患の概略
1 大腿骨骨幹部骨折
2 大腿骨遠位部骨折
3 脛骨高原骨折
4 膝蓋骨骨折
5 下腿骨折
6 踵骨骨折
B 整形外科的治療の概略
1 治療
a.牽引療法
b.観血的骨接合術
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.伸展機能不全extension lag
b.ウォルフ(Wolff)の法則
D 理学療法評価
a.X線所見(医師と十分に相談)
b.疼痛
c.ROM
d.筋力
e.感覚
f.その他
E 理学療法プログラム
a.リラクセーション
b.ROM運動(他動、自動介助、自動)
c.筋力増強運動
d.荷重練習
e.装具療法
f.物理療法
F 理学療法関連のエビデンス
19 骨性障害(5)上肢の骨折
A 疾患の概略
1 上腕骨近位端骨折
2 上腕骨骨幹部骨折
3 上腕骨顆上骨折
4 コーレス骨折
B 整形外科的治療の概略
1 上腕骨近位端骨折
2 上腕骨骨幹部骨折
3 上腕骨顆上骨折
4 橈骨遠位端骨折(コーレス骨折)
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.第2肩関節
b.肩甲上腕リズム
c.肘角
d.橈骨遠位端の形態的特徴
e.手関節
D 理学療法評価
a.医師、診療記録、画像からの情報
b.医療面接(問診)
c.疼痛
d.視診、触診
e.形態学的測定
f.感覚
g.関節可動域(ROM)、筋力
h.ADL
E 理学療法プログラム
1 共通事項
a.運動療法
b.物理療法
c.日常生活指導
2 各骨折の運動療法
a.上腕骨近位端骨折
b.上腕骨骨幹部骨折
c.上腕骨顆上骨折
d.コーレス骨折
F 理学療法関連のエビデンス
20 骨性障害(6)脊椎の骨折
A 疾患の概略
1 脱臼骨折
2 圧迫骨折
B 整形外科的治療の概要
1 脱臼骨折
2 圧迫骨折
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.脊柱の変形
b.脊柱変形と姿勢異常
D 理学療法評価
1 問診による情報収集
a.受傷時の状況を詳細に収集する
b.脊椎圧迫骨折に伴う合併症の有無
2 疼痛
3 関節可動域(ROM)
4 筋力
5 感覚・運動麻痺
6 ADL
7 姿勢およびアライメントの評価
8 歩行の観察
E 理学療法プログラム
a.運動療法
b.物理療法
c.装具療法
F 理学療法関連のエビデンス
21 実習1 下肢荷重練習
課題
解説
22 演習3
課題
解説
23 筋・軟部組織性障害(1)テニス肘、野球肘、手根管症候群
A 筋・軟部組織性障害の概論
1 過用症候群
2 筋・軟部組織性障害の好発部位
B 疾患の概略
1 テニス肘
2 野球肘
a.内側型野球肘
b.外側型野球肘
c.後側型野球肘
3 手根管症候群
C 整形外科的治療の概略
1 テニス肘
2 野球肘
3 手根管症候群
D 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.carrying angle
b.投球動作
c.手根管内圧と横アーチ
E 理学療法評価
1 テニス肘、野球肘
a.問診による情報収集
b.疼痛
c.関節可動域(ROM)
d.筋力
e.ADL
2 手根管症候群
a.視診、触診
b.感覚
c.筋力
d.電気生理学的検査
e.その他
f.ADL
F 理学療法プログラム
1 テニス肘、野球肘
a.関節可動域(ROM)運動
b.筋力増強運動
c.物理療法および装具療法
2 手根管症候群
a.保存療法の適応とアプローチ期間の目安
b.手関節の装具固定
c.筋力増強運動
d.ADL練習
G 理学療法関連のエビデンス
a.テニス肘
b.野球肘
c.手根管症候群
24 筋・軟部組織性障害(2)肩関節周囲炎
A 疾患の概略
B 整形外科的治療の概略
1 薬物療法
2 局所注射療法
3 パンピングpumping療法、joint distension
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.広義の肩関節
b.狭義の肩関節(肩甲上腕関節)
c.肩甲上腕リズム
d.三角筋と棘上筋の共同作用
e.関節上腕靱帯、axillary pouch(dependent pouch)
f.quadrilateral space(後方四角腔)
D 理学療法評価
a.問診による情報収集
b.疼痛
c.アライメント
d.ROM
e.筋力
f.ADL
g.その他
E 理学療法プログラム
1 freezing phase(疼痛性痙縮期)
a.運動療法
b.物理療法
c.ADL練習
2 frozen phase(拘縮期)からthawing phase(回復期)
a.運動療法
b.物理療法
c.ADL練習
F 理学療法関連のエビデンス
25 筋・軟部組織性障害(3)筋断裂・アキレス腱断裂
A 疾患の概略
B 整形外科的治療の概略
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
1 筋断裂
a.羽状筋
b.遠心性収縮
c.筋腱移行部
2 アキレス腱断裂
a.危険領域
b.踵骨のアライメントとアキレス腱断裂との関係
D 理学療法評価
a.問診による情報収集
b.視診と触診
c.疼痛
d.周径
e.関節可動域(ROM)
f.筋力
g.トンプソンテストThompson's squeeze test
h.後足部のアライメント計測
i.ADL
j.パフォーマンステスト
k.その他
E 理学療法プログラム
a.RICE処置
b.ROM運動
c.筋力増強運動
d.歩行練習
e.スポーツ活動
f.再発の予防
F 理学療法関連のエビデンス
a.筋断裂
b.アキレス腱断裂
関節内外複合障害・その他
26 Motor unit性障害
A 疾患の概略
B 整形外科的治療の概略
a.サンダーランドのType1、2
b.サンダーランドのType3
c.サンダーランドのType4、5、6
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.橈骨神経麻痺
b.尺骨神経麻痺
c.正中神経麻痺
d.腕神経叢麻痺
e.腓骨神経麻痺
D 理学療法評価
a.チネル徴候
b.徒手筋力検査法
c.知覚検査
d.電気生理学的検査
e.ROM
f.自律神経検査
E 理学療法プログラム
a.疼痛の軽減
b.ROM運動
c.筋力増強運動
d.電気刺激療法
e.固有知覚を利用した運動学習
f.グライディングテクニック
g.サポーター、テーピング、装具
h.バイオフィードバック訓練
F 理学療法関連のエビデンス
27 脊椎性障害(1)概論、頸椎椎間板ヘルニア、頸部脊柱管狭窄症
A 疾患の概略
1 頸椎椎間板ヘルニアcervical disc herniation
a.症状
b.鑑別疾患
2 頸部脊柱症cervical spondylosis
3 頸部後縦靱帯骨化症ossification of posterior longitudinal ligament(OPLL)
B 整形外科的治療の概略
1 保存療法
a.安静・固定
b.装具療法
c.薬物療法
2 手術療法
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
1 頸椎矢状面でのアライメント
2 頸椎レベルと可動性
3 ルシュカ(Luschka)関節
4 頸胸椎移行部と自律神経系
D 理学療法評価
1 問診
2 視診
a.前方からの視診
b.側面からの視診
c.後面からの視診
3 触診
4 関節可動域(ROM)
5 神経学的検査
6 神経伸張テスト
7 その他のテスト
E 理学療法プログラム
1 保存療法の理学療法
a.疼痛軽減
b.可動域改善運動
c.筋力増強運動
d.ADL練習
2 手術療法前後の理学療法
a.手術前の理学療法
b.手術後理学療法
F 理学療法関連のエビデンス
28 脊椎性障害(2)(急性腰痛)腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症
A 疾患の概略
1 腰椎椎間板ヘルニア
2 腰部脊柱管狭窄症
B 整形外科的保存治療の概略
1 腰椎椎間板ヘルニア
2 腰部脊柱管狭窄症
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
1 腰椎椎間板ヘルニア
a.姿勢と髄核
b.各種動作による椎間板内圧
c.椎間板の栄養
2 腰部脊柱管狭窄症
a.姿勢と間欠跛行
b.腰部脊柱管狭窄症における虚血性因子
D 理学療法評価
a.下肢筋力テストおよび神経学的検査
b.神経学的所見
c.運動診
d.トレッドミルおよび自転車テスト
E 理学療法プログラム
1 腰椎椎間板ヘルニア
a.安静および物理療法
b.運動療法
c.姿勢指導
2 腰部脊柱管狭窄症
a.腰部超音波療法
b.運動療法
c.日常生活指導
3 術後理学療法
a.残存症状に対する理学療法
b.日常生活動作の指導
F 理学療法関連のエビデンス
29 脊椎性障害(3)慢性腰痛症
A 疾患の概略
B 整形外科的治療の概略
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.脊柱の生理的彎曲
b.骨盤後傾pelvic tilt
c.椎間関節の力学的支持機構
d.椎間板の線維輪と椎間板内圧
e.表層筋(腹直筋、内・外腹斜筋、腸肋筋)と深層筋(腹横筋、多裂筋)
f.屈曲と弛緩現象flexion relaxation phenomenon
D 理学療法評価
1 問診による情報収集
a.主訴の把握
b.罹病期間と症状の把握
c.職業・生活・家庭環境の把握
2 疼痛
a.安静時痛
b.自動運動時痛
c.他動運動時痛
3 立位、座位姿勢でのアライメント
a.位置、高さの確認
b.動きの確認
4 ROM
5 筋力
a.体幹筋力
b.下肢の筋力
6 神経学的所見
7 ADL
8 QOL
9 歩行観察
E 理学療法プログラム
1 運動療法
a.治療体操
b.ストレッチング
c.筋力強化
d.腰部脊柱安定化エクササイズ
2 教育的アプローチ
a.ADL練習
b.腰痛教室
3 精神医学的アプローチ
F 理学療法関連のエビデンス
a.運動療法
b.教育的アプローチ
c.物理療法
d.装具療法
30 複合障害(1)関節リウマチ(1)
A 疾患の概略
1 概念、疫学、病因
a.疾患の概念
b.疫学
c.病因
d.自然経過
2 臨床症状
a.全身症状(関節外症状)
b.関節症状
B 医学的治療の概略
1 診断
a.診断基準
b.鑑別疾患
2 評価法
a.疾患活動性の評価
b.病期
c.内臓病変、合併症の有無と種類
d.機能障害度
e.QOLの評価
3 治療
a.基本的な治療方針
b.薬物療法
c.手術療法
d.患者教育
C 運動学的疾患理解のためのキーワード
a.RAにみられる変形発生の機序
b.環椎前弓-歯突起間距離(ADI)
D 理学療法評価
a.カルテからの情報収集
b.問診による情報収集
c.機能と構造
d.活動と参加
e.環境因子
f.個人因子の評価
31 複合障害(2)関節リウマチ(2)
A 理学療法のための運動学・運動療法学的キーワード
a.三分力
b.交差運動(相反性収縮運動)
c.他動運動passive exercise
d.自動介助運動active assistive exercise
e.自動運動active exercise
f.抵抗運動resistive exercise
B 理学療法評価
1 情報収集
2 病状評価
3 障害評価
a.スタインブロッカー機能障害度分類(class分類)
b.各種日常生活動作評価
C 理学療法プログラム
a.鎮痛
b.ROM維持・改善練習
c.筋力維持・増強練習
d.歩行練習
e.日常生活動作指導
f.装具療法
D 理学療法関連のエビデンス
E リウマチ体操
32 複合障害(3)スポーツ障害
A スポーツ障害の疫学
1 スポーツ外傷の分類
2 スポーツ外傷の発生機序と受傷機転の把握
3 スポーツ外傷の発生要因
4 疫学
B 理学療法評価
a.問診による情報収集
b.視診、触診
c.形態測定
d.関節可動域(ROM)
e.筋力テスト
f.下肢アライメントチェック
g.整形外科的テスト
h.柔軟性のテスト各種
C スポーツ外傷発生時の対応と応急処置
1 RICE処置
2 脳振盪
a.受傷直後のチェック項目
b.受傷から数時間後の対応
3 熱中症
D 理学療法プログラム
1 トレーニングの原則
2 アスレチックリハビリテーションの概要
3 スポーツ外傷に対するトレーニングプログラム
a.メディカルリハビリテーションとアスレチックリハビリテーションの分類
b.プログラム作成上の注意点
4 トレーニングの種目による分類
a.患部に対する運動療法の形態
b.スポーツ復帰に向けたトレーニング
c.再発防止に向けたトレーニングの種類
5 テーピング
a.テーピングとは
b.テーピングの実際:足関節へのテーピング
c.テーピングの実際:膝関節のテーピング
6 物理療法
7 スポーツマッサージ
8 選手とのコミュニケーション
33 演習4
課題
解説
34 実習2 筋力強化運動
課題
解説
参考文献
索引
この度、シンプル理学療法学シリーズの1冊として、『運動器障害理学療法学テキスト』を上梓することとなった。本書では「障害別」の概念に沿い、関節機能障害、関節外機能障害、関節内外複合障害・その他の3障害に分類し、関節機能障害を、骨・軟骨障害、関節軟部組織性障害、関節構造に由来する障害に、関節外機能障害を、骨性障害、筋・軟部組織性障害に、関節内外複合障害・その他を、脊椎性障害、複合障害などに細分類し、講義28、演習4、実習2の34章に編集した。
本シリーズの特長の1つとして、「調べておこう」と「学習到達度自己評価問題」という項目を設けている。「調べておこう」では、運動器障害理学療法を学ぶ前に、整形外科疾患・外傷の病態、分類、治療戦略など講義の準備(自己学習)を置いて学習効果を高めるようにした。「学習到達度自己評価問題」では、講義で学んだことを可及的早期に振り返り学習し、運動器疾患の障害、理学療法評価、理学療法介入方法をより深く理解できるようにした。
本書の特長として、「理学療法関連のエビデンス」を設けたことがある。近年、“根拠に基づいた医療Evidence Based Medicine(EBM)”の興りと世界的な広がりは「運動器障害の理学療法」にも及んでいる。“臨床研究に基づいて統計学的に有効性が証明された治療”が重要視され、“より効果的な質の高い医療を提供すること”が求められている。章ごとに根拠に基づいた理学療法情報を取り入れ、システマチックレビュー、メタ分析などの一次、二次情報として挿入した。
各章ごとに「疾患の概略」「整形外科的治療の概略」では、疾患・障害の病態、原因から症状、治療までを、流れの中に構成するよう心がけ、整形外科の治療骨子、最小限の専門的知識や用語を記述するに止めた。「運動学的疾患理解のためのキーワード」では、運動学視点より障害の理解と理学療法評価、プログラムにつながる知識の整理を目指した。「理学療法評価」「理学療法プログラム」では、講義で学んだ知識・技術を確実に理解できる内容を目指した。全体を通じて、学生が運動器障害の理学療法をより理解しやすいように文章は可能な限り短い表現に止めた。「ヒント」では、臨床的なトピックをコラム形式にてまとめ、臨床的疑問に対して“考えるヒント、理解のヒント”となるように意図した。
多種多様な運動器疾患・外傷の障害は複雑多岐で、画一的な介入方法にまとめることは困難である。今後の医療技術の発展と障害分類の複雑化・細分化に対しどのような理学療法教育を構築するかは重要課題である。“Give a man a fish and you feed him for a day. Teach him how to fish and you feed him for a lifetime.(人に魚を与えれば1日食べられる。釣り方を教えれば一生食べられる)”という諺がある。知識や技術の伝授だけではなく、学生自らが学習し創造していく能力を培わせることが理学療法教育の根幹と考える。本書が理学療法士教育に寄与できることを希望してやまない。
2011年9月
編集者一同