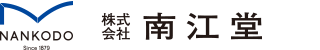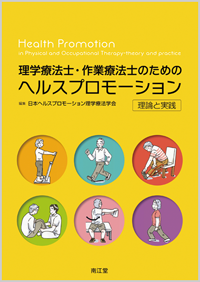理学療法士・作業療法士のためのヘルスプロモーション
理論と実践
こちらの商品は改訂版・新版がございます。
| 編集 | : 日本ヘルスプロモーション理学療法学会 |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-26755-2 |
| 発行年月 | : 2014年2月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 172 |
在庫
定価3,520円(本体3,200円 + 税)
サポート情報
-
2022年02月14日
「14章 ヘルスプロモーション関連法規」情報更新リーフレット
- 商品説明
- 主要目次
- 序文

理学療法士・作業療法士を目指す学生に向けてヘルスプロモーションについて解説したテキスト。ヘルスプロモーションの理論と実践について、初心者にもわかりやすく解説。学習の手助けとなるよう各章には用語解説、コラムなども配置し、理学療法士、作業療法士が関わる高齢者の介護予防について、効率的に学べるようになっている
1 ヘルスプロモーション総論
A ヘルスプロモーションとは
1 WHOの提唱するヘルスプロモーション
2 わが国におけるヘルスプロモーション
B 高齢者ヘルスプロモーションの重要性
C 老化の特徴
1 身体機能
a 形態的な変化
b 骨の変化
c 筋の変化
d 持久力の変化
e 歩行の変化
f 姿勢調節の変化
g 神経の変化
h 感覚の変化
2 認知機能
a 認知
b 記憶
c 注意
3 心理機能
a 感情
b 性格
4 社会性
D 高齢者の虚弱
1 高齢者の廃用症候群
2 高齢者の虚弱の原因
3 サルコペニアと虚弱
4 高齢者の虚弱予防策
コラム「ロコモティブシンドロームとサルコペニア」
E ヘルスプロモーションの進め方
1 健康な地域づくり
2 住民参加
3 行政関係者の関与
4 専門家の関与(理学療法士・作業療法士の役割)
コラム「地域ヘルスプロモーション実施の流れ」
2 高齢者の評価
A 評価の考え方
B 高齢者の評価を行う上での廃用症候群の理解
C 評価を行う上での留意点
コラム「緊急時の対処法」
D 問診の取り方
1 問診の基本
2 座る位置と距離
3 話す姿勢
4 聞く姿勢
5 高齢者の反応
a 特有の反応(1):作話
b 特有の反応(2):長考
c 特有の反応(3):訴えの量と病態の非相関
d 特有の反応(4):病態の理解困難
コラム「難聴への配慮」
E バイタルチェック
1 体温
2 脈拍
3 血圧
3 高齢者の身体機能評価I
A 形態計測
1 体重測定
2 身長測定
3 腹囲測定
4 BMI(Body Mass Index)
B 身体組成
1 生体電気インピーダンス法
2 皮下脂肪厚測定法
C 柔軟性
1 長座体前屈テスト
D 筋力
1 握力測定
2 下肢筋力測定
3 30秒椅子立ち上がりテスト
4 高齢者の身体機能評価II
A バランス機能
1 Timed“Up & Go”test(TUG)
2 Functional Reach Test(FRT、FR)
3 開眼片足立ちテスト
B 歩行能力
1 10m最大歩行速度
2 10m障害物歩行
C 活動能力
1 老研式活動能力指標
2 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)
コラム「歩行評価は、1.5m、5m、10mのいずれの距離が良いか?」
5 高齢者の身体機能評価III
A 持久力
1 局所持久力
2 全身持久力
a 心肺運動負荷テスト
b フィールドウォーキングテスト
B 呼吸機能
1 スパイロメトリー
2 呼吸筋力
3 パルスオキシメーター
コラム「SpO2はどこまで正確?」
C 循環機能
1 血圧
2 脈拍
3 二重積
6 高齢者の認知機能、精神・心理機能およびQOLの評価
A 認知機能
1 認知症のスクリーニングテスト
コラム「HDSRとMMSEのどちらを使用する?」
2 注意機能
B 精神・心理機能
1 PGCモラールスケール
2 Geriatric Depression Scale(GDS)
3 Profi le of Mood States(POMS)
C QOL
1 SF-36(MOS Short-Form 36-Item Health Survey)
2 視覚アナログ尺度(Visual Analogue Scale、VAS)
7 ヘルスプロモーションの実践I 虚弱予防
A 全身調整トレーニング
1 姿勢、動作練習
2 呼吸
3 ストレッチング
4 健康体操
5 ウォーキング
B レジスタンストレーニング
1 片足立ち
2 スクワット
C 日常生活での工夫
8 ヘルスプロモーションの実践II 転倒予防
A 転倒の疫学
B 転倒の原因
C 転倒予防の考え方
D 転倒予防の具体的取り組み
1 サルコペニアの改善
2 二重課題処理能力の改善
3 環境要因に対する簡便な対応策
4 地域全体の転倒発生率を抑制するには
9 ヘルスプロモーションの実践III 認知症予防
A 認知症予防施策の現状と課題
B 認知症と軽度認知障害
1 認知症の症状と治療の流れ
2 MCIの症状とその鑑別
コラム「簡易にMCIを鑑別する取り組み」
C 認知機能低下予防の取り組み
D 地域における認知機能低下予防の実際
E 認知機能低下予防介入を継続するための工夫
10 ヘルスプロモーションの実践IV 生活習慣病予防・改善
A 生活習慣病の疫学
B 生活習慣病発症予防のための身体活動水準および有酸素性作業能力
1 身体活動水準
2 有酸素性作業能力
C 生活習慣病改善のための運動処方と実践例
1 疾患者を対象とした有酸素運動およびレジスタンストレーニング強度の指針
a 有酸素運動
b レジスタンストレーニング(筋力強化運動)
2 基本運動プログラムおよび運動教室の実践例
D 運動処方時の注意点
1 有酸素運動
2 レジスタンストレーニング
E 健康チェックと運動の注意点
1 運動時の突然死
2 健康チェックと運動の注意点
11 行動科学とヘルスプロモーション
A 運動を習慣化させるには
B 行動変容ステージ
1 行動変容ステージとは
2 運動の習慣化における行動変容ステージの確認
3 行動変容ステージの活用
a 前熟考ステージ
b 熟考ステージ
c 準備ステージ
d 実行ステージ
e 維持ステージ
4 行動変容ステージの関連要素
a 意志のバランス
b セルフ・エフィカシー
12 要介護高齢者のヘルスプロモーション
A 在宅でのヘルスプロモーション
1 介護保険制度における居宅(在宅)サービスの役割
2 在宅を取り巻く現状
3 在宅で要求される視点
a 予防的視点の重要性
4 ヘルスプロモーションの展開例−家族構成別−
a 同居家族がいる要介護高齢者
b 独居の要介護高齢者
コラム「コーチングについて」
5 終末期について
B 入所施設でのヘルスプロモーション
1 介護保険制度における施設サービスの役割
2 入所施設を取り巻く現状
3 入所施設で要求される視点
a 集団体操やレクリエーション活動の有効利用
b 人間関係構築への支援
c ケアとリハビリテーションの一体化
コラム「ケア」
4 ヘルスプロモーションの展開例−要介護状態区分別−
a 要介護1レベル
b 要介護2、3レベル
c 要介護4、5レベル
C 通所施設でのヘルスプロモーション
1 介護保険制度における通所サービスの役割
2 通所施設を取り巻く現状
3 通所施設で要求される視点
a 情報共有の重要性
b 生活圏の拡大や役割の再獲得を意識した援助
4 ヘルスプロモーションの展開例−障害別−
a 脳血管障害
b 認知症
c 高齢による衰弱(虚弱)
13 ヘルスプロモーションのための住環境整備
A 老化に伴う住環境整備の必要性
1 住環境整備に当たっての心構え
2 介護保険制度下での住環境整備の要点
3 ヘルスプロモーションにおける住環境整備
B 住環境の評価
1 ヘルスプロモーションにおける住環境評価の概要
2 急性期における住環境評価の考え方
3 回復期における住環境評価の考え方と実際
4 住環境評価にかかる診療報酬と介護報酬
C 疾患別にみた住環境整備のポイント
1 脳血管障害後遺症
2 関節リウマチ
3 パーキンソン病
4 認知症
D 住環境整備の実際
1 トイレの改修例
2 浴槽に手すりを設置した例
コラム「ギャッチベッド? ギャッジベッド?」
14 ヘルスプロモーション関連法規
A 老人福祉法
1 地域密着型サービス
2 老人福祉施設、有料老人ホーム
B 高齢者の医療の確保に関する法律・健康増進法
C 介護保険法
1 保険者
2 被保険者
3 保険給付の内容と手続き
D その他の関連法規
1 医療保険制度
a 健康保険法
b 国民健康保険法
2 公的年金保険
3 身体障害者福祉法
4 支援費制度
15 ヘルスプロモーション研究の進め方
A 研究デザイン
1 研究デザインの分類
a 観察的研究
b 実験的研究(介入研究)
B 研究データの分析
1 データの尺度
2 パラメトリックとノンパラメトリック
3 統計学的分析方法
a カイ二乗検定(χ2検定)
b 2群の比較
c 3群の比較
d 相関と回帰分析
C 研究計画と研究倫理審査委員会
1 研究計画書、研究倫理審査申請書の作成
D 研究結果の公表
1 学術論文
2 学会発表
参考文献
索引
ヒトは、生まれてからも細胞分裂をくり返し、成長を続けるが、20歳を超えたあたりから老化が始まる。特に、60歳を超えると老化のスピードが加速し、急激に身体機能が低下する。誰もが健康で、不老長寿や健康長寿を望んでいるが、普段の生活を省みないで糖尿病・高血圧・高脂血症に代表される生活習慣病から、脳卒中や心疾患を発生するケースが多い。従来我々理学療法士・作業療法士は、障害を持った方の理学療法や作業療法を展開してきたが、現在社会問題となっている超高齢社会に、ここ10年から15年の間にうまく対応し、健康で生き生きとした在宅生活を、いかに長く続けさせられるかが、我々に課せられた課題である。
さらに、病気そのものを予防する「予防医療」の先駆的取り組みとして、「先端予防医療センター」が都内や大阪に誕生している。ここでは健康増進と疾病の早期発見・早期治療が行われ、今後全国各地に波及する見込みである。このような観点から、単なる長寿から「健康長寿」へとシフトし、予防医療や、診療や投薬だけでなく、今後は運動面や生活面において、病気を予防する取り組みがなされ、健康増進に根ざした研究がさらに加速されることが予想される。
このような状況で、我々理学療法士や作業療法士など健康増進に携わる職種を中心として、日本ヘルスプロモーション理学療法学会が誕生した。この学会では、「これまでのリハビリテーション医療の中心的役割を担ってきた従来の理学療法や作業療法に加え、疾病予防や介護予防、健康増進を含めた包括的な理学療法や作業療法」を、ヘルスプロモーション理学療法・作業療法と定義し、2011年2月に設立した。これまで2回の学会を開催し、さらに「ヘルスプロモーション理学療法研究」という学会誌を5冊発刊した。さらに会員向けの研修会をこれまで2回開催している。
しかし、理学療法士・作業療法士を対象としたヘルスプロモーションを包括的に取り扱った教育現場向けのテキストがなかったため、教科書として、本書『理学療法士・作業療法士のためのヘルスプロモーション−理論と実践』を企画した。ここに本書を皆さんにお届けできたことを大変嬉しく思う。執筆は教育現場の第一線で活躍されている方々にお願いした。この一冊にヘルスプロモーションのノウハウが詰め込まれ、理解しやすいよう配慮がなされている。本書が、ヘルスプロモーションをこれから学習しようとしている学生諸君や、若手理学療法士・作業療法士諸君のバイブルとなり、今後版を重ね、皆様に愛読されるようになれば幸いである。そのためには、皆様からのご意見やご要望をお寄せいただき、それに応えていくことで内容を充実させたい。今後温かいご支援をいただければ幸いである。
2013年11月
日本ヘルスプロモーション理学療法学会 理事長 山田道廣