��b�Ō�w�e�L�X�g������3��
EBN�u���̊Ō���H
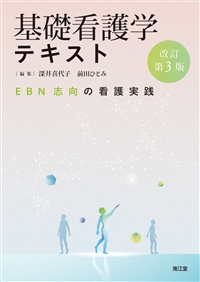
| �ҏW | : �[����q/�O�c�ЂƂ� |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-23495-0 |
| ���s�N�� | : 2023�N12�� |
| ���^ | : B5�� |
| �y�[�W�� | : 528 |
��
�艿5,940�~(�{��5,400�~ �{ ��)
- ���i����
- ��v�ڎ�
- ����

�����f�[�^�ɗ��t�����ꂽ�Ō���H�̎�����ڎw���C��b�Ō�w�̍L�͂ő��l�ȓ��e�ɂ��ĉ\�Ȃ����葽���̍����������Ȃ����������D�]�e�L�X�g�̉����ŁD���łł́C�V�����G�r�f���X�����ƂɑS�̂��������C�V���ڂƂ��āu�Q�m����ÂƊŌ�v�u���e�N�m���W�[�ƊŌ�v�u�r�֏�Q�ƃP�A�v����lj��D�Ō�̉Ȋw�������鍂���u�Ɛ[���w�т��T�|�[�g����C�Ō�w�n�����C�Ō�w���K�g�̏��D
�T �V����̊Ō�
�@�Ō�̑ΏۂƊŌ�w
�@�@�P�@�Ō�̑ΏۂƂ�
�@�@�Q�@�Ō�w�̌n�ɂ������b�Ō�w
�@�@�R�@��b�Ō�w�̍\���v�f
�A�V����̊Ō�̖���
�@�@�P�@�Љ�ɂ�����Ō�̃A�C�f���e�B�e�B
�@�@�Q�@���オ���߂�Ō�
�@�@�R�@�ϗ��I�ۑ�ɒ��ފŌ�
�@�@�S�@�ЊQ�Ō�
�B�Ȋw�I�Ō�̐��i
�@�@�P�@�Ō�w�ɂ�����o����`�Ɗ�b���_
�@�@�Q�@�P�A�Z�p�̐i����EBN
�@�@�R�@���H�ɂ����錤�����p
�C�Q�m����ÂƊŌ�
�@�@�P�@�Q�m����Â̓o��
�@�@�Q�@��`�Ō�
�@�@�R�@�Q�m����Âɂ�����Ō�̖���
�D�Ō�̃O���[�o���[�[�V����
�@�@�P�@�O���[�o���Ȏ��_�ŊŌ���Ƃ炦��K�v��
�@▶�R����▶�s���ϗe
�@�@�Q�@�O���[�o���Љ�ɂ�����Ō�w�j
�@▶�R����▶�E�F���l�X
�@▶�R����▶�Z�N�V�����e�B
�E���ҁE�Ƒ��̈ӎv����
�@�@�P�@�ӎv�������芪����
�@�@�Q�@�ӎv����Ƃ�
�@�@�R�@�Ō�E�Ƃ��Ă̈ӎv����x��
�@�@�S�@�ӎv����x���̃|�C���g
�F����ƊŌ�
�@�@�P�@�Ō�Ɋւ�鐧�x�Ɛ���̓���
�@▶�R����▶SDGs
�@�@�Q�@����̋��
�@▶�R����▶�n���P�A�V�X�e��
�U �Ō슈���W�J�̕��@
�@�Ō�ߒ�
�@�`�@�Ō�ߒ��Ƃ�
�@�@�P�@�Ō�ߒ��̗��j�I���W
�@�@�Q�@�Ō슈���ɂ�����Ō�ߒ��̈Ӌ`
�@�@�R�@�킪���ɂ�����Ō�ߒ��̔��W
�@�a�@�Ō�ߒ��̍\���v�f�Əz����
�@�@�P�@�Ō�ߒ��̍\���v�f
�@�@�Q�@�Ō�ߒ��̏z����
�@�b�@�Ō�ߒ��̊�ՂƂȂ闝�_
�@�@�P�@�Ō�ߒ��ƈ�ʗ��_
�@�@�Q�@�Ō�ߒ��ƊŌ엝�_
�@�@�R�@�Ō�ߒ��ƃN���e�B�J���V���L���O
�@�c�@�Ō�ߒ��̉ۑ�ƓW�]
�@�@�P�@���߂ĊŌ�ߒ��Ƃ�
�@�@�Q�@�Ō�ɂ�����P�A�����O�̍čl
�A�Ō슈���̏��
�@�`�@�Ō슈��
�@�@�P�@�����̏�̑��l��
�@�@�Q�@�`�[�����
�@�a�@�Ō슈���̏��
�@�@�P�@�Ō슈���ɂ�������̓���
�@�@�Q�@���ƃA�Z�X�����g
�@�@�R�@�d�q�J���e�ƌl���̕ی�
�@�b�@�Ō슈���̋L�^�Ə�p
�@�@�P�@�Ō슈���̋L�^
�@�@�Q�@�Ō���̊��p
�B���e�N�m���W�[�ƊŌ�
�@�`�@�����ICT
�@�a�@ICT�Ɖ��u�Ō�
�@�@�P�@���u�Ō�Ƃ�
�@�@�Q�@���u�Ō�̋�̗�
�@�@�R�@���u��ÁC���u�Ō���\�ɂ��邽�߂�
�@�b�@��ƊŌ�̖���
�C���N���ƃw���X���e���V�[
�@�`�@�w���X���e���V�[�̒�`
�@�a�@�w���X���e���V�[��2�̏��
�@�@�P�@�w���X�P�A�̏��
�@�@�Q�@�w���X�v�����[�V�����̏��
�@�b�@�w���X���e���V�[�̕]���Ɨv��
�@�@�P�@�w���X���e���V�[�Ɋւ��钲���̊T�v
�@�@�Q�@�u�]���v�ɂ���
�@�@�R�@�u�ӎv����v�ɂ���
�@�c�@�w���X���e���V�[�ɕK�v�ȏ��̕]���ƈӎv����̃X�L��
�V �Ō슈���̑O��ƂȂ�Z�p
�@�Ō�ɂ�����l�ԊW�ƃR�~���j�P�[�V����
�@�`�@�Ō�Ɛl�ԊW
�@�@�P�@�l�ԊW�̃v���Z�X�̂����ɐ�������Ō�
�@�@�Q�@����-�Ō�ҊԂ̉����I�l�ԊW
�@�@�R�@�l�ԊW�W�����邽�߂̎��ȗ����E���җ���
�@�a�@�R�~���j�P�[�V�����̊�b�m��
�@�@�P�@�R�~���j�P�[�V�����̕���
�@�@�Q�@�R�~���j�P�[�V�����̍\���v�f�Ɛ����ߒ�
�@�@�R�@����I�E��I�R�~���j�P�[�V����
�@�@�S�@�Ō�ɂ�����R�~���j�P�[�V�����̓���
�@�@�T�@�R�~���j�P�[�V�����ɉe��������q
�@�b�@�����I�R�~���j�P�[�V�����X�L��
�@�@�P�@�ΐl�W�W������R�~���j�P�[�V�����̐S����
�@�@�Q�@�����I�R�~���j�P�[�V�����̊�{
�@�@�R�@���ÓI�R�~���j�P�[�V����
�@�c�@��Ã`�[���̃R�~���j�P�[�V����
�@▶�R����▶�O���[�v�E�_�C�i�~�b�N�X
�@�d�@�@���p�����R�~���j�P�[�V����
�@�@�P�@�d�b��i�[�X�R�[���̖����Ɨ��ӓ_
�@�@�Q�@�g��E��փR�~���j�P�[�V�����Ɨ��ӓ_
�@�@�R�@�r�f�I�ʘb�E���{�b�g���p
�A�����Ō�
�@�`�@�����̊�b�m��
�@�a�@�����ǂ̐���
�@�@�P�@�a���̂̐N��
�@�@�Q�@�����ǂƐ��̖h��@�\
�@�@�R�@�Պ����h��ƊŌ�
�@�b�@�����\�h�̂��߂̊Ō�Z�p
�@�@�P�@�a���̂���������
�@�@�Q�@�a���̂̐N���o�H���Ւf����
�@�c�@��Ê֘A�����ƐE�Ɗ���
�@�@�P�@��Ê֘A�����Ɗ����Ǘ�
�@�@�Q�@�E�Ɗ����h�~�ƈ��S�Ǘ�
�B�Ō쓮��ƃ{�f�B���J�j�N�X
�@�`�@�{�f�B���J�j�N�X
�@�@�P�@�{�f�B���J�j�N�X�Ƃ�
�@�@�Q�@�{�f�B���J�j�N�X�Ɛl�ԍH�w
�@�@�R�@�{�f�B���J�j�N�X�̌��E
�@�@�S�@�l�Ԃ̍\���I�E�@�\�I�ȃ{�f�B���J�j�N�X
�@�@�T�@�l�Ԃ̎p���iposture of human�j
�@�@�U�@��ƓI�ȃ{�f�B���J�j�N�X
�@�@�V�@�͊w����݂�����̊�{
�@�a�@�Ō쓮��ɂ�����{�f�B���J�j�N�X
�@�@�P�@�Ō쓮��
�@�@�Q�@���҂╨�̈ړ�
�@�@�R�@���E�p��̊��p
�@�@�S�@���҂ւ̓K��
�C����S�i���X�N�}�l�W�����g�j
�@�`�@To Err is Human
�@�@�P�@����S
�@�@�Q�@�q���[�}���G���[
�@�@�R�@��Î��̂̌���ƕ���
�@�a�@��È��S�Ǘ��ɂ�����q���[�}���G���[��
�@�@�P�@��p�I�G���[��
�@�@�Q�@���W���G���X�E�G���W�j�A�����O
�@�@�R�@��È��S�ɂ�����Q�[�~���O�V�~�����[�V�����̊��p
�W �w���X�A�Z�X�����g
�@�g�̓I���N��Ԃ̃A�Z�X�����g
�@�`�@�w���X�A�Z�X�����g�Ƃ�
�@�a�@�t�B�W�J���A�Z�X�����g�̕��@
�@�@�P�@�̕\���猩���q�g�̂��炾���ώ@����
�@�@�Q�@�o�C�^���T�C���ɂ��A�Z�X�����g
�@▶�R����▶ ������g�����̉��v�E�����v�̑S�p��
�@�@�R�@�����p�߂ƍb��B�̐G�f
�@�@�S�@���o��n�̃A�Z�X�����g
�@�@�T�@�]�E�_�o�n�̃A�Z�X�����g
�A�S����ԂƎЉ�̃A�Z�X�����g
�@�`�@�l�̍l���E�C�����𗝉�������@
�@�a�@�l�̕�炵�Ԃ�𗝉�������@
�B�Z���t�P�A�\��
�@�`�@�Z���t�P�A�ƃZ���t�P�A�\��
�@�a�@�Z���t�P�A�\�͂̃A�Z�X�����g
�X ���퐶���̉���
�@�����̏�𐮂���
�@1-1�@���N�����Ƌ��Z��
�@�`�@���N�����̂��߂̊������̎��_
�@�@�P�@���I��
�@�@�Q�@�ΐl�I��
�@�@�R�@����E�Ǘ��I��
�@�a�@�����̏�ɉ��������Z���̎��_
�@�@�P�@��ʕa��
�@�@�Q�@�×{�a��
�@1-2�@���������邳�ƐF��
�@�`�@���Ɛ���
�@�@�P�@���z�Ɛ������Y��
�@�@�Q�@�قȂ�g�������l�̂ɗ^����e��
�@�@�R�@������Ԃɗp������F
�@�a�@���邳�ƐF��
�@�@�P�@���邳�̑���
�@�@�Q�@�F�̑���
�@�b�@�����ɓK��������
�@�@�P�@������߂����邳�̊
�@�@�Q�@���ÂƐF���x��
�@�@�R�@�G�ߕω�
�@�@�S�@���@��
�@1-3�@��C�ƏL����
�@�`�@���퐶���ɂ�����L��
�@�@�P�@���N�Ȑl���甭������L��
�@�a�@�a�@���ɂ�����L��
�@�@�P�@�����q�ɂ�����
�@�@�Q�@���Ҏ��g���甭���������
�@�b�@���@�L
�@�c�@���ÁE�Ǐ�ɘa��ړI�Ƃ�������
�@�@�P�@�g�̂ւ̍�p
�@�@�Q�@���_�S���ʂւ̍�p
�@1-4�@���Z��ԂƉ���
�@�`�@���̕����I����
�@�a�@�a�@�̏W�����Î��ł̉��̖��
�@�b�@���ƂȂ鉹�ւ̑Ώ����@
�@1-5�@�Q���� �r�c���b
�@�`�@�����̏�Ƃ��Ă̐Q��
�@�a�@�Q�����C��
�@�@�P�@�Q�����C��Ƃ�
�@�@�Q�@�Q�����C��̕ϓ��v��
�@�b�@���K�ȐQ�������
�@�@�P�@�Q�����ӂ̊�����
�@�@�Q�@�x�b�h���[�L���O�̕��@
�@1-6�@�߁@��
�@�`�@���N�҂̓���ɂ�����ߕ��̖���
�@�a�@���N��Q�̂���l�̈ߕ�
�@�b�@�a�ҁE���㐶���҂ɂƂ��Ă̐Q��
�@�c�@�Տ��ɂ�����Q�ߌ����̕��@
�A�����I�j�[�h���[����
�@2-1�@�H�ׂ�
�@�`�@�h�{�̊�b�m��
�@�@�P�@�Ō�ɂ�����h�{�̈Ӌ`
�@�@�Q�@���{�l�̐H���ێ�
�@�@�R�@�����Ƌz��
�@�a�@����l�̐H�̓���
�@�@�P�@�h�{�ێ��
�@�@�Q�@�H�K��
�@�@�R�@�H�s��
�@�b�@�H�������̂��߂̊Ō�Z�p
�@1�@�a�@�H
�@2�@������H�ׂ邱�Ƃ���������
�@3�@�o���ȊO�̉h�{�⋋���@����������
�@2-2�@�ċz����
�@�`�@�ċz�̊�b�m��
�@�@�P�@�ċz��n�̌`�ԂƋ@�\
�@�@�Q�@�ċz�^���ƌċz����
�@�a�@�ċz�̃A�Z�X�����g
�@�@�P�@�ċz�̐���
�@�@�Q�@�ċz��ɓ����I�ȏǏ�
�@�@�R�@�������_�f�O�a�x�C���t�����Ȃǂ̃f�[�^
�@�b�@�ċz�����y�ɂ���Ō�Z�p
�@�@�P�@���y�ȑ̈�
�@�@�Q�@�ċz�P��
�@�@�R�@�r႖@
�@�@�S�@�z���Ö@
�@�@�T�@�z���Ö@
�@�@�U�@�_�f�Ö@
�@�@�V�@�P�A�̕]��
�@2-3�@�r������
�@2-3-1�@�r�@�A
�@�`�@�r�A�̃��J�j�Y��
�@�a�@�r�A�ɉe������v��
�@�b�@�r�A�Ɋւ���A�Z�X�����g
�@�@�P�@��ϓI���
�@�@�Q�@�q�ϓI���
�@�c�@�r�A�̉����ɂ������Ō�Z�p
�@�@�P�@���R�r�A�𑣂��Ō�Z�p
�@�@�Q�@�~�i���j�A��Q�ɑ���Ō�Z�p
�@�@�R�@�r�o��Q�ɑ���Ō�Z�p�\���A
�@2-3-2�@�r�@��
�@�`�@�r�ւ̈Ӌ`�ƃ��J�j�Y��
�@�@�P�@�l�Ԃ̌��N�Ɣr��
�@�@�Q�@�r�ւ̃��J�j�Y��
�@�@�R�@�r�ւɉe�����y�ڂ����q
�@�a�@���K�Ȕr�ւ𑣂�����
�@�@�P�@�r�ւ̃A�Z�X�����g
�@�@�Q�@���R�r�ւ𑣂�����
�@�@�R�@����ł̔r�ւ̉���
�@�b�@�r�ւُ̈�ɑ��鉇��
�@�@�P�@�������̃P�A
�@�@�Q�@�r�֍���̃P�A
�@2-4�@������ۂ�
�@�`�@�g�̂𐴌��ɕۂ��Ƃ̈Ӌ`�ƊŌ�̖���
�@�@�P�@�����̈Ӌ`
�@�@�Q�@�畆�E�S���̍\���Ƌ@�\
�@�a�@�����̃j�[�h�̃A�Z�X�����g
�@�@�P�@�g�̏̃A�Z�X�����g
�@�@�Q�@�����s�ׁE�s���̃A�Z�X�����g
�@�b�@�����̉����Z�p
�@�@�P�@����Ɛ��܂̐�����
�@�@�Q�@�S�g���@�ƕ������@
�@�@�R�@��������уV�����[��
�@�@�S�@�A���̐���
�@�@�T�@������
�@�@�U�@��@��
�@�@�V�@���o�̐���
�@�@�W�@��E���E�@�̐���
�@2-5�@��������
�@�`�@�����E�^���Ɋւ����b�m��
�@�@�P�@�����E�^���̈Ӌ`
�@�@�Q�@�����E�^���̐g�̂ւ̉e��
�@�a�@�����E�^���@�\�̃A�Z�X�����g
�@�@�P�@�^���@�\�̕]��
�@�@�Q�@���퐶���s���̐��s�Ɋւ���Z���t�P�A�\��
�@�@�R�@�������Ƃ���ӎv
�@�@�S�@�����s�����x���鐶����
�@�@�T�@�����Ƌx���̃o�����X
�@�b�@�����𑣂�����
�@�@�P�@�̈ʕϊ��̉���
�@�@�Q�@�Ԉ֎q�ւ̈ڏ�E�ڑ��̉���
�@�c�@�×{�����ɂ����郌�N���G�[�V����
�@2-6�@�|�W�V���j���O
�@�`�@�|�W�V���j���O�Ƒ̈�
�@�a�@��{�I�ȑS�g�|�W�V����
�@�@�P�@��ʁilying position�j
�@�@�Q�@���ʁisitting position�j
�@�@�R�@���ʁistanding position�j
�@�b�@���퐶���ɕK�v�ȃ|�W�V���j���O
�@�@�P�@�̈ʕϊ��ƃ|�W�V���j���O
�@�@�Q�@�H���P�A�ƃ|�W�V���j���O
�@�@�R�@�r���P�A�ƃ|�W�V���j���O
�@�@�S�@�����P�A�ƃ|�W�V���j���O
�@2-7�@�����Ƌx��
�@�`�@�����E�x���̒�`�E�@�\�ƊŌ�҂̖���
�@�a�@�����̐����w�I��b�m��
�@�@�P�@�����̒��ߖ@
�@�@�Q�@�����i�K�Ǝ���
�@�b�@�����ɉe������v��
�@�c�@�Ǐ�̂Ƃ炦��
�@�d�@���悢�����ւ̊Ō쉇��
�@�@�P�@�A�Z�X�����g
�@�@�Q�@�Ō쉇���̎��ۂƂ��̍���
�@2-8�@�S�n�悳�ƊŌ�P�A
�@�`�@�u�S�n�悳�v�Ƃ�
�@�a�@�u�S�n�悢�v�Ɗ�����Ƃ��̐S�g�̃��J�j�Y��
�@�b�@�u�S�n�悳�v�������炷�Ō�P�A�̌���
�@�@�P�@�Ō�P�A�����l�̔���
�@�@�Q�@�Ō�t���Ƃ炦�銳�ҁE�Ƒ��̕ω��Ǝ������g�̕ω�
�Y �������i�ƏǏ�ɘa�̃P�A�Z�p
�@�����̕ی�
�@�`�@�����̕ی�ƕ�і@�̗��j
�@�a�@��і@�̊�b�m��
�@�@�P�@��т̖ړI
�@�b�@��і@�ɋ��ʂ�����{��̌���
�@�@�P�@�ړI�ɂ������ޗ�����@�ł���
�@�@�Q�@�z��Q��\�h����
�@�@�R�@�^����Q��\�h����
�@�@�S�@������\�h����
�@�@�T�@���y�ł���
�@�c�@��тƃh���b�V���O
�@�@�P�@��@��
�@�@�Q�@�h���b�V���O
�@�d�@�Ǐ�ɘa�Z�p�Ƃ��Ă̕�і@
�@�@�P�@����������тɂ��Ö��җ��̑��i
�@�@�Q�@�����x���Z�p�Ƃ��Ă̕�і@
�A�̉t�o�����X��ۂP�A
�@�`�@�̉t�ɂ��Ă̊�b�m��
�@�@�P�@�̉t�̋敪
�@�@�Q�@�̉t�̗ʁE���z
�@�@�R�@�̉t�̐���
�@�@�S�@�̉t�o�����X�i�����o�����X�Ƒ̉t�ʃo�����X�j
�@�a�@�̉t�o�����X�̗���
�@�@�P�@�E����
�@�@�Q�@���@��
�@�b�@�̉t�o�����X�̃A�Z�X�����g�w�W
�@�@�P�@���퐶���̒��Ŕ��f�ł���w�W
�@�@�Q�@��������
�@�@�R�@�f�@����
�@�c�@�̉t�o�����X�𐮂��邽�߂̃P�A
�@�@�P�@���퐶���ɂ�����P�A
�@�@�Q�@�A�t�̊Ǘ�
�B����̃P�A�i�p�胊���p�h���i�[�W�j
�@�`�@�����p����̊�b�m��
�@�@�P�@����̌����Ɣw�i
�@�@�Q�@�����p����̊ӕʂƃP�A�̏d�v��
�@�a�@�p�胊���p�h���i�[�W�iML�j�̎��ہi�Ō�҂��s�����́j
�@�@�P�@�����p�njn�̑��s
�@�@�Q�@ML�̎��{����
�@�@�R�@ML�̕��@
�C��ጂ̗\�h�P�A
�@�`�@��ጂ̒�`
�@�a�@��ጂ̏d�Ǔx���ނƏ�ԕ]��
�@�b�@�\�h�P�A�̊�{
�@�c�@�S�g�畆�ώ@
�@�d�@���X�N�A�Z�X�����g
�@�@�P�@�u���[�f���X�P�[��
�@�@�Q�@K���X�P�[��
�@�@�R�@�����J���� ��ጔ����댯���q�]���[
�@�e�@�����E����͂̊Ǘ�
�@�@�P�@�̈ʕϊ��E�|�W�V���j���O
�@�@�Q�@�̈����U�Q��̎g�p
�@�@�R�@���Ǘ���]������
�@�@�f�@�X�L���P�A
�@�@�P�@�畆�̐���
�@�@�Q�@�ہ@��
�@�@�R�@�}�b�T�[�W�̋֎~
�@�@�S�@�ցE�A���ւȂǂ̎�������̉��
�@�g�@�h�@�{
�D�X�g�[�}�P�A
�@�`�@�X�g�[�}�̎��
�@�a�@�X�g�[�}����
�@�@�P�@�X�g�[�}��
�@�@�Q�@�ʁ@��
�@�b�@�X�g�[�}�̊�{�I�ȃP�A
�@�@�P�@�X�g�[�}���ݑO�̃P�A
�@�@�Q�@�X�g�[�}����̃P�A
�@�c�@�X�g�[�}���͔畆��Q�̑��������Ƃ��̑Ή�
�E���y�E���J��ۂP�A
�@�`�@������Ɛg�̂̒��a��ۂ�
�@�@�P�@�����N�Z�[�V�����̊�b�m��
�@�@�Q�@�����N�Z�[�V�����̂��߂̊Ō�Z�p
�@�@�R�@�����N�Z�[�V�����@�̓K�p�ƌ���
�@�@�S�@�P�A�̃|�C���g�Ɨ��ӎ���
�@�a�@���M�E����h���ɂ����y�E���J�̑��i
�@�@�P�@���M�E����h���̊�b�m��
�@�@�Q�@���M�h���̈��y�E���J���i����
�@�@�R�@����h���̈��y���i����
�@�@�S�@���x�h���Ƃ��Ă�㪖@�̊��p
�@�@�T�@㪖@�̎�ނƎ���
�F���S�E�q�f�̃P�A
�@�`�@���S�E�q�f�̊�b�m��
�@�@�P�@���S�E�q�f�̒�`
�@�@�Q�@���S�E�q�f�̃��J�j�Y��
�@�a�@���S�E�q�f�̌���
�@�@�P�@�������q�f
�@�@�Q�@�������q�f
�@�b�@���S�E�q�f�̃P�A
�@�@�P�@�A�Z�X�����g
�@�@�Q�@���f���Âɔ����P�A
�@�@�R�@���S�E���y�ȑ̈�
�@�@�S�@�H���E�h�{��Ԃւ̔z��
�@�@�T�@���_�ʂ̃P�A
�G�r�֏�Q�̃P�A
�@�`�@��w���f���ɂ�����֔�
�@�@�P�@�f�f�E���Â�ړI�Ƃ����֔�̒�`
�@�@�Q�@���@��
�@�@�R�@�ւ̐���
�@�a�@�֎���
�@�@�P�@��@�`
�@�@�Q�@�u�@�w
�@�@�R�@�֎��ւ������炷���
�@�b�@�����������剷���p��ɐ�����r�֏�Q
�@�@�P�@��������̎�p
�@�@�Q�@��ʑO���؏��p��nj�Q�ɂ���
�@▶�R����▶�Տ����f
�H�ɂ݂̃P�A
�@�`�@�N�Q��e�Ƃ��Ă̒ɂ�
�@�a�@�̌��Ƃ��Ẵq�g�̒ɂ�
�@�b�@�ɂ݂̎�ނƓ���
�@�c�@�ɂ݂̑���E�]���̕��@
�@�@�P�@��@�f
�@�@�Q�@�t�B�W�J���A�Z�X�����g
�@�d�@���ɂ̃��J�j�Y��
�@�e�@���ɃP�A�̕��@
�@�f�@�֘A��
�I�����u�ɂ̃P�A
�@�`�@�����u�ɂɊւ���Ō�̎��H�͈�
�@�@�P�@�����u�ɂ��ɘa����Ō�t�̗ϗ��I�Ӗ�
�@�@�Q�@�Ō�̂��߂̂����u�ɂ̒m��
�@�@�R�@�I��
�@�@�S�@��I���
�@�a�@�����u�ɂ̃P�A
�@�@�P�@���҂̒ɂ݂𗝉�����
�@�@�Q�@�����u�ɂ̃}�l�W�����g�̂��߂Ɋ��҂Ǝ��͂��s���Ă�������𖾂炩�ɂ���
�@�@�R�@�ɂ݂��}�l�W�����g���銳�҂̃Z���t�P�A�\�͂����肷��
�@�@�S�@���҂̃Z���t�P�A�\�͂ɉ����ĕK�v�Ȓm���C�Z�p�C�T�|�[�g�����
�@�@�T�@�P�A�̌��ʂ�]�����C�C������
�@▶�R����▶�`�[�����
�J�^�b�`�̃P�A
�@�`�@�^�b�`�̊�b�m��
�@�@�P�@�^�b�`�̓`�B���J�j�Y��
�@�@�Q�@�Ō�t���s���^�b�`�̎��
�@�a�@�^�b�`�̃P�A
�@�@�P�@�^�b�`�̃v���Z�X�ƃA�Z�X�����g
�@�@�Q�@�^�b�`�̕��@�ƌ���
�K���o�ُ�̃P�A
�@�`�@���o�̊�b�m��
�@�@�P�@���o�̃��J�j�Y���Ɛ_�o�x�z
�@�@�Q�@���o�ɉe������v��
�@�a�@���o�ُ�
�@�@�P�@���o�ُ�Ƃ�
�@�@�Q�@���o�ُ�̌���
�@�@�R�@���a�E���ÂɊ֘A�������o�ُ�
�@�@�S�@���o�ُ�̃A�Z�X�����g
�@�b�@���o�ُ��\�h�E�ɘa����P�A
�L���o��Q�҂̃P�A�i���[�r�W�����P�A�j
�@�`�@���[�r�W�����P�A�̊�b�m��
�@�@�P�@���o��Q�҂̓���
�@�@�Q�@���o��Q�҂̗���
�@�a�@���o��Q�҂̃A�Z�X�����g
�@�@�P�@���@�\�̃A�Z�X�����g
�@�@�Q�@���퐶���〈�����̃A�Z�X�����g
�@�b�@���[�r�W�����P�A�̎��H
�@�@�P�@�ۗL���@�\�̈ێ�
�@�@�Q�@�Ԗ����̊g��
�@�@�R�@�O���A�̌y��
�@�@�S�@�R���g���X�g���x
�@�@�T�@�R�~���j�P�[�V�����\�͂̉��P
�@�@�U�@���s�i�ړ��j�̎x��
�@�@�V�@���퐶���s���̍H�v
�@�@�W�@��`�J�E���Z�����O
�@�@9�@���[�r�W�����҂̂�����̃P�A
�@�@10�@�ٗp�p���x��
�@�c�@���[�r�W�����P�A�̉ۑ�
�M�^�[�~�i���P�A
�@�`�@�^�[�~�i���P�A�̊�b�m��
�@�@�P�@�^�[�~�i���P�A�Ƃ�
�@�@�Q�@�I�����ɂ��銳�҂̗���
�@�a�@�I�������҂̐g�̓I��ɂ��ɘa����Z�p
�@�@�P�@���ӊ��Ƃ�
�@�@�Q�@���ӊ��̕a�Ԑ����ƃ��J�j�Y��
�@�@�R�@���ӊ��̊��o
�@�@�S�@���ӊ��̃A�Z�X�����g
�@�@�T�@���ӊ��̊ɘa�P�A�ipalliative care�j�̕��@
�@�b�@���_�I��ɂ��ɘa����Z�p
�@�@�P�@�s���Ƃ�
�@�@�Q�@�s���̐���
�@�@�R�@�s���̃T�C���ƂȂ锽��
�@�@�S�@�s���̃A�Z�X�����g
�@�@�T�@�s���𑪒肷��ړx�̊��p
�@�@�U�@�s���̂��銳�҂ւ̊Ō�P�A
�@�@�V�@�s���̂��銳�҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����Z�p
�Z �Ō�̋���I����
�@�Ō�̋���I����
�@�`�@�w�K�҂̈ˑ��x�ɉ����ċ���I����������K�v��
�@�a�@�m���E�Z�p��g�ɂ���x��������
�@�@�P�@�u�w���^�v����u�w�K�����^�v�ւ̈ӎ��̓]��
�@�@�Q�@�킩��₷��������
�@�@�R�@�Z���t�}�l�W�����g�ɕK�v�ȃe�[���[���C�h�̒m���E�Z�p��������
�@�b�@���Ȍ��͊������߂�
�@�c�@������G���p���[�����g����
�@�d�@���ȋ���͂�g�ɂ���x��������
�@�e�@�{�݂���ݑ�ւ̎x��
�@�@�P�@�n���P�A�V�X�e��
�@�@�Q�@��Î{�݊Ԃ̋@�\����
�@�@�R�@�a�@�̎�ނƌp���Ō�̕K�v��
�@�@�S�@�a�@�ɂ�����މ@�x���E�މ@����
�@�@�T�@���E��Ãj�[�Y�̍����ݑ�×{�҂ւ̊Ō�
�@�@�U�@�{�݂���ݑ�ւ̎x���ɕK�v�ȗv�f
�A�w���X�v�����[�V�����̊�{���O�ƕ���
�@�`�@WHO�̌��N�헪�Ƃ��Ẵw���X�v�����[�V����
�@�@�P�@�w���X�E�t�H�[�E�I�[��
�@�@�Q�@�A���}�E�A�^�錾�C�I�^������
�@�@�R�@���N�ɂ��������
�@�a�@�w���X�v�����[�V�����Ƃ�
�@�@�P�@�I�^�����͂���уo���R�N���͂ɂ���`
�@�@�Q�@���N�ɂ��Ă̍l�����ƃw���X�v�����[�V���������̊�b
�@�b�@�w���X�v�����[�V�����̃v���Z�X�헪
�@�@�P�@�I�^�����͂�3�̃v���Z�X�헪
�@�@�Q�@�o���R�N���͂�5�̃v���Z�X�헪
�@�c�@�w���X�v�����[�V�����̊����̕��@
�@�@�P�@���N�I�Ȍ�������Â���
�@�@�Q�@�l�̔\�́E�Z�p�̊J��
�@�@�R�@���N���x�����������
�@�@�S�@�n�抈���̋���
�@�@�T�@�ی��E��ÃT�[�r�X�̕����]��
�@�d�@�w���X�v�����[�V�����̊T�O�}
�@�e�@���{�̃w���X�v�����[�V�����ƌ��N����
�@�@�P�@���N���{21
�@�@�Q�@���茒�N�f���E����ی��w��
�@�f�@�w���X�v�����[�V�����̗L����
�[ �f�Â̕⏕
�@�Ö@�̊Ǘ�
�@�`�@�Ō�t����ɂ��ė�������K�v��
�@�a�@�Ō�t���s���^��E�Ǘ��Ƃ�
�@�b�@�^��E�Ǘ��̒m���E�Z�p
�@�@�P�@���i�Ƃ�
�@�@�Q�@��̐��������
�@�@�R�@��̎�舵���i�ۊǂƊǗ��j
�@�c�@�����d�g��
�@�@�P�@���^���@
�@�@�Q�@�̓��ɂ������̓���
�@�@�R�@�Ō�t�̖Ö@���̊ώ@�|�C���g
�A���@��
�@�`�@�Ö@�ɂ����钍�˂̈Ӌ`�ƊŌ�̖���
�@�@�P�@���˂̓���
�@�@�Q�@���˂ɂ�����Ō�̖���
�@�a�@���ˎ��{�O�̃A�Z�X�����g
�@�@�P�@����E�A�����M�[�C������
�@�@�Q�@�t�B�W�J���A�Z�X�����g�iphysical assesment�j
�@�b�@���˂̕��@
�@�@�P�@���ˊ��̑I��
�@�@�Q�@���˖@�ɋ��ʂ���菇�Ɨ��ӓ_
�@�@�R�@�e���˖@�̎菇�Ɨ��ӓ_
�B�A�@��
�@�`�@�A���Ƃ�
�@�@�P�@�A���̖ړI
�@�@�Q�@�A���̎��
�@�a�@�A�����̃C���t�H�[���h�E�R���Z���g�Ǝ��Ȍ��茠
�@�b�@�����ƗA���̎��{
�@�@�P�@�A���̌���
�@�@�Q�@���S�ɔz�������m���ȗA���̎��{���@�Ɨ��ӎ���
�@�@�R�@�A���ɔ�������p�Ɨ\�h�E�Ώ�
�C�����⏕
�@�`�@�����ɂ�����Ō�t�̖���
�@�@�P�@�����̖ړI�ƕK�v��
�@�@�Q�@�����ɂ�����Ō�̎���
�@�a�@���̌����ɂ�����P�A
�@�@�P�@���t����
�@�@�Q�@��ʌ���
�@�@�R�@�����ǁi�ہE�E�C���X�j����
�@�@�S�@�a������
�@�b�@�����@�\�����ɂ�����P�A
�@�@�P�@�z�@�\����
�@�@�Q�@�ċz�@�\����
�@�@�R�@�_�o�E�؋@�\����
�@�c�@�摜�����ɂ�����P�A
�@�@�P�@���ː��Ɋւ����b�m��
�@�@�Q�@�e��摜�����ƃP�A
�@�d�@�����������ɂ�����P�A
�@�@�P�@�㕔�����Ǔ����������i�H���E�݁E�\��w���j
�@�@�Q�@���������Ǔ����������i�咰�j
�@▶�R����▶�o�C�I�}�[�J�[
�D�O���Ō�̖���
�@�`�@�O���̓���
�@�a�@�O���ɂ�����Ō�̋@�\�Ɩ���
�@�b�@�O���ɂ�����Ɩ��̎���
�@�@�P�@�Ǘ��Ɩ�
�@�@�Q�@�f�Â̕⏕�Ɩ�
�@�@�R�@���Ҏw���E����
�@�@�S�@���@�k
�@�c�@�O���Ō�t�ɋ��߂���\��
�@�@�P�@�R�~���j�P�[�V�����\��
�@�@�Q�@�N���j�J���E�W���b�W�����g�iclinical judgment�j�\��
�@�@�R�@�����\��
�@�d�@�O���Ō�̐�剻
�@�@�P�@��剻�̐i�W
�@�@�Q�@�O�����w�Ö@
�E�S�x�h���Ǝ~���@
�@�`�@�S�x�h���̊�b�m��
�@�@�P�@�S��~
�@�@�Q�@�v���Ȉ�A�̋~�����u�ߒ�
�@�@�R�@�ꎟ�~�����u
�@�a�@�~���@
�@�@�P�@�ꎞ�I�~���@�̎��{
�@�@�Q�@�~���@���{���̒��ӓ_
�@�b�@�S�x�h���ɂ����銴���Ǘ\�h��
�\ �Ō쌻�ۂ̑���Z�p
�@�]����-1�@�]�g
�@�@�P�@�]�g�Ƃ�
�@�@�Q�@������@�ƕ]��
�@�@�R�@�Ō�w�����̉��p��
�A�]����-2�@fMRI
�@�@�P�@fMRI�Ƃ�
�@�@�Q�@������@�ƕ]��
�@�@�R�@�Ō�w�����ւ̉��p
�B���̃��Y��
�@�@�P�@���̃��Y���Ƃ�
�@�@�Q�@������@�ƕ]��
�@�@�R�@�Ō�w�����ւ̉��p
�C�������̓���
�@�@�P�@�������̓���Ƃ�
�@�@�Q�@����������̕��@�Ɖ��
�@�@�R�@�Ō�w�����ւ̉��p
�D�S���ϓ�
�@�@�P�@�S���ϓ��Ƃ��̑���̈Ӌ`
�@�@�Q�@�S�d�}R-R�Ԋu�ϓ��W���iCVR-R�CCV�j
�@�@�R�@�S�d�}R-R�Ԋu�ϓ��W���̃X�y�N�g����͂ƊŌ�w�����ւ̉��p
�E�ċz���脟�̈ʂɂ��ω�
�@�@�P�@�ċz�@�\�̑�����@
�@�@�Q�@�ċz����Z�@��p����������
�F���̔����̑g�D�w�I�]��
�@�@�P�@�g�D�w�̓_�H�R��P�A�ւ̉��p
�@�@�Q�@������@�ƕ]��
�@�@�R�@�Ō�w�����ւ̉��p
�G��`�q�Ƃ��̔����̉��
�@�@�P�@��`�q�Ƃ�
�@▶�R����▶��`�q�g����
�@▶�R����▶�E�C���X�x�N�^�[
�@�@�Q�@��`�q���������̊Ō�w�����ւ̉��p
�@�@�R�@������̒��ӓ_
�@▶�R����▶PCR����
�H�a��������
�@�@�P�@�a�����Ƃ�
�@�@�Q�@�a�����̑�����@�ƕ]��
�@�@�R�@�Ō�w�����ւ̉��p
�I�����v�����Ō�҂̊ώ@��̉�
�@�@�P�@�����v���i�A�C�g���b�L���O�j�Ƃ�
�@�@�Q�@�����v���@��ɂ���
�@�@�R�@��ȑ��荀��
�@�@�S�@����菇
�@�@�T�@�Ō�w�����ւ̉��p
�J�ɂ݂̑���
�@�@�P�@�ɂ݂Ƃ�
�@�@�Q�@������@�ƕ]��
�@�@�R�@�Ō�w�����ւ̉��p
�t�@�^
�@�@�P�@�߉���\���Ȃ�тɑ���@�i2022�N4�������j
�@�@�Q�@�����֔�ǂ̕���
�y��3�ł̏��z
�@�Ǐ��͔ł��d�˂�ƕ����܂��D�{���͏��Ŕ��s�i2006 �N5 ���j����8 �N���C������2 �Ŕ��s�i2015 �N1 ���j����9 �N���o�āC���̂قǁu��b�Ō�w�e�L�X�g ������3 �Łv�̔��s�ɑ��������܂������Ƃ��C�ҎҁE���M�҂Ƃ��ǂ���ϊ������v���܂��D10 �N�Ԏx������闝�_�͓��ʂ̐^���Ƃ�����悤�ɁC�����̊Ԋu�͑Ó��ł��낤�Ǝv������ł��D
�@���ł̏��ɋL���܂����悤�ɁC�{���͊�b�Ō�w�̋��ȏ����Ō�Z�p�̃}�j���A���{�łȂ��C�����f�[�^�Ɋ�Â������������Ȃ���X�̃P�A�̕��@�Ǝ菇���������Ȋw�̃e�L�X�g�ɂ������Ƃ����z������a�����܂����D�{���͂قڂ��ׂĂ̒P���ɊŌ�Z�p�̍����Ƃ��Ă̌����f�[�^�������}�\���ڂ����C�����炭�͂킪�����̊Ō�w�̋��ȏ��ł������Ǝv���܂��D�Ō�w�̋��ȏ��ɂ͑̌n���Ȃ��C������V���[�Y�{���������ŁC�{���͊����Ċ�b�Ō�w�ɓ��������P�̂̃e�L�X�g�Ƃ��Ċ��s���܂����D���̗��R�́C�Ō�w�̋}���Ȑi�������������C�����Ē��J�ɔ��f�����Ȃ���C�A�b�v�f�[�g�����Ȋw�Ƃ��Ă̊Ō�w�̑S�̂��C���w�҂���őO���̊Ō���H�҂Ɏ������߂ł�����܂��D
�@1990 �N�㔼�̊�b����̑�w������ɁC���{�̊Ō�w�͊w��Ƃ��ċ}���ɐi�����܂����D����Ō�w�n�̊w���E�w�Ȃ��܂ޑ�w�̐��͍����ōő��ƂȂ�܂����D��30�N�O�ɂ͑�w��11 �Z�����Ȃ��������Ƃ�N���M����ł��傤�D����ɔ�����w�@�����X�Ɛݒu����C�w�p�c�̂̐��������Ă����܂����D�����_�����p���Ŕ��\���邱�Ƃ��Ō�w�E�ł��悤�₭�펯�ƂȂ����܂��D���R�Ȃ���C�Ō�w�̐i���͊Ō���H�̏�Ƀv���ӎ��Ɗ��͂��������Ă����܂����D���������͂��������{�����]�݁C�ڎw���Ƃ���ł����D
�@���āC2019 �N���ɓ˔@�Ƃ��ďo�����C�u���Ԃɐ��E�������P����COVID︲19 �p���f�~�b�N�́C����Љ�Ƀp���_�C���V�t�g�����v���܂����DIT ���EICT �����x��Ă����킪���̋��猻��ł́C�����\�h�Ɖ��u������E�[�������邽�߂̃C���t���J���ƍs���}�j���A����肪�҃X�s�[�h�Ői�߂��܂����D3 �N���܂葱�����R���i�Ђ�U��Ԃ�ƁC��������邽�߂ɕ������i�w���⋳�t�́j�]���̑傫�����v���N������܂��D�R���i�Ђ��_�@�ɐi���̃X�s�[�h�𑝂����ߖ�����IT ���EICT ���Љ�i�j���[�m�[�}������j�ł́C�ǂ̂悤�ȊŌ�w���炪���߂���ł��傤���D�X�}�[�g���ɂ���ăo�C�^���T�C���̊ώ@���Ō�Z�p����폜���ꂽ��C�e�[���[���C�h�́i�ɂ��Ȃ��E���y�ȁj�Ō�p�3D �v�����^�[�ŊȒP�ɍ�ꂽ��C�A�o�^�[���g�����K��Ō삪������O�ɂȂ鎞�オ����̂͂��������Ȃ��ł��傤�D�����C�Љ�ǂ̂悤�ɐi���E�ω����悤�Ƃ��C�s�ςł���̂͊Ō삪�ΐl�Ԃ̐��Z�p�ł���Ƃ������Ƃł��D�l�̊��o�⊴����C���@�I�ȋ@�B�����䂷�鎞��͂܂��܂���̂悤�ȋC�����܂��D�{�����ڏq����Ō���H�̍�����Z�p���_���ÓT�Ƃ��Ď�����̊Ō�i�w�j�́C�����Ă��ׂĂ̊Ō�҂̋��菊�̂ЂƂƂȂ邱�Ƃ��肢�܂��D
�@�Ō�ɂȂ�܂������C���s�ɂ������ς����b������������]�������ɐS�����\���グ�܂��D
2023 �N11 ��
�Ҏ҂��\����
�[����q
�y���ł̏��z
�@�{���̂悤�ȊŌ�̋�����v���n�܂���10 ���N���o�߂��C����Ō��ڎw���������͋ߗׂ̒n��ł���]�Z��I�ׂ鎞��ɂȂ�܂����D�����āC�Ō�w�n��w�@���[��������C�C�m���E���m�����������Ō�҂�����E�����̏�͂������C���H�̍őO���ɂ����Ă���������悤�ɂȂ�܂����D����ɁC���Đ�i���̊Ō�̎��i���E���E���̉e�����C�킪���ł��Ō싦��ɂ�鋳��Ǝ��i�F�萧�x���������C�F��Ō�t����Ō�t���a�����āC���H�⌤���̏�ł��̍�����含�����͂��߂܂����D����C������������̗���̒��ŁC�Ō�w�n�̊w����X�ƒa�����C�p�������܂ފŌ�n�W���[�i���̐��������Ă��܂����D1986 �N�ɏ��߂ĊŌ�w�̔���@���C�w�������Ǝ��H���o�����C�Ō�w�̋���ƌ����Ɍg���悤�ɂȂ����Ҏҁi�[��j�́C�}�炸���Ō�w�̕ϊv�̎���ɊŌ�҂Ƃ��Ă�identity ����݂܂����D�������C����͈��̐_�o�����w�҂��Ō쐶���w�҂ɕϐg���邽�߂ɂ͑�ύD�s���Ȋ��ł������̂�������܂���D�܂��C�Ō�w����o�����C��U�w�E�Ɖu�w���C�߂Ȃ���Ō�w�҂ł���Â����Ҏҁi�O�c�j�ɂƂ��āC�Ō�w�̖]�܂����i���ł������悤�ɂ��v���܂��D
�@�m���ɂ��̕ϊv�͊Ō�ɂƂ��ĉ���I�Ȑi���ł�������������܂��C����O�̐��E���猩��C���͊Ō�w�͂����ɂ������Ă悤�₭�w��iphilosophy�j�̒��ԓ���������ꂽ�Ƃ�������̂ł��D�w�₪�����̐ςݏd�˂ɂ�闝�_�̌n�ł���Ȃ�C�Ō�w���\������{�i�I�ȗ��_�\�z�̍�Ƃ��n�܂����ɉ߂��Ȃ�����ł��D�Љ�Ɋw���̏���Ō�w�ɂ́C���ꂩ��w��Ƃ��Ă̌��r��ς݁C�Ō�w�̑�n�����肠����`�����ۂ����Ă��܂��D
�@�������N���C�Ō�E��Evidence-Based Nursing�iEBN�j�i�Ȋw�I�����Ɋ�Â����Ō삠�邢�͊Ō���H�j���ӎ�����悤�ɂȂ�܂����DEBN ��EBM�iEvidence-Based Medicine�j����h�������T�O�ł����C�傫�Ȍo�ό��ʂ����҂���EBM �Ƃ͈قȂ�CEBN �́C�o�������łȂ������f�[�^�Ɋ�Â������H��Nj����邱�ƂŃP�A�̎������コ���邽�߂̃L�[���[�h�ƂƂ炦���Ă��܂��DEBN �ɕK�v�ȃG�r�f���X�͌����i�Ƃ��Ɏ��H�����j�ɂ���Ă����炳���킯�ł�����C�Ō�ƊŌ�w�Ɍg���҂͂��̍D�@�����āC���H�ɍ��������n���Ȍ����ɗ�܂Ȃ���Ȃ�܂���D���̂悤�ȊŌ�E�̓����̒��ŁC�������p�ŃP�A�̎��̌����ڎw���Ō���H�C�Z�p�̏K���ƂƂ���EBN �u����g�ɂ���Ō�w����C���H�̏ꂪ���߂�G�r�f���X��T������Ō�w�����C�����͋��ʂ̖ڕW�Ɍ������Č݂��Ɍq�����ۂ��Ȃ���m���ȑO�i���n�߂悤�Ƃ��Ă��܂��D
�@�{���́C�V����̊Ō�̎�����ڎw���Ō�w����E�����҂̌��W�ɂ���Đ��܂ꂽ��b�Ō�w�̊�]�̋��ȏ��ł���ƂƂ��ɁC�Ō���H�҂ɑ��ẮC����Ō�w�����������Ƃ���������A�s�[�����Ă��܂��D���Ƃ��C�{���ł́C�Ō�Z�p�̕��@���\�Ȃ����茤���f�[�^�Ő������悤�Ɠw�߂܂����D�����āC�����ȋ^��ɂ܂������ƂȂ��ǂݐi�߂���悤�C�����̒��߂����܂����D�܂��C���������܂��ߒ����������K�Ŋw�Ԏ��݂��Љ�܂����D����ɁC�{���̎o���{�Ƃ�������w�Ō쐶���w�e�L�X�g�x�i��]���j�Ɠ��l�C�d�v�p����p�ꕹ�L���C�p��������݂��܂����D���̂悤�ɁC�{���ɂ́C����̗v���ɉ�����C�V�����Ō�w�̍\�z�ɒ��킷��Ō�҂����̑z���̏䂪���J�ɋl�߂��Ă��܂��D
�@�{���̎咣���C�Ō�ƊŌ�w�̐i�����肢�CEvidence-Based Nursing ��ڎw�����ׂĂ̊Ō�҂Ɏ�����邱�Ƃ���]���܂��D�Ō�w���w�Ԋw�����N�͌����ɋy���C�Ō���H�̍őO���Ŋ�������Ō�҂̕��X�ɂ��傢�ɂ����p���������邱�Ƃ�ؖ]���܂��D�܂��C�{����challenging �Ȏp���ɑ��邲�ӌ��C�����z�Ȃǂ����������܂�����K�r�ł��D
�@�Ō�ɂȂ�܂������C�{���̊�悩�犮���܂ł̖�3 �N�ԁC�h���������s�͂�����������]���̏����ɐ[�����ӂ������܂��D
2006 �N3 ��6 ��
�Ҏ҂��\����
�[����q

![������� ��]�� / NANKODO](/img/usr/common/logo.gif)

