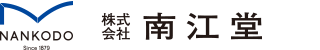日本整形外科学会診療ガイドライン
頚椎症性脊髄症診療ガイドライン2015改訂第2版
[CD-ROM付]
こちらの商品は改訂版・新版がございます。
| 監修 | : 日本整形外科学会,日本脊椎脊髄病学会 |
|---|---|
| 編集 | : 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会,頚椎症性脊髄症診療ガイドライン策定委員会 |
| ISBN | : 978-4-524-26771-2 |
| 発行年月 | : 2015年4月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 116 |
在庫
定価3,300円(本体3,000円 + 税)
正誤表
-
2015年12月09日
第1刷
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

しびれや麻痺を呈する頚椎症性脊髄症について、疫学・自然経過から診断、各種治療法の成績、予後にいたるまで34のクリニカルクエスチョンを設け、新たなエビデンスを加えて推奨gradeを定めた。整形外科医をはじめ運動器診療に携わる医療職にとっての必携書。付録のCD-ROMに文献アブストラクトを収載。
前文
1 目的
2 頚椎症性脊髄症の概念
3 改訂版の文献検索および選択の方法
4 クリニカルクエスチョンと推奨Grade
5 まとめ
第1章 疫学・自然経過
CQ1.頚椎症性脊髄症の疫学は明らかであるか
CQ2.頚椎症性脊髄症の自然経過は進行性に悪化するか
CQ3.頚椎症性脊髄症は生命予後に関係するか
第2章 病態
CQ1.頚椎症性脊髄症の発症に脊柱管狭窄は関与するか
CQ2.頚椎症性脊髄症の発症に動的因子(不安定性)は関与するか
CQ3.高齢者の頚椎症性脊髄症にみられる臨床的な特徴はあるか
第3章 診断
CQ1.頚椎症性脊髄症の臨床症状に特徴はあるか
CQ2.神経学的所見から頚椎症性脊髄症の高位診断は可能か
CQ3.頚椎症性脊髄症の重症度を表す評価法はあるか
CQ4.頚椎症性脊髄症の単純X線像に特徴はあるか
CQ5.頚椎症性脊髄症のMRIに特徴はあるか
CQ6.脊髄造影検査は頚椎症性脊髄症の診断に有用か
CQ7.電気生理学的検査は頚椎症性脊髄症の診断ならびに脊髄機能評価に有用か
CQ8.頚椎症性脊髄症と鑑別すべき疾患とその鑑別点はあるか
CQ9.腰部脊柱管狭窄症との合併例の臨床症状に特徴はあるか
第4章 治療
CQ1.各種保存療法は有効な治療法であるか
CQ2.代替医療(鍼、灸、マッサージ、整体、カイロプラクティック)は有効か
CQ3.保存療法に合併症はあるか
CQ4.手術療法の適応は明らかか
CQ5.前方法(前方除圧固定術)か後方法(椎弓形成術)かの選択基準は明らかか
CQ6.各種前方法の選択基準は明らかか
CQ7.各種後方法の間に成績の差はあるか
CQ8.前方除圧固定術の合併症として注意すべきものはあるか
CQ9.後方法の合併症として注意すべきものはあるか
CQ10.前方除圧固定術の長期手術成績は安定しているか
CQ11.後方除圧法の長期成績は安定しているか
第5章 予後
CQ1.自然経過例と保存療法例の予後に差があるか
CQ2.保存療法と手術療法の予後に差があるか
CQ3.術前の症状で予後(手術効果)を予測できるか
CQ4.術前の画像所見で予後(手術効果)を予測できるか
CQ5.術前または術中の電気生理学的検査で予後(手術効果)を予測できるか
CQ6.前方法と後方法の予後(中長期成績)に影響する因子はあるか
CQ7.手術療法の後療法で予後が変わるか
CQ8.手術療法後に頚椎の可動域はどうなるか
第6章 今後の課題
1 疫学・自然経過
2 病態
3 診断
4 治療
5 予後
索引
2015(第2版)の序
「頚椎症性脊髄症診療ガイドライン」(初版)は2005年に里見和彦先生(責任者)のもとで刊行された。初版刊行時5年後に改訂を行う予定で、日本整形外科学会診療ガイドライン委員会のもとに頚椎症性脊髄症診療ガイドライン改訂委員会が2008年に組織された。この改訂第2版が出来上がるまでに7年の時間を要したが、この間に一般向けの頚椎症性脊髄症ガイドブックを作成し、啓発に努めた。改訂委員会の組織は、初版のメンバーから市村正一先生がアドバイザーとして参加し、一般向けガイドブックから私が引き続き担当し、さらに本疾患に精通した新たな委員に加わって頂き改訂作業を行ってきた。
原則としてクリニカルクエスチョン(リサーチクエスチョンより変更)は初版を継承することとしたが、初版刊行から5年間に出た新しい知見のあるものを加えた。また本疾患に関する論文は、この期間もエビデンスレベルの高い論文はなかったが、エビデンスレベルの分類は初版のまま変更しなかった。しかし、推奨Gradeに関しては初版ではGrade I、すなわち「委員会の審査基準を満たすエビデンスがない、あるいは複数のエビデンスがあるが結論が一様ではない」といった不適当な評価が多くなってしまったことを反省し、改訂版では新しい知見が加わった場合、あるいは各担当委員が過去の論文も参考に推奨Gradeを変えるべきと判断し、委員会で討議し適切とした場合には推奨Gradeを変更し、その解説を加えた。そのためエビデンスレベルと推奨Gradeによる評価ではなく委員会としてのエキスパートオピニオンが優先され、推奨Gradeが変更されている項目があることをご了承頂きたい。これにより初版よりもより推奨Gradeの高い評価と回答がなされたものと考える。
今回の改訂作業において、日本医学図書館協会からの依頼により、東京女子医科大学図書館司書の三浦裕子氏に2004.2009年末までの論文から頚椎症性脊髄症の疫学・病因、診断、治療、予後に関する必要な論文を検出して頂いた。また東京女子医科大学整形外科教室秘書の石塚千亜季氏にもご協力頂いた。その後、各委員と査読協力者の先生方には膨大な論文から、一次検索、論文査読、構造化抄録の作成などの作業を行って頂き、さらにそれぞれのパートでの推奨Gradeの決定、解説文の作成など多くの時間と労力を注いで頂き、この改訂版が完成するに至った。このような作業にご尽力頂いた委員の先生方には心より感謝申し上げる。
前述したように改訂版ではエキスパートオピニオンも重視し、初版のクリニカルクエスチョンで多かったGradeI評価を減らすようにした。しかし、いまだ十分に解決されていない研究課題も多く、さらなるエビデンスの高い研究がなされることにより現在の推奨Gradeがより高い推奨Gradeに変わり、また新しい知見が加わり、より充実したガイドラインとなることを切望する。そして本疾患に悩む患者、それを治療する臨床医にとってかけがえのないガイドラインになるようにさらなるエビデンスの高い研究が望まれ、努力することが期待される。
ただし本ガイドラインはあくまでも「ガイドライン」であり、100%の患者に適用されるものではない。すなわち、個々の頚椎症性脊髄症の症例、そしてそれを治療する臨床医の実際の現場での裁量を規定するものではない。実際にはこのガイドラインとは違った判断がなされることも当然で、まして医事紛争に利用されるべきものではないことも強調しておく。実際の医療現場では個々の症例に応じたテーラーメードな治療がその場の医師の裁量で行われ、このガイドラインがそれを規制するものではない。
最後に、本ガイドラインが頚椎症性脊髄症を治療するすべての臨床医の先生方のお手元に置かれ、お役に立てることを心より願っている。
2015年3月
日本整形外科学会
頚椎症性脊髄症診療ガイドライン策定委員会
委員長 加藤義治
頚椎症性脊髄症のガイドラインが7年ぶりに改訂された。日本整形外科学会のガイドライン策定委員会による第2版である。本ガイドラインの特筆すべき点は、エビデンスレベルだけでなく、委員会としてのエキスパートオピニオンが加味されて、推奨gradeが決められている点である。
ガイドラインが最初に導入されたころには、エビデンスレベルが重要視されていた。しかし、高いエビデンスレベルを得るには、100例以上のrandomized controlled trial(RCT)が必要である。RCTには介入群と非介入群あるいは対象群を無作為に割付けることが求められるが、特に手術においては、この無作為割付けを患者に納得してもらうことが容易ではない。患者の多くは、その方法よりも主治医個人を信じて手術を受ける。そのため、主治医の意思が反映されることのないRCTへの参加を躊躇するわけである。また担当医も、RCTは医療倫理的に釈然としないものを感じることがある。結果、薬と違って外科手術のエビデンスはいつまでたっても低いままで、clinical question(CQ)に対する回答も推奨gradeI(エビデンス不足)が多い状態であった。一方、ガイドラインは治療指針でもあり、推奨すべき治療が明示されていなければ参照する意味がない。両者の間で、ガイドラインの作り手も悩みが深かったものと思う。そこで、本改訂版ではエキスパートオピニオンを優先するという方針を明確にしたわけである。
その結果、第1版からエビデンスレベルが変更されたCQがいくつかある。たとえば、「頚椎の不安定性が脊髄症の発症に関与している場合がある」は、grade Iからgrade Cになった。臨床的には、不安定性が脊髄症発症に影響すると感じている専門家が多いためであろう。また手術適応については、「進行性あるいは長く持続する脊髄症、軽症でも保存療法で効果がなく脊髄圧迫の強い青壮年者が適応である」も、grade Iからgrade Cとなった。つまり、症状が軽くても脊髄圧迫が強ければ手術をすすめる必要があり、漫然とした保存的治療で悪化した場合には逆に保存的治療が問題とされるかもしれないということである。このように、本ガイドラインは踏み込んだ記述が多く、臨床上の疑問により明確に回答しているように思う。
ガイドラインはその時代の標準的治療法を示すものとして重要である。診療は基本的にガイドラインに準拠して行われるべきであり、それに反した診断・治療を行う場合にはそれなりの理由が必要となる。最新の学会発表や論文の集大成ともいえるガイドラインを座右におくことで、少なくとも診断や手術に対する最新の考え方を学ぶことができるはずである。
臨床雑誌整形外科66巻11号(2015年10月号)より転載
評者●東京医科歯科大学整形外科教授 大川淳