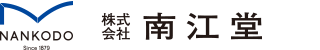肺MAC症診療Up to Date
非結核性抗酸菌症のすべて
| 編集 | : 倉島篤行/小川賢二 |
|---|---|
| ISBN | : 978-4-524-26833-7 |
| 発行年月 | : 2013年7月 |
| 判型 | : B5 |
| ページ数 | : 272 |
在庫
定価7,480円(本体6,800円 + 税)
- 商品説明
- 主要目次
- 序文
- 書評

肺MAC症を中心とした非結核性抗酸菌症について、基礎から診療の実際、最新知見まで幅広く網羅。2012年改訂「肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解」などの最新情報にも対応。好評書『結核Up to Date(改訂第3版)』と同様に、臨床の“スタンダード”となる一冊。専門医はもちろん、一般内科医、呼吸器・感染症診療に関わる医師のマストアイテム。
総論 非結核性抗酸菌症
1.肺非結核性抗酸菌症の日本と世界の疫学的動向−本当に増えているの?
a.疫学研究手法について
b.わが国の疫学研究
c.諸外国(北米、オーストラリア)における疫学研究の動向
d.ヨーロッパ、アジアにおける疫学調査の動向
2.非結核性抗酸菌の分類・同定Up to Date−DNAで何がわかるのか?
a.細菌の分類と同定
b.遺伝子解析による非結核性抗酸菌の同定
c.質量分析法による非結核性抗酸菌の同定
3.非結核性抗酸菌症の画像−なぜ中葉舌区なのか?
a.Mycobacterium avium complex(MAC)症
b.Mycobacterium kansasii症
4.非結核性抗酸菌症と環境−環境には何に注意すればよいのか?
a.水環境とMAC
b.土壌とMAC
c.動物とMAC
d.他の菌種と環境
5.非結核性抗酸菌とバイオフィルム−お風呂は感染源か?
a.抗酸菌のBFは
b.浴室内MACのBFは肺MAC症の感染源か
c.BFと病原性発現
d.BF関連遺伝子と転写制御
e.予防と消毒
6.非結核性抗酸菌症とHIV感染−相変わらず両者合併例は多い?
a.MAC
b.M.kansasii
c.その他のNTM
7.非結核性抗酸菌症とリウマチおよび生物学的製剤−新しい抗リウマチ薬は使えるのか?
a.生物学的製剤
b.生物学的製剤と抗酸菌感染症
c.RA固有の問題
d.生物学的製剤投与下に発症したNTM症
8.非結核性抗酸菌症の診断基準とその運用−2回菌がみつかればよいのか?
a.新しい診断基準にいたる経緯
b.わが国の2008年診断基準の内容と特徴
9.非結核性抗酸菌症の治療見解とその運用−どの薬剤がお勧めか?
a.わが国における肺NTM症治療見解作成の経緯
b.「改訂見解」肺MAC症に対する標準化学療法の解説と実際の運用
c.「改訂見解」肺M.kansasii症に対する標準化学療法の解説
10.非結核性抗酸菌症の外科治療−どういうときに切除するのか?
a.外科治療が必要なNTM症
b.日米のNTM症ガイドライン
c.どの程度化学療法を行ってから手術適応を判断するか
d.切除すべき病巣は
e.切除可能な主病巣の広がりは
f.術後の化学療法は
g.NTM症の外科治療成績
11.孤立結節影を示す非結核性抗酸菌症−MAC症を中心に、その臨床像と治療の考え方
a.孤立結節型肺MAC症の臨床像
b.孤立結節型肺MAC症の治療
12.非結核性抗酸菌症と肺癌−いろんなパターンがあるんです
a.肺MAC症・肺癌同時発見
b.肺MAC症先行の肺癌
c.肺癌先行の肺MAC症
d.肺癌が疑われた肺MAC症(孤立結節型)
13.非結核性抗酸菌症とCOPD−増えているのだろうか?
a.肺MAC症とCOPDの臨床疫学からみた関連性
b.COPD合併肺MAC症の検討
各論I 肺MAC症
1.肺MAC症の病理−結核と同じなのか? 何が違うのか?
a.線維空洞型肺MAC症
b.結節・気管支拡張型肺MAC症
c.過敏性肺炎型肺MAC症(hot tub lung)
d.全身播種型肺MAC症
2.肺MAC症のヒト遺伝子研究−MAC症にかかりやすい人はいるのか?
a.肺MAC症の遺伝素因について
b.単一遺伝子疾患としての抗酸菌感染症
c.肺MAC症に関わる遺伝因子の解析
d.遺伝子多型解析研究の現状と今後の課題
3.肺MAC症の菌遺伝子研究−日本の菌は違うのか?
a.MACの分子疫学解析法について
b.VNTR型別解析の応用例
c.MACの薬剤感受性遺伝子−マクロライド耐性について
d.菌側遺伝子の解析からみえてきた日本のMAC症の特徴
e.肺MAC症の病勢と菌遺伝学的解析
4.肺MAC症とサイトカイン−結核と違うのか?
a.自然免疫と獲得免疫
b.自然免疫は関係ないのか?
c.Nramp1(Slc11a1)の話
d.IFN-γの分泌量が少ないのが問題なのか?
e.Th1 vs Th2 vs Th17
f.IL-10はTh1型サイトカインを抑制しているのか?
g.抗酸菌特異的な抑制系が存在するのか?
5.MAC症診断における血清診断法−バイオマーカーになりうるのか?
a.肺MAC症診断の問題点
b.抗酸菌血清診断の歴史
c.MAC特異的血清診断、キャピリア(R)MAC抗体ELISAの開発
d.肺MAC症診断に対する有用性
e.免疫抑制状態患者での成績
f.偽陽性、偽陰性の問題
g.治療による抗体価の変化
h.血清診断が有用な場面
6.肺MAC症:画像経過と臨床像−治療していくとどのように変化するのか?
a.肺MAC症の病型
b.画像の経過に関して
c.病変の進展によって起こる臨床像の変化
7.肺MAC症とアミノグリコシド−どのくらい有効なのか?
a.アミノグリコシド系抗菌薬の特徴
b.アミノグリコシド系抗菌薬を含む治療と含まない治療の無作為化比較試験
c.最近のアミノグリコシド系抗菌薬を含めた多剤併用療法の治療成績
8.肺MAC症:化学療法の最適治療期間を考察する−何年続ければよいのか?
a.ATS/IDSAステートメントと肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解から
b.臨床データからの検証
c.私見を交えてのまとめ
9.肺MAC症と肺アスペルギルス症−肺NTM症は肺アスペルギルス症の予後を左右するのか?
a.NTM症はアスペルギルス症を発症しやすいか
b.肺NTM症、肺アスペルギルス症合併の現状−文献のまとめ
c.NTM発症からCNPA発症までの期間
d.NTM症例における慢性肺アスペルギルス症はどのように診断されているか
e.肺MAC治療と抗真菌薬について
f.症例呈示
10.肺MAC症と喀血治療−ずいぶん多いのだけれど?
a.喀血治療専門施設からみた肺MAC症と喀血
b.肺MAC症と喀血−文献的考察
c.喀血の治療
d.喀血症例提示
11.肺MAC症:診療のブレイクスルー−新たな治療戦略の可能性
a.治療開始時期の問題
b.治療薬の問題
c.治療期間の問題
d.外科治療併用
各論II 肺MAC症以外の非結核性抗酸菌症
1.肺M.kansasii症の臨床像と治療−化学療法で治癒可能な疾患
a.臨床像と診断
b.治療と予後
2.肺M.abscessus症の臨床−一番治療が難しいと聞くけど?
a.疫学
b.臨床像
c.胸部画像
d.診断
e.治療
f.治療の具体例
3.比較的まれな菌種の治療−聞いたこともないのだけれど
a.非結核性抗酸菌の分類と同定
b.稀少菌種の頻度
c.非結核性抗酸菌の感受性検査での問題点
d.まれな菌種による肺非結核性抗酸菌症の化学療法
4.まれな菌種の臨床
A.肺M.arupense症
B.肺M.chelonae症
C.肺M.fortuitum症
D.肺M.gordonae症
E.肺M.heckehornense症
F.肺M.kumamotonense症
G.肺M.kyorinense症
H.肺M.lentiflavum症
I.肺M.mageritense症
J.肺M.malmoense症
K.肺M.marinum症
L.肺M.massiliense症
M.肺M.peregrinum症
N.肺M.scrofulaceum症
O.肺M.shimoidei症
P.肺M.shinjukuense症
Q.肺M.simiae症
R.肺M.szulgai症
S.肺M.terrae症
T.肺M.triplex症
U.肺M.xenopi症
索引
編集後記
私はかつて非結核性抗酸菌症について、それは猫のようであると書いた。
「非結核性抗酸菌症は、結核症がKoch以来の由緒正しい血統書付きの名犬とすれば、猫のようである。いつのまにか住み着き、長い間何ともないと思っていると、ある日急に暴れ出し、犬ほどに力は強くないが、その行動は予測つき難く、ある日フイといなくなってしまうことすらある。たいがいの正しいと思ってする対処は殆ど無効であり、退治したと思っているとひっそりと端っこにいる。捉えどころがなく困惑していると、いつのまに野生の虎のような肉食獣の本性を現す。わが輩は猫である」
これは今でも変わらない。
肺非結核性抗酸菌症の診療に何十年も携わってきたのに、最も基本的な問題さえ解決されていない。
・なぜ増加しているのか?
・なぜ中高年女性に多いのか?
・なぜ中葉舌区から始まるのか?
・なぜin vitro抗菌力とin vivo抗菌力は一致しないのか?
・一般成人で約30%近くは非結核性抗酸菌に感染しているらしいのだが、それと発病の関係は一体どうなっているのか?
肺非結核性抗酸菌症の化学療法はマクロライド少量長期投与ではなく、マクロライド大量長期投与である。従来、私は合理的な処方と思われるなかでの最小投与量を長く行ってきた。例えばCAM800ではなく600とか、RFP450ではなく300とか。しかし、長期に観察していると、化学療法開始当初は臨床も画像もレスポンスし一度よくなるが再び悪化していく事例に多く遭遇した。
このような例では、投与量を例えばCAM800、RFP450にすると、再び臨床症状や画像経過は改善していく。つまり大量投与といっても、真の有効域の下限をフラついているのである。
RFP登場以前の昔の結核化学療法では、化学療法継続により画像所見がそれ以上改善しない時点をターゲットポイントとし、ターゲットポイント以後1〜1.5年、空洞がある場合は菌陰性化後3年間継続というのが推奨されていた。
大量長期投与を何とか減らそうと、肺非結核性抗酸菌症化学療法を概念的に初期強化、維持期、再感染防止の三つのphaseに区分し、それぞれの時期における理想的なprotocolを目指した。この考えでは、臨床的・画像的なターゲットポイントを達成すれば薬剤数あるいは投与量は段階的に削減していくことになる。
しかしこの試みが成果的に進行し、その後完全に薬剤freeを達成できたのは、術後の場合の他は自験例の5%以下の極めて軽微例に限られた。多くは削減段階での再悪化を来たし元のdoseへの復帰を余儀なくされた(しかしこれ自体は再びeffectiveである)。
コンサルテーションで訪れる例の多くは、数年間の化学療法後、何らかの理由による1〜2年の薬剤完全offという例が多く、その度に画像と排菌が段階的に進展悪化するというパターンに多く遭遇する。つまり現行薬剤では大量長期の継続にならざるを得ないし、またそれが最も好結果をもたらしているのも事実である。
結核菌と異なり、非結核性抗酸菌は多くの薬剤に対して獲得耐性ではなく自然耐性である。
そうであるならば将来、新規抗結核薬開発と同じようなスタンスで新規抗非結核性抗酸薬が登場してくるのか、疑問を持たざるを得ない。
結核症でヒトの肺に空洞などを来すのは、結核菌がヒト組織に障害をもたらす毒素を持っているわけではなく、侵入してきた結核菌を殺傷しようとする特異性免疫によるdelayed type hypersensitivityによって生じているのは既に実証された事実である。
ならば、非結核性抗酸菌症でもこの方面からのもっとスマートなアプローチがないのだろうか?
Crohn病は起炎菌(欧米の症例ではMycobacterium avium subspecies paratuberculose=MAP菌が起炎菌ではないかという説がかなり有力である)や機序の解明も不明な肉芽腫性疾患であるが、何らかの抗原に対する組織過剰反応が病態と思われ、そのCrohn病で臨床的にはTNF-α阻害薬が著効を示している。
TNF-α阻害薬の中でも膜受容体に結合する薬剤でないと有効でないことが判っているが、TNF-α阻害薬が受容体に結合することによりMAP菌貪食Mφはapoptosisに陥り、この断片化により細胞内寄生MAP菌も殺傷されるという仮説が立てられている。
結核菌は細胞内寄生菌でもあるが、細胞外でも十分増殖可能であるし、ヒト肺の病変部位ではむしろ細胞外の方が多い。
結核菌より細胞内寄生性格の強い非結核性抗酸菌症ならば、この種の治療法はあり得るのではないだろうか? と自問してみるが、非結核性抗酸菌よりも更に細胞内寄生の強い、というより細胞外では生存できない他の菌でも、この種の治療は困難である。
TNF-α阻害薬投与下でのレジオネラ菌、リステリアそしてハンセン病の発症さえ警告されている。つまり感染症制圧において、新たな方法論の中で、主役ではなくても、併用治療としてどうしても感受性抗菌薬は必須のようである。
非結核性抗酸菌が細胞内でどのようにdormancyを保つかは不明であるが、結核菌ではdeepなdormant stateからreplicating stateに蘇生させるresuscitate promoting factorが発見されている。これの類似作用物を用いれば、dormant stateに効く抗菌薬がなくてもactively replicatingな状態のみに有効な抗菌薬で支持治療としては十分な資格があるのではないだろうか?
まだ非結核性抗酸菌に対してそのような薬剤さえないのが現状ではあるが、本書がこのような将来への夢を実現させるひとつのキッカケになるのを希望して止まない。
2013年6月
倉島篤行
近年とくに問題となっている高齢者や易感染宿主(HIV患者、免疫抑制薬や生物学的製剤使用など)の増加と合併する呼吸器感染症への対応は、喫緊の課題である。なかでも肺Mycobacterium avium complex(MAC)症はいまだ決定的な治療法が存在しない難治性感染症であり、近年その罹患率は増加している。呼吸器内科医に限らず、日常診療において本病名を目にする機会が増えたことを実感する毎日である。しかし実際は、治療方針の決定に際し明確なエビデンスに乏しいため、臨床医の総合的判断に委ねられる部分が大きい。このような背景から、すでに改訂第3版が発刊されている『結核Up to Date』と並んで、非結核性抗酸菌症に特化した本書の登場を今や遅しと待ち望んでいたのは私だけではないであろう。
本書の編者は抗酸菌の診療・研究においてわが国のトップリーダーである、複十字病院の倉島篤行先生と国立病院機構東名古屋病院の小川賢二先生であり、また著者の多くは非結核性抗酸菌症の臨床経験・実績が豊富な先生方によって構成されている。どの著者も肺MAC症に関するEBMの記載にとどまらず、臨床現場で遭遇する頻度の高い課題の一つ一つに明快に対応すべく、豊富な臨床経験に基づいて多数の画像や図表を交えて解説している。総論では肺MAC症の疫学、診断、治療法(外科治療の適応も含む)や他疾患(HIV感染、関節リウマチ、肺癌、COPD)に合併した場合の対応についてコンパクトかつ詳細に述べられている。各論は二部構成となっており、各論Iでは肺MAC症の病理学的考察、遺伝因子の関与や感染免疫などの基礎医学的内容に加えて、治療開始時期や治療期間、喀血時や肺アスペルギルス症を合併した際の治療方針など、いっそう実践的な内容に踏み込んで私見を交えながらの解説がなされている。各論IIではMAC以外の非常に稀有な菌種にいたるまで、実際の症例を提示しながらわかりやすく解説されている。
また本書では、実際に臨床現場で直面する問題点とジレンマに対し、著者の豊富な臨床経験に裏打ちされた実践的な私見が随所に述べられており、きわめて興味深い。たとえば、生物学的製剤使用中に発症したNTMに対しては、『関節リウマチ(RA)に対するTNF阻害薬使用ガイドライン(2012年改訂版)』において生物学的製剤の中止が原則とされている。しかし生物学的製剤はRA患者の切り札になり得る治療法であり、その中止は患者にとってきわめて重大な問題である。そのため本書では「患者との完全な合意と理解、厳重な監視下などの条件を満たせば、抗菌療法の有効性を確認した後での生物学的製剤の再投与も選択肢の一つとなり得る」と述べられている。著者が経験する臨床現場の日常が如実に反映されており、肺MAC症診療に対する著者の熱意が伝わり読んでいて心地よい。
また、本書の随所に散りばめられた「Tea Break」では、総論・各論とは異なり、MACをはじめとする非結核性抗酸菌症の知られざる一面や研究領域の新たな展開などがわかりやすく解説されており、本書の魅力をさらに高めることに貢献している。
肺MAC症は呼吸器専門医だけが認知する特殊な感染症という立場から、一般臨床医が知っておくべきcommon diseaseへと変貌を遂げた。本書には肺MAC症の疫学、診断、治療について実地臨床で必要とされる情報がわかりやすく記載されており、若手医師や非専門医でも手に取りやすい内容となっている。また、各論には遺伝子解析や感染免疫といった専門医も読み応えのある学術性の高い内容も含まれている。“肺MAC症診療の指南書”として、日々の臨床や研究にぜひ役に立てていただきたい一冊である。
臨床雑誌内科113巻5号(2014年5月号)より転載
評者●長崎大学病院病院長 河野茂
本書を読ませていただいた。筆者は呼吸器外科医で、まれに免疫不全患者の真菌症の区域切除などの手術もあるが、肺腫瘍、気胸が主で、実際には非結核性抗酸菌症の手術はほとんど行ったことがない。肺癌と考えて手術を行ったらMycobacterium avium complex(MAC)であった症例がいくつかと、非結核性抗酸菌症を生じ、治療を継続している気管支拡張症で、血痰やある程度の喀血で手術あるいは気管支動脈塞栓術の適応を相談される症例がほとんどである。それでも胸部異常陰影の診断で気管支鏡検査を行い、MACを生じ、どうしようかと悩んだ経験はある。本書は、もちろん非結核性抗酸菌症の専門家にも十分耐えうる内容であると確信しているが、われわれのような非結核性抗酸菌症を、結核でないのでとりあえず感染性がないことに安心し、ゆっくり外来で誰かに相談しようと考える専門でない医師たちに対して、非結核性抗酸菌症の全体像をわかった気分にさせてくれる。
序文の「わが輩は猫である」については、本当にそのとおりなのであろう。総論では、副題が「本当に増えているの?」、「DNAで何がわかるのか?」、「なぜ中葉舌区なのか?」、「どういうときに切除するのか?」、「MAC症を中心に、その臨床像と治療の考え方」、「いろんなパターンがあるんです」と、そのままズバリ、知りたいことに応えてくれる内容である。たくさんある「Tea Break」は、突然一気に深く専門領域に導いてくれる。各論もそれぞれ読者の位置により違いがあると思われるが、内容も濃く参考になると思われる。編集者が読者を意識して、各執筆者の書きたいことを誘導する優れた手法に感じ入った次第である。
筆者が各論で特に気に入ったのは、「肺MAC症と喀血治療」の項である。石川秀雄先生のグループほど多くないが、筆者の科でも、喀血の治療として超選択的気管支動脈塞栓術(BAE)を行っている。塞栓物質はほとんど金属コイルで、超選択的に行っている。「呼吸器外科医の間でもその有用性について十分な認識がされていない」と書いてあるが、そのとおりである、わが意を得たりと感じ入った。放射線科の医師たちでさえ、いまだにスポンゼルやジェルパートを使用し、血痰、喀血の再発が多いのは当然であるという認識をもっている。前脊髄動脈を誤って塞栓してしまうのは超選択的であれば非常にまれであり、非常に減少していると筆者も考えている。
本書は、常に手元にぜひおいておきたい本の一つになった。
胸部外科67巻1号(2014年1月号)より転載
評者●東京女子医科大学呼吸器外科教授 大貫恭正